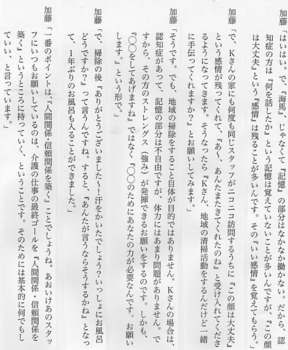向精神薬―専門医レベルの知識がないと優良誤認してしまう [向精神薬]
向精神薬に関する製薬企業パンフレットの読み方
ポイント
●新薬の有効性と安全性だけを強調する,実態と合わない精神薬理用語による分類がある.
●うつ病自然寛解率や不眠症治療薬のプラセボ効果を知らないと,薬効を過大評価してしまう.
●治験の心理検査で出た瑣末な結果を,さも重大なことのように見せかけるパンフレットがある.
●専門医レベルの知識がないと優良誤認してしまうため,多くの内科医にとって,向精神薬に関する製薬企業パンフレットは有害無益である.
…(中略)…
自然経過を示さずに治療前後を比較
うつ病の,治療なしでの寛解率は2年で80~90%である.主な治療は休息であり,場合によっては抗うつ薬を使う.このように,うつ病はあまりにも自然回復しやすいので,臨床試験において実薬群とプラセボ群の間に有意差が出にくい疾患である.ゆえに製薬会社が医師向けパンフレットを作る際には,自然経過のデータをできるだけ隠すのが定石になる.うつ病の自然寛解率を知らない医師なら,薬物使用後に生じた改善をもっぱら薬によるものと誤認してくれるからである.典型的手口は,抗うつ薬による治療前と治療後をそのまま直接比較する図である.参考までに2011年に発売されたSSRIであるエスシタロプラムの国内治験データを表1に示す.プラセボ群,実薬群ともうつ病の重症度が同じように改善しているのがわかる.
また,不眠症治療においてプラセボ効果が存在することは広く知られている.ゆえにここでもプラセボ群のデータをできるだけ隠すのが定石になる.例えばメラトニン受容体作動薬であるラメルテオンの国内第Ⅲ相試験において,プラセボ群,実薬群ともに自覚的睡眠潜時の改善がみられ,プラセボ群と実薬群の間に生じた差は2.36分だった.言い換えるとラメルテオンに期待できる効能は寝つきが142秒良くなることである.実薬群だけの成績を示したパンフレットでは,この数字が見えない.
瑣末な結果を重大なことのように表示
抗認知症薬の国内治験における主要評価項目は,多くの場合ADAS(Alzheimer Disease Assessment Scale)とCIBIC(Clinician's Interview Based Impression of Change)の2つである.前者は認知機能を,後者は全般臨床症状を評価する.治験はこのADASとCIBICの両方でプラセボへの優越性がみられた場合のみ,薬の有効性が証明できるというデザインになっているため,この2つに有意差がなければ,ほかの評価項目で有意差がみられても,それは瑣末な結果に過ぎない.しかし,p値が0.05を下回っている項目があると,それが何であっても重大な結果であるかのように表示するのがパンフレットの典型的手口である.
例えば,日常生活動作を評価するDAD(Disability Assessment for Dementia)はCIBICの下位尺度の1つである.プラセボ群と実薬群の間でCIBICに差はなかったが,DADでのみp<0.05が出た臨床試験を題材に,DADの成績だけを図表化しCIBICについては一切出さなかったパンフレットがある.何が主要評価項目で何が下位尺度に過ぎないのかは,パンフレットだけでは区別がつかない.
おわりに
以上で明らかなように,向精神薬に関する製薬企業パンフレットは優良誤認させる表現にあふれている.読者に専門医レベルの精神科の知識がない限り,優良誤認させられるのは必至なので,多くの内科医にとって向精神薬に関する製薬企業パンフレットは有害無益であり,受け取らずにそのまま製薬企業に返すのが唯一の正解である.必要最低限の情報は添付文書に書いてある.不眠症,うつ,認知症の領域では実薬の効果はプラセボと大差なく,無理に薬を使う根拠はどこにもない.
【小田陽彦:向精神薬に関する製薬企業パンフレットの読み方. medicina Vol.53 1996-1998 2016】

私の感想:
何とも凄い論文ですね。
私も認知症は専門領域ですし、うつ病は自分が患った病気ですので薬効などに関してはかなり詳しい方です。ただ、統計学的な専門知識に欠けているところがあるので、正確に認識していない部分もあるように思います。
ドネペジル(商品名:アリセプト![[レジスタードトレードマーク]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/219.gif) )のプラセボ効果に関しては、アピタルにおいて何度も紹介しましたね。
)のプラセボ効果に関しては、アピタルにおいて何度も紹介しましたね。
そのうちの一つを以下にご紹介します。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第608回『役割と生きがいの賦与―ドネペジルの効果の特徴』(2014年9月11日公開)
メマンチンは認知症の行動・心理症状(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia;BPSDにおいては、興奮/攻撃性、妄想、怒りっぽさ(易刺激性)/情緒不安定といった項目(症状)において特に有効性が高く、また、試験開始時には上記の症状を認めなかった患者群においてもメマンチン療法により、後の症状発現率が有意に低下したことが注目されております。一方、ドネペジル(商品名:アリセプト![[レジスタードトレードマーク]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/219.gif) )においては、アパシー、不安、抑うつといったBPSDに対して効果が高い(Gauthier S, Feldman H, Hecker J et al:Efficacy of donepezil on behavioral symptoms in patients with moderate to severe Alzheimer's disease. Int Psychogeriatr Vol.14 389-404 2002)という違いがあります。
)においては、アパシー、不安、抑うつといったBPSDに対して効果が高い(Gauthier S, Feldman H, Hecker J et al:Efficacy of donepezil on behavioral symptoms in patients with moderate to severe Alzheimer's disease. Int Psychogeriatr Vol.14 389-404 2002)という違いがあります。
ちょうどよい機会ですので、ドネペジルの中核症状に対する効果についても言及しておきましょう。
シリーズ第98回『アルツハイマー病の治療薬 医療を支えるわずかな望み――ドネペジル(その3)』におきまして、ドネペジルの有効率は、「最終全般臨床症状評価において5mg群はプラセボ群と比較して有意に優れていた。『改善』以上の割合は5mg群17%、プラセボ群13%、『軽度悪化』以下の割合は5mg群17%、プラセボ群43%であった。」という添付文書のデータをご紹介しました。
MMSE(Mini-Mental State Examination)が12~24点の軽度および中等度アルツハイマー病を対象として(連続112例の検討)、ドネペジルの効果を評価した報告があります(Shimizu S, Hanyu H, Sakurai H et al:Cognitive profiles and response to donepezil treatment in Alzheimer's disease patients. Geriatr Gerontol Int Vol.6 20-24 2006)。MMSEで4点以上改善した場合をresponder(レスポンダー)、それ以外をnon-responder(ノンレスポンダー)と判定した場合、ドネペジル療法のresponderは34例(30%)、non-responderは78例(70%)であったそうです。なお、MMSEのサブスケール別にみると、「場所見当識」、「注意力・計算力」、「言語機能」の3領域が有意な改善したことがわかったそうです。
なお、「全般的認知機能検査Mini-Mental State Examination(MMSE)では、通常、MMSEが3点以上増加した場合、『有効』と判定する。」(目黒謙一:心理社会的介入と薬物療法によるアプローチ─問題提起─. 老年精神医学雑誌 第24巻増刊号-Ⅰ 98-102 2013)という意見もあり、MMSEが何点以上の改善をもってして有効と判断するのかは明確には統一されておりません。
ポイント
●新薬の有効性と安全性だけを強調する,実態と合わない精神薬理用語による分類がある.
●うつ病自然寛解率や不眠症治療薬のプラセボ効果を知らないと,薬効を過大評価してしまう.
●治験の心理検査で出た瑣末な結果を,さも重大なことのように見せかけるパンフレットがある.
●専門医レベルの知識がないと優良誤認してしまうため,多くの内科医にとって,向精神薬に関する製薬企業パンフレットは有害無益である.
…(中略)…
自然経過を示さずに治療前後を比較
うつ病の,治療なしでの寛解率は2年で80~90%である.主な治療は休息であり,場合によっては抗うつ薬を使う.このように,うつ病はあまりにも自然回復しやすいので,臨床試験において実薬群とプラセボ群の間に有意差が出にくい疾患である.ゆえに製薬会社が医師向けパンフレットを作る際には,自然経過のデータをできるだけ隠すのが定石になる.うつ病の自然寛解率を知らない医師なら,薬物使用後に生じた改善をもっぱら薬によるものと誤認してくれるからである.典型的手口は,抗うつ薬による治療前と治療後をそのまま直接比較する図である.参考までに2011年に発売されたSSRIであるエスシタロプラムの国内治験データを表1に示す.プラセボ群,実薬群ともうつ病の重症度が同じように改善しているのがわかる.
また,不眠症治療においてプラセボ効果が存在することは広く知られている.ゆえにここでもプラセボ群のデータをできるだけ隠すのが定石になる.例えばメラトニン受容体作動薬であるラメルテオンの国内第Ⅲ相試験において,プラセボ群,実薬群ともに自覚的睡眠潜時の改善がみられ,プラセボ群と実薬群の間に生じた差は2.36分だった.言い換えるとラメルテオンに期待できる効能は寝つきが142秒良くなることである.実薬群だけの成績を示したパンフレットでは,この数字が見えない.
瑣末な結果を重大なことのように表示
抗認知症薬の国内治験における主要評価項目は,多くの場合ADAS(Alzheimer Disease Assessment Scale)とCIBIC(Clinician's Interview Based Impression of Change)の2つである.前者は認知機能を,後者は全般臨床症状を評価する.治験はこのADASとCIBICの両方でプラセボへの優越性がみられた場合のみ,薬の有効性が証明できるというデザインになっているため,この2つに有意差がなければ,ほかの評価項目で有意差がみられても,それは瑣末な結果に過ぎない.しかし,p値が0.05を下回っている項目があると,それが何であっても重大な結果であるかのように表示するのがパンフレットの典型的手口である.
例えば,日常生活動作を評価するDAD(Disability Assessment for Dementia)はCIBICの下位尺度の1つである.プラセボ群と実薬群の間でCIBICに差はなかったが,DADでのみp<0.05が出た臨床試験を題材に,DADの成績だけを図表化しCIBICについては一切出さなかったパンフレットがある.何が主要評価項目で何が下位尺度に過ぎないのかは,パンフレットだけでは区別がつかない.
おわりに
以上で明らかなように,向精神薬に関する製薬企業パンフレットは優良誤認させる表現にあふれている.読者に専門医レベルの精神科の知識がない限り,優良誤認させられるのは必至なので,多くの内科医にとって向精神薬に関する製薬企業パンフレットは有害無益であり,受け取らずにそのまま製薬企業に返すのが唯一の正解である.必要最低限の情報は添付文書に書いてある.不眠症,うつ,認知症の領域では実薬の効果はプラセボと大差なく,無理に薬を使う根拠はどこにもない.
【小田陽彦:向精神薬に関する製薬企業パンフレットの読み方. medicina Vol.53 1996-1998 2016】
私の感想:
何とも凄い論文ですね。
私も認知症は専門領域ですし、うつ病は自分が患った病気ですので薬効などに関してはかなり詳しい方です。ただ、統計学的な専門知識に欠けているところがあるので、正確に認識していない部分もあるように思います。
ドネペジル(商品名:アリセプト
そのうちの一つを以下にご紹介します。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第608回『役割と生きがいの賦与―ドネペジルの効果の特徴』(2014年9月11日公開)
メマンチンは認知症の行動・心理症状(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia;BPSDにおいては、興奮/攻撃性、妄想、怒りっぽさ(易刺激性)/情緒不安定といった項目(症状)において特に有効性が高く、また、試験開始時には上記の症状を認めなかった患者群においてもメマンチン療法により、後の症状発現率が有意に低下したことが注目されております。一方、ドネペジル(商品名:アリセプト
ちょうどよい機会ですので、ドネペジルの中核症状に対する効果についても言及しておきましょう。
シリーズ第98回『アルツハイマー病の治療薬 医療を支えるわずかな望み――ドネペジル(その3)』におきまして、ドネペジルの有効率は、「最終全般臨床症状評価において5mg群はプラセボ群と比較して有意に優れていた。『改善』以上の割合は5mg群17%、プラセボ群13%、『軽度悪化』以下の割合は5mg群17%、プラセボ群43%であった。」という添付文書のデータをご紹介しました。
MMSE(Mini-Mental State Examination)が12~24点の軽度および中等度アルツハイマー病を対象として(連続112例の検討)、ドネペジルの効果を評価した報告があります(Shimizu S, Hanyu H, Sakurai H et al:Cognitive profiles and response to donepezil treatment in Alzheimer's disease patients. Geriatr Gerontol Int Vol.6 20-24 2006)。MMSEで4点以上改善した場合をresponder(レスポンダー)、それ以外をnon-responder(ノンレスポンダー)と判定した場合、ドネペジル療法のresponderは34例(30%)、non-responderは78例(70%)であったそうです。なお、MMSEのサブスケール別にみると、「場所見当識」、「注意力・計算力」、「言語機能」の3領域が有意な改善したことがわかったそうです。
なお、「全般的認知機能検査Mini-Mental State Examination(MMSE)では、通常、MMSEが3点以上増加した場合、『有効』と判定する。」(目黒謙一:心理社会的介入と薬物療法によるアプローチ─問題提起─. 老年精神医学雑誌 第24巻増刊号-Ⅰ 98-102 2013)という意見もあり、MMSEが何点以上の改善をもってして有効と判断するのかは明確には統一されておりません。
DLB:アリセプトの投与が錐体外路症状の出現率を高めるか? [レビー小体型認知症]
【森 悦朗, Ikeda M, Nakagawa M, Miyagishi H, Yamaguchi H, Kosaka K: Effects of ドネペジル on Extrapyramidal Symptoms in Patients with Dementia with Lewy Bodies - A Secondary Pooled Analysis of Two Randomized-Controlled and Two Open-Label Long-Term Extension Studies. Dement Geriatr Cogn Disord, 40 (3-4), 186-198 (2015)】
Abstract
Background/Aims: The aim of this study was to clarify the effects of donepezil on extrapyramidal symptoms in patients with dementia with Lewy bodies (DLB). Methods: Using pooled datasets from phase 2 and 3, 12-week randomized, placebo-controlled trials (RCT, n = 281) and 52-week open-label long-term extension trials (OLE, n = 241) of donepezil in DLB, the effects of donepezil on the incidence of extrapyramidal adverse events (AEs) and on the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) part III were assessed, and potential baseline factors affecting the AEs were explored. Results: The RCT analysis did not show significant differences between the placebo and active (3, 5, and 10 mg donepezil) groups in extrapyramidal AE incidence (3.8 and 6.5%, p = 0.569) and change in the UPDRS (mean ± SD: -0.2 ± 4.3 and -0.6 ± 6.5, p = 0.562). In the OLE analysis (5 and 10 mg donepezil), the incidence did not increase chronologically; all AEs leading to a dose reduction or discontinuation except one were relieved. The UPDRS was unchanged for 52 weeks. An exploratory multivariate logistic regression analysis of the RCTs revealed that donepezil treatment was not a significant factor affecting the AEs. Baseline severity of parkinsonism was a predisposing factor for worsening of parkinsonism without significant interactions between donepezil and baseline severity. Conclusion: DLB can safely be treated with donepezil without relevant worsening of extrapyramidal symptoms, but treatment requires careful attention to symptom progression when administered to patients with relatively severe parkinsonism.
Introduction
Dementia with Lewy bodies (DLB) is the second most common form of senile dementia following Alzheimer's disease (AD) [1]. The core clinical features of DLB include neuropsychiatric symptoms and parkinsonism as well as cognitive impairment characterized by deficits in attention, executive function, and visual perception [2]. The cholinergic loss and a choline acetyltransferase activity deficit with preserved postsynaptic cortical muscarinic and nicotinic receptors [3,4,5] rationalizes the use of cholinesterase inhibitors (ChEIs) in DLB. The favorable potential of ChEls such as galantamine, rivastigmine, and donepezil has been demonstrated in previous studies [6,7,8,9,10,11]. The phase 2 and 3 trials of donepezil in patients with DLB have added to the accumulating evidence of the efficacy and safety of donepezil in terms of cognitive, behavioral, and global function in DLB, even for long durations, without increasing the risk of clinically significant safety events [12,13,14,15].
It has been reported that 25-50% of patients with DLB have parkinsonism at the time of diagnosis and that 75-80% of such patients eventually develop it [16], although the exact proportion is still controversial. In a natural course, the symptoms could worsen with a speed comparable to Parkinson's disease (PD) [17]. The cholinergic interneurons synapse on the GABAergic striatal neurons that project to the globus pallidus. The cholinergic actions inhibit striatal cells of the direct pathway and excite striatal cells of the indirect pathway. Thus, ChEIs augment cholinergic function, which may oppose the effects of dopamine on the direct and indirect pathways exacerbating parkinsonism in DLB, in which nigrostriatal dopaminergic neurons have been lost [18,19,20,21]. On purely theoretical grounds, ChEI administration targeting cognitive impairment and behavioral symptoms may exacerbate parkinsonism. Despite studies showing that ChEIs did not affect parkinsonism and which did not replicate the possible untoward effects in patients with DLB or PD dementia (PDD) [22,23], concerns over a possible influence on the extrapyramidal symptoms still linger due to a shortage of evidence from large-scale, placebo-controlled, or long-term studies especially in DLB and require further confirmation.
As in diseases like DLB treatment for one symptom may precipitate others [24] and the combination or severity of the associated multiple, multi-dimensional symptoms varies by patient, a large-scale comprehensive study is essential. Our trials of donepezil in patients with DLB consist of two randomized, double-blind, placebo-controlled trials (RCT) and two open-label long-term extension studies (OLE) and enrolled a large group of patients that may embody patients with diverse demographic characteristics and clinical symptom manifestations, which the current diagnosis of probable DLB may encompass. We therefore developed two types of comprehensive pooled datasets from two RCTs and two OLEs of donepezil for DLB. RCTs provide information with minimized bias, while OLEs involve more patient-years of exposure to donepezil and may thus disclose adverse effects which are not observed in the parent RCTs. Using these datasets of the largest scale ever in DLB, we analyzed the effect of donepezil on the occurrence and worsening of extrapyramidal symptoms in patients with DLB.
Methods
Design of the Phase 2 and 3 Studies
This analysis pooled the data from the phase 2 and 3 studies of donepezil for DLB conducted in Japan. The phase 2 studies, consisting of a RCT (clinicaltrials.gov reference: NCT00543855) and a subsequent OLE (clinicaltrials.gov reference: NCT00598650), were conducted as two sequential protocols. A 12-week randomized, double-blind, placebo-controlled exploratory study (phase 2 RCT) was first conducted to investigate the efficacy and safety of donepezil at 3, 5, and 10 mg/day starting in 2007 (fig. 1a) [12]. In the patients who completed this RCT, the safety and efficacy of long-term administration at 5 mg were further investigated in the following 52-week OLE (phase 2 OLE) (fig. 1b) [13]. The phase 3 study (clinicaltrials.gov reference: NCT01278407) was conducted as a single protocol consisting of an RCT phase and a subsequent OLE phase. A 16-week randomized, double-blind, placebo-controlled comparative study consisting of a 12-week confirmatory phase (phase 3 RCT) (fig. 1a) [14] and a 4-week transition period and a subsequent 36-week OLE phase were conducted starting in 2011 for a total duration of 52 weeks (phase 3 OLE) (fig. 1b) [15]. The aim was to confirm the superiority of donepezil at 5 and 10 mg/day for 12 weeks over placebo with regard to both cognitive function and behavioral symptoms and to evaluate the safety and efficacy of long-term administration of 10 mg/day for 52 weeks. Each study was conducted in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki. The protocols were approved by the institutional review board at each participating center.
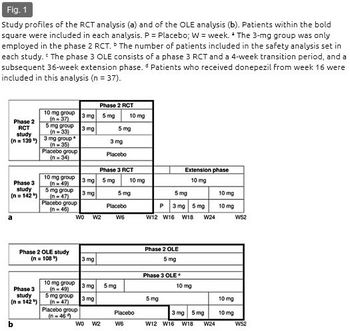
Patients
The inclusion and exclusion criteria were the same in both RCTs. The inclusion criteria were patients aged ≥50 years with probable DLB fulfilling the consensus diagnostic criteria [2], with mild to moderate-severe dementia [10-26 points on the Mini-Mental State Examination (MMSE) and Clinical Dementia Rating ≥0.5], behavioral symptoms or cognitive fluctuation [Neuropsychiatric Inventory (NPI)-plus ≥8 (rated on 12 items: original 10 NPI items + sleep [25,26] + Cognitive Fluctuation Inventory [27,28])], and with caregivers who could routinely stay with the patients, provide information for this study, assist with treatment compliance, and escort them to required visits.
The exclusion criteria included PD that was diagnosed at least 1 year prior to the onset of dementia; focal vascular lesions on an MRI or CT that might cause cognitive impairment; other neurological or psychiatric diseases; complications or a history of severe gastrointestinal ulcers, severe asthma, or obstructive pulmonary disease; systolic hypotension (<90 mm Hg); bradycardia (<50 bpm); sick sinus syndrome; atrial or atrioventricular conduction block; QT interval prolongation (≥450 ms); severe parkinsonism (Hoehn and Yahr stage ≥4) [29], and treatment with ChEIs or any investigational drug within 3 months prior to screening. ChEIs, antipsychotics, and anti-Parkinson drugs were not allowed during the study, except for levodopa and dopamine agonists, of which only stable doses were allowed during the RCTs.
Written informed consent was obtained from the patient (if at all possible) and his/her primary family member before initiating the study procedures.
Donepezil Administration
In the phase 2 RCT, the patients were randomized to placebo, 3, 5, or 10 mg/day of donepezil (placebo, 3-, 5-, and 10-mg groups) (fig. 1a). In the subsequent phase 2 OLE, all patients received donepezil at 5 mg/day (fig. 1b). Donepezil administration in the 5- and 10-mg groups started with a 2-week titration period with a 3-mg dose, which was applied in all of the studies.
In the phase 3 RCT, the patients were randomized to placebo, 5, or 10 mg/day (placebo, 5-, or 10-mg group) (fig. 1a). Since the phase 3 study incorporated the RCT and OLE phases, the duration of donepezil administration in the phase 3 OLE differed by treatment group: 52 weeks for the 5- and 10-mg groups (10 mg administration from week 24 and 6, respectively) with a 12-week overlap with the phase 3 RCT, and 36 weeks for the placebo group (3 mg titration from week 16, 5 mg administration from week 18, and 10 mg from week 24) (fig. 1b).
In the OLEs, a dose reduction to 3 mg in the phase 2 OLE or to 5 mg after week 24 in the phase 3 OLE was allowed upon emergence of a safety concern.
Summary of the Results of the Phase 2 and 3 Studies
The results of the phase 2 and 3 studies are reported in detail elsewhere [12,13,14,15]. Briefly, in phase 2, the RCT showed that donepezil significantly improved cognitive, behavioral, and global functions with good tolerability, and the OLE demonstrated that administration was well tolerated even for a long duration and that the effect on cognitive and behavioral impairment was maintained for up to 52 weeks. In phase 3, although the RCT failed to confirm a superiority concerning the behavioral symptoms over placebo, it confirmed the efficacy concerning cognitive function (one of the co-primary endpoints) without serious safety concerns. The OLE demonstrated a lasting improvement in cognitive function for up to 52 weeks, without increasing the risk of clinically significant safety events.
Datasets
The safety data regarding extrapyramidal symptoms derived from these studies were pooled in two ways: RCT and OLE (fig. 1). The datasets of the two RCTs were pooled and analyzed according to allocated treatment during the 12-week period: placebo, 3-, 5-, or 10-mg groups (n = 281) (fig. 1a). The dataset derived from all patients receiving donepezil via long-term administration [i.e. phase 2 OLE and phase 3 OLE (whole period of phase 3: RCT + OLE)] was pooled and analyzed (n = 241) (fig. 1b).
Assessment of Extrapyramidal Symptoms
The influence on extrapyramidal symptoms was evaluated according to the incidence of extrapyramidal adverse events (AEs) and the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) part III [30]. To reduce interrater and intrarater variability, an advanced rater training was conducted, a fixed rater was involved in the assessment of each patient in principle, and an elaborate monitoring was made throughout the study period. Of all the AEs which occurred during the studies (coded according to the Preferred Terms of the Medical Dictionary for Regulatory Activities), the following were identified as extrapyramidal AEs after discussion by the central committee: parkinsonism, rigidity, tremor, camptocormia, gait difficulty, and akinesia. The UPDRS part III was conducted every 12 weeks in the phase 2 RCT and in phase 3, and every 24 weeks in the phase 2 OLE.
Statistical Analysis
This secondary analysis was based on the safety analysis set of each study, which comprised all patients who received at least one dose of donepezil and had safety assessment data. For the analysis of the RCTs, the incidence of extrapyramidal AEs was summarized by treatment group and compared between the placebo and each active group using Fisher's exact test. The change in the UPDRS part III total and subscale score from baseline was compared between the placebo and each treatment group using analysis of covariance (ANCOVA) with the baseline values as covariates. Subscales were predefined as the following four symptoms: tremor, akinesia, rigidity, and postural instability and gait difficulty, with score ranges of 0-28, 0-36, 0-20, and 0-16, respectively [31,32]. For the analysis of OLEs, the incidence of extrapyramidal AEs was calculated. The UPDRS part III scores were analyzed using Student's paired t test.
To identify any potential baseline factors that may contribute to the extrapyramidal AEs, the incidence was calculated for subgroups stratified by the potential factors, and univariate and multivariate logistic regression analyses were subsequently conducted. Potential factors included endogenous factors (sex, age, and body weight) and symptom-related factors [UPDRS part III score, Hoehn and Yahr stage (≤2 or 3), and use of anti-Parkinson drugs (use or nonuse)]. In multivariate analyses, either the UPDRS part III score or the Hoehn and Yahr stage was included in the model because of the high correlation between them. In the analysis of the RCTs, the interaction between the treatment groups and factors was tested for each symptom-related factor using a logistic regression analysis. Each interaction was to be included in the model when significance was detected.
Values of the UPDRS part III score at the final evaluation were imputed using a last observation carried forward (LOCF) method. All analyses were made using SAS version 9.3 (SAS institute, Cary, N.C., USA).
Results
Baseline Characteristics
The demographic and baseline characteristics of the patients included in this analysis are summarized in table 1. The phase 2 RCT enrolled 140 patients. Of 123 patients who completed the RCT, 108 patients were enrolled in the phase 2 OLE, 81 of whom completed the study. The phase 3 study enrolled 142 patients; the RCT and OLE were completed by 111 and 100 patients, respectively.
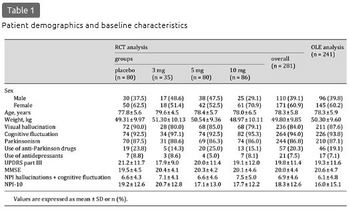
Of the patients included in the RCT analyses, females accounted for 60.9%. The mean age was 78.3 (range 57-95) years; all but 2 patients were 65 years or older. Anti-Parkinson drugs (levodopa or dopamine agonists) were used by 20.3% (57/281) with the mean ± standard deviation (SD) levodopa equivalent dose [33] of 262.0 ± 179.8 mg/day at baseline, and the dosages were not changed during the RCTs. No patients were on antipsychotics. The mean scores for the MMSE and UPDRS part III at baseline were 20.0 and 19.8 points, respectively. The characteristics in the OLE analysis were similar. During the OLEs, levodopa or dopamine agonists were started by 9.1% of patients (22/241), with the dose being increased in 6.6% (16/241) and decreased in 1.2% (3/241).
Analysis of RCTs
Incidence of Extrapyramidal AEs
The incidence of extrapyramidal AEs was 3.8% (3/80), 5.7% (2/35), 7.5% (6/80), and 5.8% (5/86) in the placebo, 3-, 5-, and 10-mg groups, respectively, and 6.5% (13/201) in the combined donepezil group, with no significant difference from the placebo group (p = 0.639, 0.495, 0.721, and 0.569 in the 3-, 5-, and 10-mg and combined donepezil group, respectively) (table 2). Most of the extrapyramidal AEs were reported as parkinsonism, the incidence of which was somewhat higher in the combined donepezil group [5.0% (10/201)] than in the placebo group [2.5% (2/80)], but the difference was not significant (p = 0.519). Severity was mild or moderate in all cases, and none were serious. Extrapyramidal AEs that led to discontinuation were reported in 3 patients as parkinsonism and were relieved after discontinuation: 2 patients in the 5-mg group (1 patient while receiving 3 mg) and 1 patient in the 10-mg group while receiving 3 mg.
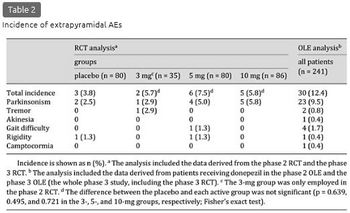
UPDRS Part III Score
The mean ± SD change in the UPDRS part III total score at week 12 (LOCF) was -0.2 ± 4.3, -0.5 ± 7.4, -1.2 ± 6.8, and -0.1 ± 5.9 in the placebo, 3-, 5-, and 10-mg groups, respectively, and -0.6 ± 6.5 in the combined donepezil group (table 3). The score was rather decreased in each treatment group from baseline, with no significant differences between the placebo and any active groups. Data at the final evaluation prior to week 12 from 30 patients were imputed using the LOCF method, but the results at week 12 of the observed case analysis were very similar to the results of the LOCF analysis (data not shown). Among the UPDRS part III subscales, the mean ± SD score decrease in rigidity was significantly larger in the 5-mg group (-0.8 ± 2.2) than in the placebo group (-0.2 ± 2.0, p = 0.030), although significant differences were not found in the 3- and 10-mg groups for either this or other items (table 4).
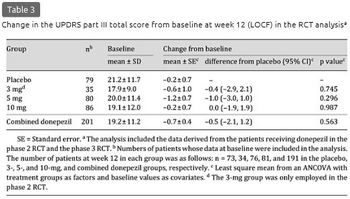

Analysis of Long-Term Administration
Incidence of Extrapyramidal AEs
Extrapyramidal AEs were reported by 12.4% (30/241) of patients (table 2). The incidence did not change over time for 52 weeks; the incidence in weeks 0-12, >12-24, >24-36, and >36-52 was 4.4% (9/204), 2.3% (4/173), 3.1% (5/161), and 6.4% (10/157), respectively (note that the placebo group during the phase 3 RCT was excluded from this calculation due to a difference in the administration period).
One severe AE was reported by 1 patient as parkinsonism, and all other AEs were mild or moderate in severity. No serious AEs were reported. AEs that led to discontinuation were reported in 4 patients as parkinsonism. AEs that led to a dose reduction were reported in 4 patients: 3 as parkinsonism and 1 as akinesia. All of these AEs recovered or were relieved after dose reduction or discontinuation, except for the single case of parkinsonism which led to discontinuation after dose reduction in the phase 2 OLE. Most of the extrapyramidal AEs that led to neither discontinuation nor dose reduction of the study drug were treated by start or dose increment of anti-Parkinson drugs [72.7% (16/22)].
UPDRS Part III Score
The mean ± SD change in the UPDRS part III total score from baseline was -0.7 ± 6.5, -0.2 ± 8.6, and 0.1 ± 8.4 at weeks 24, 52, and 52 (LOCF, n = 197, 179, and 227), respectively. The absolute magnitude of the mean change was small, ranging from -0.7 to 0.1, with no significant difference from baseline at any of the evaluation points (p = 0.145, 0.768, and 0.794, respectively).
Exploration for Potential Factors Affecting Extrapyramidal Symptoms
RCT Analysis
The incidence of extrapyramidal AEs did not differ according to the potential endogenous factors (table 5). Calculated by symptom-related factors, the incidence tended to be higher in the subgroups of the 5- and 10-mg groups with a UPDRS part III score above or equal to the median, a Hoehn and Yahr stage of 3, and use of anti-Parkinson drugs, relative to the incidence in the same subgroups of the placebo group and their respective counterparts in the 5- and 10-mg groups, even with an overall small incidence. The results of the univariate logistic regression analysis are shown in table 6. No significant interactions were detected between the treatment group and the symptom-related factors (UPDRS part III score, Hoehn and Yahr stage of 3, and use of anti-Parkinson drugs: p = 0.920, 0.949, and 0.354, respectively). The UPDRS part III score [odds ratio (OR): 1.087, p < 0.001], Hoehn and Yahr stage of 3 (OR: 5.228, p = 0.005), and use of anti-Parkinson drugs (OR: 4.612, p = 0.003) were the significant factors contributing to the extrapyramidal AEs. In the multivariate logistic regression analysis, the UPDRS part III score was the significant factor (OR: 1.071, p = 0.005) (table 7). In the model including the Hoehn and Yahr stage instead of the UPDRS part III score, a Hoehn and Yahr stage of 3 was significant (OR: 4.857, p = 0.014). In the subgroups of the active drug groups with use of anti-Parkinson drugs, the mean levodopa equivalent doses were comparable between patients with and without extrapyramidal AEs (228.6 and 262.9 mg, respectively; p = 0.679).

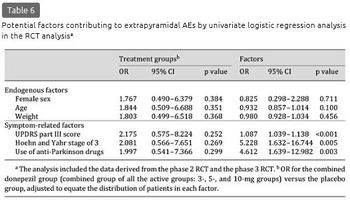
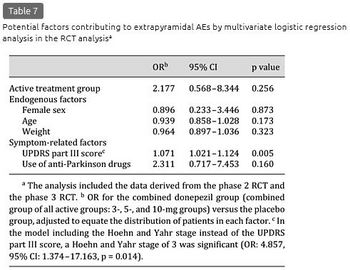
Long-Term Studies
The incidence of the extrapyramidal AEs did not differ greatly by the endogenous factors (table 5). Among the symptom-related factors, the incidence tended to be higher in the subgroups with a UPDRS part III score above or equal to the median, a Hoehn and Yahr stage of 3, and use of anti-Parkinson drugs. In the univariate logistic regression analysis, the UPDRS part III score [OR: 1.052, 95% confidence interval (CI): 1.019-1.087, p = 0.002], a Hoehn and Yahr stage of 3 (OR: 5.126, 95% CI: 2.228-11.794, p < 0.001), use of anti-Parkinson drugs (OR: 4.125, 95% CI: 1.831-9.293, p < 0.001), and age (OR: 0.931, 95% CI: 0.872-0.993, p = 0.030) were the significant factors. In the multivariate logistic regression analysis, the UPDRS part III score (OR: 1.043, 95% CI: 1.007-1.080, p = 0.020) and use of anti-Parkinson drugs (OR: 2.581, 95% CI: 1.058-6.298, p = 0.037) were the significant factors. In the model including the Hoehn and Yahr stage instead of the UPDRS part III score, a Hoehn and Yahr stage of 3 (OR: 5.561, 95% CI: 2.179-14.192, p < 0.001) and age (OR: 0.904, 95% CI: 0.834-0.980, p = 0.014) were significant. In the subgroups with use of anti-Parkinson drugs, the mean levodopa equivalent doses were comparable between patients with and without extrapyramidal AEs (265.4 and 271.5 mg, respectively; p = 0.925).
Discussion
This study explored the presence of any possible influence of DLB treatment with donepezil on extrapyramidal symptoms using two pooled datasets. In the RCT analysis, the difference in the incidence of extrapyramidal AEs between the active and placebo groups was minimal, and there was no tendency for a dose-dependent increase in the incidence. In the OLE analysis, none of the extrapyramidal AEs were serious. AEs that led to discontinuation or dose reduction were reported only in 8 patients (3.3%), all of which except for one case of parkinsonism recovered or were relieved after discontinuation or dose reduction. Moreover, the possibility of delayed onset or worsening of extrapyramidal AEs with long-term treatment appears low. In contrast to the concern based on the classical dopaminergic-cholinergic imbalance theory about worsening of extrapyramidal symptoms by cholinergic enhancement, these results suggest that patients with DLB can benefit from donepezil, which has a well-established efficacy on cognitive and psychiatric functions [12,13,14,15], with a minimal risk for extrapyramidal symptoms. The absence of an influence of ChEIs, including donepezil, on parkinsonism has been reported in previous studies, along with improvement in a few of these studies, which reinforces the interpretations drawn from this analysis [7,10,11,22,34]. Our finding is also in accordance with accumulating evidence of cholinergic involvement in PD; degeneration of multiple cholinergic projection systems occurs early in PD [35], cholinergic degeneration plays a role in some aspects of motor symptoms including postural control [36] and gait [37], and treatment with donepezil produces reductions in the number of falls in frequently falling patients with PD [38].
In contrast to our study, a worsening of parkinsonism after ChEI administration has been reported in some studies [18,19,20,21]. Moreover, compared with AD, extrapyramidal symptoms are considered to occur more frequently in patients with DLB. In a 24-week RCT and a 52-week OLE of donepezil in patients with severe AD in Japan, parkinsonism was reported with less than a 5.0% incidence [39,40]. The incidence in the present study is seemingly higher, although the events cannot necessarily be attributed to donepezil but to disease progression.
In the present study, baseline severity of parkinsonism (i.e. the UPDRS part III score, a Hoehn and Yahr stage of 3, and use of anti-Parkinson drugs) was identified as a predisposing factor for worsening of parkinsonism. Donepezil was not a contributing factor. There was no significant interaction between donepezil and baseline severity. These results suggest that extrapyramidal AEs can mostly be attributed to progression in the relatively severe stage.
Studies of ChEIs for patients with PDD, which is in the same spectrum of Lewy body disease as DLB, reported a slightly higher incidence of extrapyramidal AEs in the active than in the placebo group (tremor: 3.9 and 10.2% in the placebo and rivastigmine groups, respectively [41]; PD: 6.9, 10.8, and 10.4%, and tremor: 2.9, 7.2, and 7.1% in the placebo and donepezil 5- and 10-mg groups, respectively [42]), although both studies concluded that the active treatment was well tolerated. These studies may enable us to delineate the similar safety profile of ChEIs in patients with DLB manifesting relatively severe extrapyramidal symptoms and in those with PDD.
In any case, careful attention is certainly required in treating DLB with donepezil. Particular attention should be placed on patients who manifest extrapyramidal symptoms that restrict their daily living activities and who require pharmacological treatment. Nevertheless, even after the occurrence or worsening of these symptoms, dose reduction or discontinuation, or addition of anti-Parkinson drugs may prevent further worsening and lead to recovery or relief.
An interpretation of this analysis may require consideration of several points. First, the present analysis may not encompass all of the possible factors that may affect the symptoms in treatment with donepezil. Second, the analysis is based on the data obtained under a clinical trial setting where the strict inclusion and exclusion criteria employed may have curtailed the variety of patient characteristics which may be encountered in a real-life setting. Third, patients with very severe parkinsonism of a Hoehn and Yahr stage ≥4 were not included, and thus the present findings cannot be extrapolated to those patients. Finally, the recording of extrapyramidal AEs and UPDRS part III scoring might be confounded due to interrater variability in the assessments in multicenter studies where both neurologists and psychiatrists participated, although a rater training and elaborate monitoring were conducted to reduce the concern. Future studies which overcome all of these possible limitations may be warranted.
In conclusion, donepezil can treat DLB effectively and safely without relevant worsening of extrapyramidal symptoms. However, its administration to patients whose daily living activities are restricted and for whom pharmacotherapy is required due to parkinsonism necessitates care regarding symptom progression. In case of the occurrence or progression of symptoms, a dose reduction or discontinuation, or addition of anti-Parkinson drugs is considered as an effective approach.
Acknowledgments
We thank all patients and caregivers for their participation in the study; all investigators and their site staff for their contributions; Clinical Study Support, Inc., for their editorial assistance in preparing this manuscript, and the Eisai study team for their assistance. The studies and analyses were sponsored by Eisai Co., Ltd. (Tokyo, Japan). The sponsor was involved in the study designing, the collection and analysis of data, and review of the manuscript.
Disclosure Statement
E.M. received personal fees from Eisai during the conduct of the studies; grants and personal fees from Eisai, Daiichi Sankyo, and FUJIFILM RI, and personal fees from Janssen, Johnson and Johnson, Lundbeck, Novartis, Ono Pharmaceutical, Nihon Medi-Physics, and Medtronic outside the submitted work. All grants were for his department, and he received them as the director of the department. M.I. received personal fees from Eisai during the conduct of the studies; grants and personal fees from Daiichi Sankyo, Eisai, FUJIFILM RI, Janssen, Nihon Medi-Physics, Novartis, Pfizer, Takeda, and Tsumura, and personal fees from MSD and Ono Pharmaceutical outside the submitted work. All grants were for his department, and he received them as the director of the department. M.N., H.M., and H.Y. are employees of Eisai. K.K. received personal fees from Eisai during the conduct of the studies and personal fees from Tsumura, Eisai, Janssen, FUJIFILM RI, Novartis, Nihon Medi-Physics, Daiichi Sankyo, Ono Pharmaceutical, Otsuka, and Dainippon Sumitomo outside the submitted work.
References
(省略)
Abstract
Background/Aims: The aim of this study was to clarify the effects of donepezil on extrapyramidal symptoms in patients with dementia with Lewy bodies (DLB). Methods: Using pooled datasets from phase 2 and 3, 12-week randomized, placebo-controlled trials (RCT, n = 281) and 52-week open-label long-term extension trials (OLE, n = 241) of donepezil in DLB, the effects of donepezil on the incidence of extrapyramidal adverse events (AEs) and on the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) part III were assessed, and potential baseline factors affecting the AEs were explored. Results: The RCT analysis did not show significant differences between the placebo and active (3, 5, and 10 mg donepezil) groups in extrapyramidal AE incidence (3.8 and 6.5%, p = 0.569) and change in the UPDRS (mean ± SD: -0.2 ± 4.3 and -0.6 ± 6.5, p = 0.562). In the OLE analysis (5 and 10 mg donepezil), the incidence did not increase chronologically; all AEs leading to a dose reduction or discontinuation except one were relieved. The UPDRS was unchanged for 52 weeks. An exploratory multivariate logistic regression analysis of the RCTs revealed that donepezil treatment was not a significant factor affecting the AEs. Baseline severity of parkinsonism was a predisposing factor for worsening of parkinsonism without significant interactions between donepezil and baseline severity. Conclusion: DLB can safely be treated with donepezil without relevant worsening of extrapyramidal symptoms, but treatment requires careful attention to symptom progression when administered to patients with relatively severe parkinsonism.
Introduction
Dementia with Lewy bodies (DLB) is the second most common form of senile dementia following Alzheimer's disease (AD) [1]. The core clinical features of DLB include neuropsychiatric symptoms and parkinsonism as well as cognitive impairment characterized by deficits in attention, executive function, and visual perception [2]. The cholinergic loss and a choline acetyltransferase activity deficit with preserved postsynaptic cortical muscarinic and nicotinic receptors [3,4,5] rationalizes the use of cholinesterase inhibitors (ChEIs) in DLB. The favorable potential of ChEls such as galantamine, rivastigmine, and donepezil has been demonstrated in previous studies [6,7,8,9,10,11]. The phase 2 and 3 trials of donepezil in patients with DLB have added to the accumulating evidence of the efficacy and safety of donepezil in terms of cognitive, behavioral, and global function in DLB, even for long durations, without increasing the risk of clinically significant safety events [12,13,14,15].
It has been reported that 25-50% of patients with DLB have parkinsonism at the time of diagnosis and that 75-80% of such patients eventually develop it [16], although the exact proportion is still controversial. In a natural course, the symptoms could worsen with a speed comparable to Parkinson's disease (PD) [17]. The cholinergic interneurons synapse on the GABAergic striatal neurons that project to the globus pallidus. The cholinergic actions inhibit striatal cells of the direct pathway and excite striatal cells of the indirect pathway. Thus, ChEIs augment cholinergic function, which may oppose the effects of dopamine on the direct and indirect pathways exacerbating parkinsonism in DLB, in which nigrostriatal dopaminergic neurons have been lost [18,19,20,21]. On purely theoretical grounds, ChEI administration targeting cognitive impairment and behavioral symptoms may exacerbate parkinsonism. Despite studies showing that ChEIs did not affect parkinsonism and which did not replicate the possible untoward effects in patients with DLB or PD dementia (PDD) [22,23], concerns over a possible influence on the extrapyramidal symptoms still linger due to a shortage of evidence from large-scale, placebo-controlled, or long-term studies especially in DLB and require further confirmation.
As in diseases like DLB treatment for one symptom may precipitate others [24] and the combination or severity of the associated multiple, multi-dimensional symptoms varies by patient, a large-scale comprehensive study is essential. Our trials of donepezil in patients with DLB consist of two randomized, double-blind, placebo-controlled trials (RCT) and two open-label long-term extension studies (OLE) and enrolled a large group of patients that may embody patients with diverse demographic characteristics and clinical symptom manifestations, which the current diagnosis of probable DLB may encompass. We therefore developed two types of comprehensive pooled datasets from two RCTs and two OLEs of donepezil for DLB. RCTs provide information with minimized bias, while OLEs involve more patient-years of exposure to donepezil and may thus disclose adverse effects which are not observed in the parent RCTs. Using these datasets of the largest scale ever in DLB, we analyzed the effect of donepezil on the occurrence and worsening of extrapyramidal symptoms in patients with DLB.
Methods
Design of the Phase 2 and 3 Studies
This analysis pooled the data from the phase 2 and 3 studies of donepezil for DLB conducted in Japan. The phase 2 studies, consisting of a RCT (clinicaltrials.gov reference: NCT00543855) and a subsequent OLE (clinicaltrials.gov reference: NCT00598650), were conducted as two sequential protocols. A 12-week randomized, double-blind, placebo-controlled exploratory study (phase 2 RCT) was first conducted to investigate the efficacy and safety of donepezil at 3, 5, and 10 mg/day starting in 2007 (fig. 1a) [12]. In the patients who completed this RCT, the safety and efficacy of long-term administration at 5 mg were further investigated in the following 52-week OLE (phase 2 OLE) (fig. 1b) [13]. The phase 3 study (clinicaltrials.gov reference: NCT01278407) was conducted as a single protocol consisting of an RCT phase and a subsequent OLE phase. A 16-week randomized, double-blind, placebo-controlled comparative study consisting of a 12-week confirmatory phase (phase 3 RCT) (fig. 1a) [14] and a 4-week transition period and a subsequent 36-week OLE phase were conducted starting in 2011 for a total duration of 52 weeks (phase 3 OLE) (fig. 1b) [15]. The aim was to confirm the superiority of donepezil at 5 and 10 mg/day for 12 weeks over placebo with regard to both cognitive function and behavioral symptoms and to evaluate the safety and efficacy of long-term administration of 10 mg/day for 52 weeks. Each study was conducted in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki. The protocols were approved by the institutional review board at each participating center.
Patients
The inclusion and exclusion criteria were the same in both RCTs. The inclusion criteria were patients aged ≥50 years with probable DLB fulfilling the consensus diagnostic criteria [2], with mild to moderate-severe dementia [10-26 points on the Mini-Mental State Examination (MMSE) and Clinical Dementia Rating ≥0.5], behavioral symptoms or cognitive fluctuation [Neuropsychiatric Inventory (NPI)-plus ≥8 (rated on 12 items: original 10 NPI items + sleep [25,26] + Cognitive Fluctuation Inventory [27,28])], and with caregivers who could routinely stay with the patients, provide information for this study, assist with treatment compliance, and escort them to required visits.
The exclusion criteria included PD that was diagnosed at least 1 year prior to the onset of dementia; focal vascular lesions on an MRI or CT that might cause cognitive impairment; other neurological or psychiatric diseases; complications or a history of severe gastrointestinal ulcers, severe asthma, or obstructive pulmonary disease; systolic hypotension (<90 mm Hg); bradycardia (<50 bpm); sick sinus syndrome; atrial or atrioventricular conduction block; QT interval prolongation (≥450 ms); severe parkinsonism (Hoehn and Yahr stage ≥4) [29], and treatment with ChEIs or any investigational drug within 3 months prior to screening. ChEIs, antipsychotics, and anti-Parkinson drugs were not allowed during the study, except for levodopa and dopamine agonists, of which only stable doses were allowed during the RCTs.
Written informed consent was obtained from the patient (if at all possible) and his/her primary family member before initiating the study procedures.
Donepezil Administration
In the phase 2 RCT, the patients were randomized to placebo, 3, 5, or 10 mg/day of donepezil (placebo, 3-, 5-, and 10-mg groups) (fig. 1a). In the subsequent phase 2 OLE, all patients received donepezil at 5 mg/day (fig. 1b). Donepezil administration in the 5- and 10-mg groups started with a 2-week titration period with a 3-mg dose, which was applied in all of the studies.
In the phase 3 RCT, the patients were randomized to placebo, 5, or 10 mg/day (placebo, 5-, or 10-mg group) (fig. 1a). Since the phase 3 study incorporated the RCT and OLE phases, the duration of donepezil administration in the phase 3 OLE differed by treatment group: 52 weeks for the 5- and 10-mg groups (10 mg administration from week 24 and 6, respectively) with a 12-week overlap with the phase 3 RCT, and 36 weeks for the placebo group (3 mg titration from week 16, 5 mg administration from week 18, and 10 mg from week 24) (fig. 1b).
In the OLEs, a dose reduction to 3 mg in the phase 2 OLE or to 5 mg after week 24 in the phase 3 OLE was allowed upon emergence of a safety concern.
Summary of the Results of the Phase 2 and 3 Studies
The results of the phase 2 and 3 studies are reported in detail elsewhere [12,13,14,15]. Briefly, in phase 2, the RCT showed that donepezil significantly improved cognitive, behavioral, and global functions with good tolerability, and the OLE demonstrated that administration was well tolerated even for a long duration and that the effect on cognitive and behavioral impairment was maintained for up to 52 weeks. In phase 3, although the RCT failed to confirm a superiority concerning the behavioral symptoms over placebo, it confirmed the efficacy concerning cognitive function (one of the co-primary endpoints) without serious safety concerns. The OLE demonstrated a lasting improvement in cognitive function for up to 52 weeks, without increasing the risk of clinically significant safety events.
Datasets
The safety data regarding extrapyramidal symptoms derived from these studies were pooled in two ways: RCT and OLE (fig. 1). The datasets of the two RCTs were pooled and analyzed according to allocated treatment during the 12-week period: placebo, 3-, 5-, or 10-mg groups (n = 281) (fig. 1a). The dataset derived from all patients receiving donepezil via long-term administration [i.e. phase 2 OLE and phase 3 OLE (whole period of phase 3: RCT + OLE)] was pooled and analyzed (n = 241) (fig. 1b).
Assessment of Extrapyramidal Symptoms
The influence on extrapyramidal symptoms was evaluated according to the incidence of extrapyramidal adverse events (AEs) and the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) part III [30]. To reduce interrater and intrarater variability, an advanced rater training was conducted, a fixed rater was involved in the assessment of each patient in principle, and an elaborate monitoring was made throughout the study period. Of all the AEs which occurred during the studies (coded according to the Preferred Terms of the Medical Dictionary for Regulatory Activities), the following were identified as extrapyramidal AEs after discussion by the central committee: parkinsonism, rigidity, tremor, camptocormia, gait difficulty, and akinesia. The UPDRS part III was conducted every 12 weeks in the phase 2 RCT and in phase 3, and every 24 weeks in the phase 2 OLE.
Statistical Analysis
This secondary analysis was based on the safety analysis set of each study, which comprised all patients who received at least one dose of donepezil and had safety assessment data. For the analysis of the RCTs, the incidence of extrapyramidal AEs was summarized by treatment group and compared between the placebo and each active group using Fisher's exact test. The change in the UPDRS part III total and subscale score from baseline was compared between the placebo and each treatment group using analysis of covariance (ANCOVA) with the baseline values as covariates. Subscales were predefined as the following four symptoms: tremor, akinesia, rigidity, and postural instability and gait difficulty, with score ranges of 0-28, 0-36, 0-20, and 0-16, respectively [31,32]. For the analysis of OLEs, the incidence of extrapyramidal AEs was calculated. The UPDRS part III scores were analyzed using Student's paired t test.
To identify any potential baseline factors that may contribute to the extrapyramidal AEs, the incidence was calculated for subgroups stratified by the potential factors, and univariate and multivariate logistic regression analyses were subsequently conducted. Potential factors included endogenous factors (sex, age, and body weight) and symptom-related factors [UPDRS part III score, Hoehn and Yahr stage (≤2 or 3), and use of anti-Parkinson drugs (use or nonuse)]. In multivariate analyses, either the UPDRS part III score or the Hoehn and Yahr stage was included in the model because of the high correlation between them. In the analysis of the RCTs, the interaction between the treatment groups and factors was tested for each symptom-related factor using a logistic regression analysis. Each interaction was to be included in the model when significance was detected.
Values of the UPDRS part III score at the final evaluation were imputed using a last observation carried forward (LOCF) method. All analyses were made using SAS version 9.3 (SAS institute, Cary, N.C., USA).
Results
Baseline Characteristics
The demographic and baseline characteristics of the patients included in this analysis are summarized in table 1. The phase 2 RCT enrolled 140 patients. Of 123 patients who completed the RCT, 108 patients were enrolled in the phase 2 OLE, 81 of whom completed the study. The phase 3 study enrolled 142 patients; the RCT and OLE were completed by 111 and 100 patients, respectively.
Of the patients included in the RCT analyses, females accounted for 60.9%. The mean age was 78.3 (range 57-95) years; all but 2 patients were 65 years or older. Anti-Parkinson drugs (levodopa or dopamine agonists) were used by 20.3% (57/281) with the mean ± standard deviation (SD) levodopa equivalent dose [33] of 262.0 ± 179.8 mg/day at baseline, and the dosages were not changed during the RCTs. No patients were on antipsychotics. The mean scores for the MMSE and UPDRS part III at baseline were 20.0 and 19.8 points, respectively. The characteristics in the OLE analysis were similar. During the OLEs, levodopa or dopamine agonists were started by 9.1% of patients (22/241), with the dose being increased in 6.6% (16/241) and decreased in 1.2% (3/241).
Analysis of RCTs
Incidence of Extrapyramidal AEs
The incidence of extrapyramidal AEs was 3.8% (3/80), 5.7% (2/35), 7.5% (6/80), and 5.8% (5/86) in the placebo, 3-, 5-, and 10-mg groups, respectively, and 6.5% (13/201) in the combined donepezil group, with no significant difference from the placebo group (p = 0.639, 0.495, 0.721, and 0.569 in the 3-, 5-, and 10-mg and combined donepezil group, respectively) (table 2). Most of the extrapyramidal AEs were reported as parkinsonism, the incidence of which was somewhat higher in the combined donepezil group [5.0% (10/201)] than in the placebo group [2.5% (2/80)], but the difference was not significant (p = 0.519). Severity was mild or moderate in all cases, and none were serious. Extrapyramidal AEs that led to discontinuation were reported in 3 patients as parkinsonism and were relieved after discontinuation: 2 patients in the 5-mg group (1 patient while receiving 3 mg) and 1 patient in the 10-mg group while receiving 3 mg.
UPDRS Part III Score
The mean ± SD change in the UPDRS part III total score at week 12 (LOCF) was -0.2 ± 4.3, -0.5 ± 7.4, -1.2 ± 6.8, and -0.1 ± 5.9 in the placebo, 3-, 5-, and 10-mg groups, respectively, and -0.6 ± 6.5 in the combined donepezil group (table 3). The score was rather decreased in each treatment group from baseline, with no significant differences between the placebo and any active groups. Data at the final evaluation prior to week 12 from 30 patients were imputed using the LOCF method, but the results at week 12 of the observed case analysis were very similar to the results of the LOCF analysis (data not shown). Among the UPDRS part III subscales, the mean ± SD score decrease in rigidity was significantly larger in the 5-mg group (-0.8 ± 2.2) than in the placebo group (-0.2 ± 2.0, p = 0.030), although significant differences were not found in the 3- and 10-mg groups for either this or other items (table 4).
Analysis of Long-Term Administration
Incidence of Extrapyramidal AEs
Extrapyramidal AEs were reported by 12.4% (30/241) of patients (table 2). The incidence did not change over time for 52 weeks; the incidence in weeks 0-12, >12-24, >24-36, and >36-52 was 4.4% (9/204), 2.3% (4/173), 3.1% (5/161), and 6.4% (10/157), respectively (note that the placebo group during the phase 3 RCT was excluded from this calculation due to a difference in the administration period).
One severe AE was reported by 1 patient as parkinsonism, and all other AEs were mild or moderate in severity. No serious AEs were reported. AEs that led to discontinuation were reported in 4 patients as parkinsonism. AEs that led to a dose reduction were reported in 4 patients: 3 as parkinsonism and 1 as akinesia. All of these AEs recovered or were relieved after dose reduction or discontinuation, except for the single case of parkinsonism which led to discontinuation after dose reduction in the phase 2 OLE. Most of the extrapyramidal AEs that led to neither discontinuation nor dose reduction of the study drug were treated by start or dose increment of anti-Parkinson drugs [72.7% (16/22)].
UPDRS Part III Score
The mean ± SD change in the UPDRS part III total score from baseline was -0.7 ± 6.5, -0.2 ± 8.6, and 0.1 ± 8.4 at weeks 24, 52, and 52 (LOCF, n = 197, 179, and 227), respectively. The absolute magnitude of the mean change was small, ranging from -0.7 to 0.1, with no significant difference from baseline at any of the evaluation points (p = 0.145, 0.768, and 0.794, respectively).
Exploration for Potential Factors Affecting Extrapyramidal Symptoms
RCT Analysis
The incidence of extrapyramidal AEs did not differ according to the potential endogenous factors (table 5). Calculated by symptom-related factors, the incidence tended to be higher in the subgroups of the 5- and 10-mg groups with a UPDRS part III score above or equal to the median, a Hoehn and Yahr stage of 3, and use of anti-Parkinson drugs, relative to the incidence in the same subgroups of the placebo group and their respective counterparts in the 5- and 10-mg groups, even with an overall small incidence. The results of the univariate logistic regression analysis are shown in table 6. No significant interactions were detected between the treatment group and the symptom-related factors (UPDRS part III score, Hoehn and Yahr stage of 3, and use of anti-Parkinson drugs: p = 0.920, 0.949, and 0.354, respectively). The UPDRS part III score [odds ratio (OR): 1.087, p < 0.001], Hoehn and Yahr stage of 3 (OR: 5.228, p = 0.005), and use of anti-Parkinson drugs (OR: 4.612, p = 0.003) were the significant factors contributing to the extrapyramidal AEs. In the multivariate logistic regression analysis, the UPDRS part III score was the significant factor (OR: 1.071, p = 0.005) (table 7). In the model including the Hoehn and Yahr stage instead of the UPDRS part III score, a Hoehn and Yahr stage of 3 was significant (OR: 4.857, p = 0.014). In the subgroups of the active drug groups with use of anti-Parkinson drugs, the mean levodopa equivalent doses were comparable between patients with and without extrapyramidal AEs (228.6 and 262.9 mg, respectively; p = 0.679).
Long-Term Studies
The incidence of the extrapyramidal AEs did not differ greatly by the endogenous factors (table 5). Among the symptom-related factors, the incidence tended to be higher in the subgroups with a UPDRS part III score above or equal to the median, a Hoehn and Yahr stage of 3, and use of anti-Parkinson drugs. In the univariate logistic regression analysis, the UPDRS part III score [OR: 1.052, 95% confidence interval (CI): 1.019-1.087, p = 0.002], a Hoehn and Yahr stage of 3 (OR: 5.126, 95% CI: 2.228-11.794, p < 0.001), use of anti-Parkinson drugs (OR: 4.125, 95% CI: 1.831-9.293, p < 0.001), and age (OR: 0.931, 95% CI: 0.872-0.993, p = 0.030) were the significant factors. In the multivariate logistic regression analysis, the UPDRS part III score (OR: 1.043, 95% CI: 1.007-1.080, p = 0.020) and use of anti-Parkinson drugs (OR: 2.581, 95% CI: 1.058-6.298, p = 0.037) were the significant factors. In the model including the Hoehn and Yahr stage instead of the UPDRS part III score, a Hoehn and Yahr stage of 3 (OR: 5.561, 95% CI: 2.179-14.192, p < 0.001) and age (OR: 0.904, 95% CI: 0.834-0.980, p = 0.014) were significant. In the subgroups with use of anti-Parkinson drugs, the mean levodopa equivalent doses were comparable between patients with and without extrapyramidal AEs (265.4 and 271.5 mg, respectively; p = 0.925).
Discussion
This study explored the presence of any possible influence of DLB treatment with donepezil on extrapyramidal symptoms using two pooled datasets. In the RCT analysis, the difference in the incidence of extrapyramidal AEs between the active and placebo groups was minimal, and there was no tendency for a dose-dependent increase in the incidence. In the OLE analysis, none of the extrapyramidal AEs were serious. AEs that led to discontinuation or dose reduction were reported only in 8 patients (3.3%), all of which except for one case of parkinsonism recovered or were relieved after discontinuation or dose reduction. Moreover, the possibility of delayed onset or worsening of extrapyramidal AEs with long-term treatment appears low. In contrast to the concern based on the classical dopaminergic-cholinergic imbalance theory about worsening of extrapyramidal symptoms by cholinergic enhancement, these results suggest that patients with DLB can benefit from donepezil, which has a well-established efficacy on cognitive and psychiatric functions [12,13,14,15], with a minimal risk for extrapyramidal symptoms. The absence of an influence of ChEIs, including donepezil, on parkinsonism has been reported in previous studies, along with improvement in a few of these studies, which reinforces the interpretations drawn from this analysis [7,10,11,22,34]. Our finding is also in accordance with accumulating evidence of cholinergic involvement in PD; degeneration of multiple cholinergic projection systems occurs early in PD [35], cholinergic degeneration plays a role in some aspects of motor symptoms including postural control [36] and gait [37], and treatment with donepezil produces reductions in the number of falls in frequently falling patients with PD [38].
In contrast to our study, a worsening of parkinsonism after ChEI administration has been reported in some studies [18,19,20,21]. Moreover, compared with AD, extrapyramidal symptoms are considered to occur more frequently in patients with DLB. In a 24-week RCT and a 52-week OLE of donepezil in patients with severe AD in Japan, parkinsonism was reported with less than a 5.0% incidence [39,40]. The incidence in the present study is seemingly higher, although the events cannot necessarily be attributed to donepezil but to disease progression.
In the present study, baseline severity of parkinsonism (i.e. the UPDRS part III score, a Hoehn and Yahr stage of 3, and use of anti-Parkinson drugs) was identified as a predisposing factor for worsening of parkinsonism. Donepezil was not a contributing factor. There was no significant interaction between donepezil and baseline severity. These results suggest that extrapyramidal AEs can mostly be attributed to progression in the relatively severe stage.
Studies of ChEIs for patients with PDD, which is in the same spectrum of Lewy body disease as DLB, reported a slightly higher incidence of extrapyramidal AEs in the active than in the placebo group (tremor: 3.9 and 10.2% in the placebo and rivastigmine groups, respectively [41]; PD: 6.9, 10.8, and 10.4%, and tremor: 2.9, 7.2, and 7.1% in the placebo and donepezil 5- and 10-mg groups, respectively [42]), although both studies concluded that the active treatment was well tolerated. These studies may enable us to delineate the similar safety profile of ChEIs in patients with DLB manifesting relatively severe extrapyramidal symptoms and in those with PDD.
In any case, careful attention is certainly required in treating DLB with donepezil. Particular attention should be placed on patients who manifest extrapyramidal symptoms that restrict their daily living activities and who require pharmacological treatment. Nevertheless, even after the occurrence or worsening of these symptoms, dose reduction or discontinuation, or addition of anti-Parkinson drugs may prevent further worsening and lead to recovery or relief.
An interpretation of this analysis may require consideration of several points. First, the present analysis may not encompass all of the possible factors that may affect the symptoms in treatment with donepezil. Second, the analysis is based on the data obtained under a clinical trial setting where the strict inclusion and exclusion criteria employed may have curtailed the variety of patient characteristics which may be encountered in a real-life setting. Third, patients with very severe parkinsonism of a Hoehn and Yahr stage ≥4 were not included, and thus the present findings cannot be extrapolated to those patients. Finally, the recording of extrapyramidal AEs and UPDRS part III scoring might be confounded due to interrater variability in the assessments in multicenter studies where both neurologists and psychiatrists participated, although a rater training and elaborate monitoring were conducted to reduce the concern. Future studies which overcome all of these possible limitations may be warranted.
In conclusion, donepezil can treat DLB effectively and safely without relevant worsening of extrapyramidal symptoms. However, its administration to patients whose daily living activities are restricted and for whom pharmacotherapy is required due to parkinsonism necessitates care regarding symptom progression. In case of the occurrence or progression of symptoms, a dose reduction or discontinuation, or addition of anti-Parkinson drugs is considered as an effective approach.
Acknowledgments
We thank all patients and caregivers for their participation in the study; all investigators and their site staff for their contributions; Clinical Study Support, Inc., for their editorial assistance in preparing this manuscript, and the Eisai study team for their assistance. The studies and analyses were sponsored by Eisai Co., Ltd. (Tokyo, Japan). The sponsor was involved in the study designing, the collection and analysis of data, and review of the manuscript.
Disclosure Statement
E.M. received personal fees from Eisai during the conduct of the studies; grants and personal fees from Eisai, Daiichi Sankyo, and FUJIFILM RI, and personal fees from Janssen, Johnson and Johnson, Lundbeck, Novartis, Ono Pharmaceutical, Nihon Medi-Physics, and Medtronic outside the submitted work. All grants were for his department, and he received them as the director of the department. M.I. received personal fees from Eisai during the conduct of the studies; grants and personal fees from Daiichi Sankyo, Eisai, FUJIFILM RI, Janssen, Nihon Medi-Physics, Novartis, Pfizer, Takeda, and Tsumura, and personal fees from MSD and Ono Pharmaceutical outside the submitted work. All grants were for his department, and he received them as the director of the department. M.N., H.M., and H.Y. are employees of Eisai. K.K. received personal fees from Eisai during the conduct of the studies and personal fees from Tsumura, Eisai, Janssen, FUJIFILM RI, Novartis, Nihon Medi-Physics, Daiichi Sankyo, Ono Pharmaceutical, Otsuka, and Dainippon Sumitomo outside the submitted work.
References
(省略)
食事を食べない患者さん [拒食]
食べない原因によっては薬剤が有効なこともある

「毒が盛られている」という発言から,食べない原因は妄想の可能性が考えられました.内服への拒否が強かったためハロペリドール(セレネース![[レジスタードトレードマーク]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/219.gif) )5mg/回の筋注を連日開始したところ,奏効し食事摂取が可能となりました.クエチアピン(セロクエル
)5mg/回の筋注を連日開始したところ,奏効し食事摂取が可能となりました.クエチアピン(セロクエル![[レジスタードトレードマーク]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/219.gif) )1回12.5mg,1日2回の内服に切り替えましたが妄想の再燃なく,食事はセッティングすれば自己摂取ができ,精神的にも穏やかな状態まで回復して自宅退院となりました.
)1回12.5mg,1日2回の内服に切り替えましたが妄想の再燃なく,食事はセッティングすれば自己摂取ができ,精神的にも穏やかな状態まで回復して自宅退院となりました.
【洪 英在、竹村洋典:食事を食べない患者さん. Gノート Vol.3 No.6(増刊) 959-964 2016】
私の感想:
拒食への対応は本当に悩みますね。
新聞で食欲が回復するケースなんてなかなか想像できないですよね。
アピタルで紹介した「拒食」関連の記述を一気にご紹介しますね。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第757回『摂食障害と模倣―正面に座って食べる』(2015年2月7日公開)
重度認知症患者さんの介護者の方から時折聞かれることに、「認知症が進行してから食べることを忘れるようになってきたのですがどうすればよいでしょうか?」といった質問があります。
食事を拒んでいるのではありません。食べようとしない状況です。
こんな時にまず最初に行われる方法は、意外と基本的なことですが言われないと案外気づかないことです。それは、患者さんの正面に座り、患者さんに見えるように食べるということです。目の前の人が食べている姿を見ると、模倣するかのように食べることを思い出してくれるのです。
「ミラーニューロンの発見『物まね細胞』が明かす驚きの脳科学」という本にとっても興味深い記述がありますのでご紹介しましょう。
「大人が赤ん坊の真似をすれば、赤ん坊は喜ぶ。もし私が友人宅での集まりに出かけていって、その家に赤ん坊がいたなら、私は真っ先にその赤ん坊のすることを真似してみせる。するといきなり、私はその子の一番の注目株になる(もちろん両親を除いて)。赤ん坊は模倣ごっこをするのが大好きなのだ。また、親と赤ん坊がしょっちゅうお互いに真似をしあうのは誰もが知るところだろう。実際、このときの模倣(と親和力)は発達中の脳にあるミラーニューロンを強化する主要形成因子の一つなのかもしれない。…(中略)…まだ話し方を知らない幼児どうしがいっしょに遊ぶときは、たいてい模倣ごっこをする。そして模倣ごっこを熱心にやる幼児ほど、一年から二年後に、言葉を多く使うようになるのだ。」(マルコ・イアコボーニ:ミラーニューロンの発見「物まね細胞」が明かす驚きの脳科学 塩原通緒訳, 早川書房発行, 東京, 2011, pp68-70)
ミラーニューロンの果たす興味深い役割については、また後日ご紹介する予定ですが、ミラーニューロンシステムを活用して認知症高齢者のコミュニケーション能力の向上を図ろうという試みもありますので若干その研究についてご紹介しておきましょう。
「Nonverbal Communication Rehabiltation(NCR)療法は、ミラーニューロンシステムの機能をリハによりさらに活性化すれば、認知症高齢者のコミュニケーション能力の向上、特に感情や好意等の心の内面を含めた意思疎通の向上を図ることができ、『心の通った』看護・介護の実現に役立てるために開発された。また、これにより、社会性が向上すれば、他のリハプログラムに対する積極性も増し、認知機能やADL・QOLの向上につながっていくことも期待されるものである。このなかで、介護において訓練しやすいプログラムとして組み立てられたものが、『にこにこリハ』である。」(長屋政博:認知症に対するリハビリテーション. 診断と治療 Vol.102 349-354 2014)
ただし、「模倣」は使い方を間違うと、精神の発達に悪影響を及ぼしうることも知られていますので注意して下さい。
マルコ・イアコボーニは、幼少期のメディア暴力の視聴が及ぼすその後の攻撃性・反社会的行動・犯罪性との関係について以下のように言及しています(一部改変)。
「1960年代にニューヨーク州にて、約1,000人の子どもを対象として実施された調査において、もともとの攻撃性や、教育や社会階級などの主要な変数を調整した上で、メディア暴力を幼少期に目にすることが約10年後にあたる高校卒業後の攻撃性や反社会的行動と相関関係にあることが実証された。この結果だけでも充分に注目に値するものだが、続きはまだある。同じ少年たちをさらに10年、つまり最初の調査から合計22年にわたって追跡調査したところ、結果はまたも明確だった。幼少期のメディア暴力の視聴と幼少期の攻撃行動は、30歳時の犯罪性と相関関係にあったのである!」(マルコ・イアコボーニ:ミラーニューロンの発見「物まね細胞」が明かす驚きの脳科学 塩原通緒訳, 早川書房発行, 東京, 2011, pp251-252)
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第758回『摂食障害と模倣―何を「食事」と認識するか』(2015年2月8日公開)
さて、摂食障害への対応に話を戻しましょう。
埼玉社会保険病院の福光由希子認知症看護認定看護師は、食事の最中に席を離れ、他人の食事に手を伸ばしてしまったCさん(70歳代、女性)の事例を紹介しています(福光由希子:状況別・やるべきこと、やってはいけないこと─食事. Nursing Today Vol.27 24-26 2012)。一部改変して以下にご紹介します。
Cさんは、高度の認知機能低下があり、攻撃的になる等の症状が出現し治療目的で入院しました。時々むせ込みがあるためペースト食に変更されました。すると、主食に果物を混ぜたり、途中で席を立ったり、他人の食事に手を伸ばしトラブルに発展してしまいました。
スタッフはCさんの様子を観察し、種々の工夫を検討していきます。
Cさんは自分で食事を口に運ぶ能力は残っていて、食欲もあり、介助を受ければ毎食ほぼ全量摂取できていました。そこでスタッフは、「白い器に白いご飯」だと認識ができず途中で残してしまうのではないかと考え、見分けがつきやすいように器の色を赤色に変更しました。
また、Cさんの様子を観察していると、おやつや家族が持ち込むものは普通の形態のものでもむせ込むことなく摂取できていました。スタッフは、ペースト食が「食事」と認識できず、いろいろな物を混ぜてしまったのではないかと考えました。そして、他人の食事に手を伸ばしてしまったのは、それがCさんにとって「食事」「自分が食べたいもの」と認識されたためだと考え、「食事形態の変更」を試みました。主治医や栄養士と相談し、少しずつ食事の形態をアップし数週間後には常食(副食は「刻み」)を摂取できるようになりました。
また、食事の途中で席を立ってしまったときのCさんの表情は眉間にシワが寄った険しい表情であり、何らかのストレスを感じていることが伺えました。自分の思いを他者に伝えることができまないCさんにとって食堂のざわついた雰囲気や耳から入ってくる音がストレスになり、食事に集中できる環境ではなかったのではないかと考え、スタッフが数名配置されている介助席から、一人で落ち着いて食べられる席に変更してみました。
これらの対応によりCさんは途中で席を立つことなく自力で全量摂取ができるようになりました。常食になってからは、お膳ごと提供しても食事を混ぜることもなくなり、発語が限られていたCさんから笑顔で「おいしい」という言葉も聞けるようになったそうです。
なお余談ですが、私は大学卒業後1年目後半から2年目前半の研修医時代を埼玉社会保険病院で過ごしました。私が勤務していたのは1983年(昭和58年)12月から1984年7月までの8か月間です。当時の名称は、「社会保険埼玉中央病院」でした。脳神経外科病棟は6階北病棟でした。救急当番日以外の日は、ほとんど毎晩のように飲屋街に出掛けていたことが懐かしく思い出されます。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第759回『摂食障害と模倣―食事に集中できる環境を』(2015年2月9日公開)
精神科医の小澤勲さん(故人)は著書の中で、クリスティーンさん(メモ1参照)が語った言葉を紹介し、認知症の人においては自分にとって意味のある感覚だけを取捨選択する機能に障害が起こっていると指摘しています。
「クリスティーンさんは『ショッピングセンター、診療所、デイケアのようなところに行くと、ラジオやテレビの音、電話の鳴る音、人の話し声などの雑音があり、人の往き来が激しい。それはまるで泡立て器のように、頭のなかをかき混ぜてしまう』と言う。そこで『耳栓をして行くことにした』とも書いておられる。
これは単なる感覚過敏ではない。自分にとって意味ある刺激だけを選択し、あとは無視する機能の障害である。感覚のスクリーニング機能の障害とよんでおこう。彼女は『脳のフィルターがなくなってしまったような感じ』と表現している。
これを注意の障害(メモ2参照)と考えることもあながち無理ではない。
刺激が氾濫する時間帯が多く、感覚のスクリーニングがうまく機能しない人は『うるさい』と感じる。その結果、混乱し、いらいらして行動にまとまりがなくなってしまう人は確かにいる。
この感覚のスクリーニング障害は、アルツハイマー型認知症より血管性認知症の人あるいは若年発症のアルツハイマー病者に多くみられるようである。」(小澤 勲:認知症とは何か 岩波新書出版, 東京, 2005, pp123-126)
メモ1:クリスティーン
1995年に46歳の若さでアルツハイマー病と診断されたクリスティーン・ボーデンさんは、自らの心の旅路を書きつづり、診断を受けた3年後に一冊目の本を出版しました(邦訳:私は誰になっていくの?─アルツハイマー病者からみた世界 桧垣陽子訳, クリエイツかもがわ, 2003)。
本を書き上げたクリスティーンさんは、結婚相談所に登録し元外交官のポール・ブライデンさんと知り合い、1999年に再婚しクリスティーン・ブライデンとなりました。
ところで、クリスティーン・ブライデンさんの病名に関しては、実は1998年に前頭側頭型痴呆症と再診断されております。前頭側頭型痴呆症であることに関しては、クリスティーン・ブライデンさん自身が著書「私は誰になっていくの?─アルツハイマー病者からみた世界」の続編「私は私になっていく─痴呆とダンスを」において、「私が前頭側頭型痴呆症と診断されたのは46歳の時でした(診断当初はアルツハイマー病だと思われていました)」(一部改変)と述べております(クリスティーン・ブライデン:私は私になっていく─痴呆とダンスを 馬籠久美子・桧垣陽子訳, クリエイツかもがわ, 2004, p248)。
メモ2:主な注意機能は以下の3つです(藤田郁代/関啓子編集 大槻美佳著 標準言語聴覚障害学・高次脳機能障害学 医学書院, 東京, 2009, p134)。
1 持続性注意
継時的に注意を持続させる能力。
関与する部位としては、右前頭葉という報告が多いです。
2 選択的注意
複数の刺激の中から、目標とする刺激を選択して注意を向ける機能。
この機能も右前頭葉が関与するとされています。
3 注意の配分
複数の作業を同時に行う場合に、うまく進めるのに最適な注意の配分を采配する能力。
のぞみメモリークリニック(http://nozomi-mem.jp/)の木之下徹院長は、「階段を上がる、平らでないところを歩くには、そのことに集中する必要がある。話しながら階段を上がることは同時にできないし、チューイングガムをかみながら歩くこともできない」というクリスティーン・ボーデンさんの言葉を紹介し、「『認知症の人』の苦悩は記憶力の低下だけととられがちですが、実はそれだけではありません。特徴的なのは、とても疲れやすく、注意力の低下が見られることです。例えば、それまで同時にできていたことができなくなり、気が散る環境で話しかけられても集中できなくなると言うのです。」(木之下 徹:「支援を受ける人」の立場から退院支援を考える. Nursing Today Vol.27 66-69 2012)と指摘しています。
ですから、食事に集中できる環境を整備するという視点はたいへん重要なことですね。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第760回『摂食障害と模倣―薬を混ぜるときの工夫』(2015年2月10日公開)
では摂食障害・拒食の原因にはどのようなものがあるのでしょうか。認知症ケアアドバイザーの五島シズさん(全国高齢者ケア協会監事、認知症介護研究・研修東京センター客員上級研究員)は、摂食障害・拒食の原因と対応について次のように述べております。
「拒食の原因としては、体調を崩しているとき、便秘、義歯が合わない、口腔内のトラブル、嚥下障害(水分がむせやすい、食事中にひどく咳き込むなど)見た目の好くない食事、うつ状態や不安、落ち着かない気分など、精神的なストレス、他のことに心を奪われている、食べものであることが認識できない、食べ方を忘れている、既に食事を済ませたと思っている、急激な環境の変化、食事の勧め方が適切でない、配膳が適切でない、など多様です。客観的な観察で原因を知り、対策を立て実行することが大切です。
拒食への援助は、拒食の原因が口腔内異常、身体疾患などが疑われる場合は、早期に医療につなげる必要があります。
食事を勧めても食べようとしない人には、『お茶だけでもどうぞ』と勧めて、ようすを見ます。」(五島シズ:愛をこめて─認知症のケア 看護の科学社, 東京, 2008, p61)
入院後拒食になった方に対して、息子さんに自宅で使用していたお盆と食器一式を届けてもらい、その食器にご飯を移し、「息子さんが届けましたよ」と声を掛けることで拒食が解消した事例もあったそうです(五島シズ:愛をこめて─認知症のケア 看護の科学社, 東京, 2008, pp110-111)。
なお、「拒食」を未然に防ぐという観点から、念頭においておくべき注意点があります。それは、ご飯に混ぜて服薬してもらう行為です。これにより食事の味が落ちてしまい、拒食に繋がることがあるのです。服薬困難な場合においても、ご飯に混ぜるのではなく、食後のゼリーなどに混ぜる方が好ましいと思われます。
五島シズさんは、「薬は、飲む時間が指定されています。薬を吐き出してしまうお年寄りには、食後30分に服用させるものであれば、食事の終わりころにお年寄りの好きなかぼちゃ、芋類、ヨーグルト、アイスクリームなどの少量を、小皿にわけて薬を混ぜ、『薬ですよ』と説明しないでお年寄りの口の中に入れます。間を置かず、口直しに、薬の入っていないかぼちゃやヨーグルトを与えます。薬を拒否するからといって、食事全体にまぶしたりすると、食事を拒否することにつながるので避けましょう。」(五島シズ:“なぜ”から始まる認知症ケア 中央法規, 東京, 2007, p187)と述べておられます。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第761回『摂食障害と模倣―できない部分見極めアシスト』(2015年2月11日公開)
2011年11月12日、筑波大学医学医療系臨床医学域精神医学/元教授の朝田隆先生(http://www.tsukuba-psychiatry.com/)は、第30回日本認知症学会学術集会のランチョンセミナーにおいて、摂食困難事例への対策には細かな観察・評価が欠かせないことを報告しました。その講演内容の要旨を2012年1月30日発行の「Dementia Support」が伝えておりますので以下にご紹介しましょう(Dementia Support 2012・Winter 26-27)。
「『食事』という行為は、『食べる場所に行く(歩行・移動)』『食べるのに適した位置に座る』『食物を認識する(食物だとわかる)』『食物を操作する(箸やスプーンなどを適切に使う)』『食物を口まで運ぶ』『口を開けて食物を受ける(茶碗を持つ、茶碗を口に近づける)』『食物を噛む(咀嚼)』『飲み込む(嚥下)』といった一連の動作ができて初めて完結する。認知症の人は、これらすべてができないのではなく、例えば箸の使い方がわからないなど、この中のどこかで障害が起こると食事が困難になってしまう。
どこができないのかを、『認識できるか』『認知できるか』『順番がわかるか』など行動を場面ごとに分析すると、本人がどこで困っているのかが見えてくる。見えてきたらできない部分をアシストすれば、本人は食事する一連の行為を完結できるようになる。そうなれば再び本人も食事を楽しむことができるようになる。だが、そのためには評価をしていく必要がある。『食品をまんべんなく摂取するか』『左右の手の協調技術はどうか(茶碗や皿からこぼさない、協調した効率的な動作、手前に引き寄せるなど)』『手づかみ、犬食いなどはないか』『熱いものを吹くなど食物の温度に対応が可能か』など、一点ずつ評価を行わなくてはわからない。朝田氏はこうした細かい分析が必要なことを、実際に何かの動作を行う場合に脳の電位部位がどのように変化するのかを示す波状の線が刻々と変化していく画像を紹介しながら解説した。」
脳機能の評価には、機能的磁気共鳴画像(functional Magnetic Resonance Imaging;fMRI)や脳磁図などが用いられました。
なぜ手づかみでの食事摂取になるかと言いますと、食具の使い方が分からない(失行)ために手でつかんで食べてしまうわけですね。
また朝田隆教授は、著書において「一点集中食い」という問題について言及しております(朝田 隆編集:認知症診療の実践テクニック─患者・家族にどう向き合うか 医学書院, 東京, 2011, pp164-165)。以下のその部分をご紹介します(一部改変)。
「多くの介護者が気づかれるのが、満遍なく食べられない、箸をつけるものとつけないもの偏りが大きいということである。どうも全体が見渡せない、個々の認識ができないらしい。自分に近いところから一つひとつ平らげていく。指示された食物を探すがみつけられないこともあり、まさに灯台下暗し、のように直下がみえない。目の前にお皿が4つ並んでいても、例えばおつゆならおつゆ、ご飯ならご飯と、1つに目がいったら、大抵はそれを持ってそればかりを食べる。普通は、ご飯を食べ、おかずをとり、ときにおつゆを吸って、満遍なく進行するのだが、それが一点集中食いというパターンになってしまう。周囲はお皿が見えないのではないかと感じる。せっかく考えた料理も何の役にも立たないので残さず食べさせるためにはどうしたらよいのか?と悩む。
介護者の方からいただいた回答にはこういうものがあった。
『これは、1つの丼にご飯とおかずを入れて、混ぜてしまえば完食できます。食べられれば、大きな器で1つでも、いくつかの小さな食器でも同じことです。きれいに4つ並べても、それがわかってもらえないなら、大きな器で1つのほうがよいのです。要は見た目をきれいに盛り付けるか、中身を重視し、栄養バランスを考えるかの違いです。どうしても食べさせたい、完食をさせたい場合は、1つの井に入れて混ぜる方法をお勧めします』。実に現実的でよいアイデアだと思う。」
お膳の上はなるべく単純にして、認知症の人の混乱を避けるということがポイントとなるわけですね。
P.S.
朝田 隆先生の現在の所属先
メモリークリニックお茶の水院長(東京医科歯科大学 特任教授)
http://memory-cl.jp/
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第762回『摂食障害と模倣―温かいもの、冷たいものを交互に』(2015年2月12日公開)
北海道医療大学看護福祉学部看護学科・地域保健看護学講座老年看護学の山田律子教授は、「認知症の人の摂食・嚥下障害については、大きく『摂食開始困難』『摂食中断』『食べ方の乱れ』の3つに分類するとケアの方向性が見出しやすい」と指摘しており、アルツハイマー病中期における「摂食開始困難」に関して以下のように述べております。
「配膳されたすべての食器を認知できないことや、食器数が多いと混乱して食べ始めることができないこともある。このような時には、フレンチのコース料理のように1品ずつ配膳したり、丼や弁当箱などワンプレートにすることで食べられることも多い。失行や視空間認知障害により開始できない場合には、食具の持ち方や使い方を支援したり、日本人の文化的習性にならって茶碗と箸を持つ食の構えを支援すると、スイッチが入ったかのように食べ始める人もいる。」(山田律子:認知症の原因疾患別に見た摂食・嚥下障害の特徴とケア 日本医事新報No.4604・学術 75-79 2012)
豊島区口腔保健センターあぜりあ歯科診療所(http://www.azeriashika.com/)の枝広あや子歯科医師は、「重度アルツハイマー病では『姿勢の維持ができなくなる』『食事中の注意力が継続しなくなり、食事中に眠ってしまう』ことや『食事と無関係な体動』が増え、『飲み込むのに時間がかかる』『いつまでも咀嚼し続ける』『口腔内に食べ物をためる』『口が開かない』といった口腔失行が出現するようになる。また、口腔の失行や筋力低下により一般の食物を咀嚼し食塊形成し移送することが困難になってくるので、食形態の調整が必要になる。」と話しています(枝広あや子:認知症の摂食・嚥下障害─原因疾患別の特徴とアプローチ アルツハイマー型認知症. 地域リハビリテーション Vol.7 447-452 2012)。
枝広あや子歯科医師は嚥下の工夫についても言及し、ゼリーなどの喉ごしの良いものとおかずの交互嚥下にすることで喉の通りが良くなる場合もあると話しています。また、口腔内の食べ物が溜め込みによって体温と同じになってしまうと、食べ物が入っていることの認知ができにくくなるので、温かいものと冷たいものの交互嚥下も有効であると指摘しています。
なお、枝広あや子歯科医師は食形態の調整については、注意散漫な状態の時に食べ物であると視覚認知しにくいペースト食が提供されてしまうと、「低下している注意力では食べ物であることがわからない可能性もあり、目の前の食事に興味がわかず、食べ始めることができないかもしれない。またスプーンの使い方や食べ方がわからず、ペースト食を粘土遊びのように手指でこねてしまうかもしれない。隣の人が食べている通常の食事のほうがおいしそうに見えて、隣の人の皿に手を伸ばしてしまうかもしれない。」と注意を喚起しております。
口腔失行が起きるメカニズムについて、東京ふれあい医療生協梶原診療所在宅サポートセンター長の平原佐斗司医師が言及しておりますのでご紹介しましょう。
「重度アルツハイマー型認知症の時期になると、口腔顔面失行(bucco facial disability)が出現することもあります。口腔顔面失行は、左・優位半球障害、特に左シルビウス溝周囲の上半部の損傷によって生じる症状であり、口頭で指示を受けたり模倣しようとしても、口腔と顔面の習慣的運動ができない状態で、しばしば認知症高齢者が食べられない原因となり、適切な観察とサポートが必要になります。」(平原佐斗司編著:認知症ステージアプローチ入門─早期診断、BPSDの対応から緩和ケアまで 中央法規, 東京, 2013, p27)
では、口腔失行が生じている認知症の人に対しては、どのようなことに留意しサポートすれば良いのでしょうか。
「認知症の人へ食事介助をしても口を開かない、顔を背ける、口に入れたものを吐き出すなどの行為がみられた際、単純に『食事を食べたがっていない』と判断してはいないでしょうか?
脳卒中でよくみられる麻痺による『摂食・嚥下機能障害』がなくても、こういったケースでは、食物を処理できなくなる『口腔失行』状態の場合も少なくありません。口腔失行では、処理できていない食物が口腔内にある場合に口を開けない、口から吐き出す、という行為が起こり得ます。この場合は顎下・頸部のマッサージなどで嚥下を促し、口に入っているものを嚥下し終わったことを確認してから次の一口を運ぶなどの介助が必要です。」(平野浩彦、枝広あや子:拒食・異食・嚥下障害をどうする?─認知症に伴う“食べる障害”を支えるケア. Expert Nurse Vol.29 22-27 2013)
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第763回『摂食障害と模倣―「三角食べ」しなくても』(2015年2月13日公開)
豊島区口腔保健センターあぜりあ歯科診療所の枝広あや子歯科医師がアルツハイマー型認知症(AD)における障害部位別の摂食障害の特徴とその支援の方法について言及しておりますので以下にご紹介しましょう。
「たとえば、食事を前にしてどうしたらよいか分からなくなって、困ったようにキョロキョロまわりを見渡していたり、食具をさかさに使う等、使用方法が分からないようすがうかがえたりしたならば、見当識障害や失行・失認等の困難が推察される。また、食事中にほかのなにかに気をとられてしまう、中断中に食事で遊んでしまう等の困難があれば、注意の維持が困難であると推察される。一方、食事を配膳されたときに、食事の時間であることを認識できていない場合や、食卓周囲の別のなにかに気をとられていたり、食事に対して注意を向ける(移す)ことが困難であったりする場合、注意の分割・転導の困難を疑う。ADでは、初期からとくに注意の分割と転導が障害されるといわれている(Perry RJ, Hodges JR:Attention and executive deficits in Alzheimer's diseae. A critical review. Brain Vol.122 383-404 1999)。
また、ADでは社会性があるために『取り繕い』をしてしまうため、困っていることを表現するのではなく、何とか周囲の人の模倣をして問題なくみえるように振る舞うことも見受けられる。もちろん、まわりを見渡し、うまく模倣して食事が始まればそのままでかまわないが、始められない場合は、介助者が声かけによって誘導したり、食具を正しく持つように支援したりして適切な動きのきっかけを支援する必要がある。また、ジェスチャーで食べる動作を示すことで、模倣により食事が始められるケースも少なくない。」(枝広あや子:変性性認知症高齢者への食支援. 日本認知症ケア学会誌 Vol.12 671-681 2014)
先に述べた「一点集中食い」に関しては、以前の生活習慣に根づいた行動パターンなのではないかと捉える方もおられます。
民俗研究者である六車由実さん(元・東北芸術工科大学芸術学部准教授 現在は有限会社ユニット・デイサービス「すまいるほーむ」管理者兼生活相談員)は、「認知症の進んだ利用者ほど、ご飯とおかずを一緒に食べないことが多い。まずご飯を全部食べた後に、次におかずの皿に箸を伸ばして平らげていくといった順番だ。けれど、ご飯とおかずと汁物を交互に食べていき全部を一緒に食べ終わるいわゆる『三角食べ』を小学校時代に徹底的に教育されてきた私などからすると、ご飯だけ食べる、おかずだけ食べるという食べ方がとても不自然な光景に見えてしまう。それで思わず、おかずの皿をご飯の近くに置きなおして、『ほら、お魚もおいしそうだから一緒に食べてくださいね』と声を掛けてしまったりするのだ。
しかしよく考えてみたら、『三角食べ』のほうが、ある時期の学校教育のなかで強制された特殊な食べ方なのである。ましてやご飯が何よりものおかずだった時代を生きた利用者たちにとっては、ご飯からまず平らげるというのは自然なのであり、身体の深くにある記憶なのだと言えるだろう。」と述べています(六車由実:驚きの介護民俗学 医学書院, 東京, 2012, pp67-68)。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第764回『摂食障害と模倣―ヘルパー復帰で食欲も戻った』(2015年2月14日公開)
松本診療所ものわすれクリニックの松本一生院長(元大阪人間科学大学教授)は著書の中で、担当ヘルパーの調整によって食欲不振が改善した事例を報告しています(松本一生:喜怒哀楽でわかる認知症の人のこころ 中央法規, 東京, 2010, pp135-140)。息子さんの観察力が問題解決への糸口となったケースでもあり全文ご紹介したいような素晴らしい事例ですが、著作権の関係がありますので、抜粋して以下にご紹介し(一部改変)、本シリーズを終えたいと思います。
「吉村健吾さん(仮名 74歳・男性)は一昨年の冬に脳梗塞の発作を起こして入院しました。それまでにも血管性認知症は少しずつ進行しており、ベースには糖尿病がありました。50代後半に発病した糖尿病は一進一退を繰り返し、網膜症とともに認知症を引き起こしました。
同居する息子とその妻が日中仕事に出るため、吉村さんは『昼間独居』の生活を送っていましたが、なかなか社会資源の活用には至りませんでした。脳血管障害のある人に起こりがちな性格変化によって、何度か利用しようとしたデイサービスの利用者の人たちと馴染むことは簡単にはできませんでした。
試しにデイサービスを利用した日にもムッツリして表情を変えず、1日中何も話さないので、吉村さんの周囲には誰も近づきませんでした。その日の終わりに職員が声をかけたとたん、彼は金切り声を上げてしまいました。
結局、『デイサービスは無理だろう』という見解になり、在宅で家族がケアをしながら、必要に応じてショートステイの利用を組みこんでいくという方針になりました。
3か月ほど経過して、女性ホームヘルパーから疑問が投げかけられました。『私たちは本当に吉村さんの役に立っているのだろうか。彼は何の反応も示さない。むしろ嫌がっているのではないか』と。また数日前に息子が何気なく『介護保険はお金がかかるから大変…』と漏らしていたことも気にかかっていました。
それを聞いたケアマネジャーはサービス担当者会議の時間を設けました。しかし出席した主治医、訪問看護師、ホームヘルパー、家族は皆、会議の途中で言葉に詰まってしまいました。誰1人として、なぜ今の吉村さんにこれだけのサービス提供が必要なのかをはっきりと理解していなかったからです。ケアマネジャーは金銭的にゆとりのない家族のことを考えて、訪問看護を続けるかわりに訪問介護を減らして様子を見ることにしました。これによって男性ホームヘルパーがケアプランから外れることになりました。
それから2週間後のことです。ケアマネジャーのもとに息子から電話がかかってきて、『父がほとんど食事をしないんです』と悲壮な声で状況を伝えてきました。ここ数日、看護師やホームヘルパーからも吉村さんの食事量が減っているという報告がケアマネジャーのもとにありました。主治医も往診しましたが、脳梗塞や糖尿病の悪化は認められません。電話口で息子はこう言いました。
『思えば私たちがあの(男性の)ホームヘルパーさんがもう来ないと話した時から、食事の量が減ってきたように思います』
いったい男性ホームヘルパーはどのようなかかわりを吉村さんにしていたのでしょうか。ケアマネジャーは呼び出して聞いてみました。すると男性ホームヘルパーは申し訳なさそうに話し始めました。
『私は定年を過ぎてから第二の人生を考えてホームヘルパーになりました。けれど研修中も働き始めてからも、自分が当事者に向き合ったときに何をしてあげればよいのかわかりませんでした。そこで毎日、吉村さんのお宅に行くたびに新聞を読むことにしたのです。はじめは適当な時間つぶしのつもりでしたが、そのうち不思議なことに気づきました。私が新聞を読み始めると、それまで知らん顔をしていた吉村さんが少しずつこちらに向いてきたのです』
その話を聞いた息子は驚いてケアマネジャーに言いました。『そういえば父は元気なころ、毎日の出来事でこころに残った記事を新聞から切り抜いてスクラップ帳に貼っていました。家には“今年の記録”として何冊も残っています。それが父の趣味だったのかもしれません』
男性ホームヘルパーはかかわり方にさぞ苦労したことでしょう。しかし何をすればよいかわからず苦し紛れにとった行動は、しっかりと吉村さんに受け入れられていました。新聞を読んでもらうことが吉村さんにとって何よりの『楽しさ』になり、つらい状況を補う力になっていました。
男性ホームヘルパーが吉村さんの担当に復帰したことで、食欲は急速に改善しました。彼にとって日々のニュースはどんな料理よりも大切な『生きる糧』だったのです。」
「毒が盛られている」という発言から,食べない原因は妄想の可能性が考えられました.内服への拒否が強かったためハロペリドール(セレネース
【洪 英在、竹村洋典:食事を食べない患者さん. Gノート Vol.3 No.6(増刊) 959-964 2016】
私の感想:
拒食への対応は本当に悩みますね。
新聞で食欲が回復するケースなんてなかなか想像できないですよね。
アピタルで紹介した「拒食」関連の記述を一気にご紹介しますね。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第757回『摂食障害と模倣―正面に座って食べる』(2015年2月7日公開)
重度認知症患者さんの介護者の方から時折聞かれることに、「認知症が進行してから食べることを忘れるようになってきたのですがどうすればよいでしょうか?」といった質問があります。
食事を拒んでいるのではありません。食べようとしない状況です。
こんな時にまず最初に行われる方法は、意外と基本的なことですが言われないと案外気づかないことです。それは、患者さんの正面に座り、患者さんに見えるように食べるということです。目の前の人が食べている姿を見ると、模倣するかのように食べることを思い出してくれるのです。
「ミラーニューロンの発見『物まね細胞』が明かす驚きの脳科学」という本にとっても興味深い記述がありますのでご紹介しましょう。
「大人が赤ん坊の真似をすれば、赤ん坊は喜ぶ。もし私が友人宅での集まりに出かけていって、その家に赤ん坊がいたなら、私は真っ先にその赤ん坊のすることを真似してみせる。するといきなり、私はその子の一番の注目株になる(もちろん両親を除いて)。赤ん坊は模倣ごっこをするのが大好きなのだ。また、親と赤ん坊がしょっちゅうお互いに真似をしあうのは誰もが知るところだろう。実際、このときの模倣(と親和力)は発達中の脳にあるミラーニューロンを強化する主要形成因子の一つなのかもしれない。…(中略)…まだ話し方を知らない幼児どうしがいっしょに遊ぶときは、たいてい模倣ごっこをする。そして模倣ごっこを熱心にやる幼児ほど、一年から二年後に、言葉を多く使うようになるのだ。」(マルコ・イアコボーニ:ミラーニューロンの発見「物まね細胞」が明かす驚きの脳科学 塩原通緒訳, 早川書房発行, 東京, 2011, pp68-70)
ミラーニューロンの果たす興味深い役割については、また後日ご紹介する予定ですが、ミラーニューロンシステムを活用して認知症高齢者のコミュニケーション能力の向上を図ろうという試みもありますので若干その研究についてご紹介しておきましょう。
「Nonverbal Communication Rehabiltation(NCR)療法は、ミラーニューロンシステムの機能をリハによりさらに活性化すれば、認知症高齢者のコミュニケーション能力の向上、特に感情や好意等の心の内面を含めた意思疎通の向上を図ることができ、『心の通った』看護・介護の実現に役立てるために開発された。また、これにより、社会性が向上すれば、他のリハプログラムに対する積極性も増し、認知機能やADL・QOLの向上につながっていくことも期待されるものである。このなかで、介護において訓練しやすいプログラムとして組み立てられたものが、『にこにこリハ』である。」(長屋政博:認知症に対するリハビリテーション. 診断と治療 Vol.102 349-354 2014)
ただし、「模倣」は使い方を間違うと、精神の発達に悪影響を及ぼしうることも知られていますので注意して下さい。
マルコ・イアコボーニは、幼少期のメディア暴力の視聴が及ぼすその後の攻撃性・反社会的行動・犯罪性との関係について以下のように言及しています(一部改変)。
「1960年代にニューヨーク州にて、約1,000人の子どもを対象として実施された調査において、もともとの攻撃性や、教育や社会階級などの主要な変数を調整した上で、メディア暴力を幼少期に目にすることが約10年後にあたる高校卒業後の攻撃性や反社会的行動と相関関係にあることが実証された。この結果だけでも充分に注目に値するものだが、続きはまだある。同じ少年たちをさらに10年、つまり最初の調査から合計22年にわたって追跡調査したところ、結果はまたも明確だった。幼少期のメディア暴力の視聴と幼少期の攻撃行動は、30歳時の犯罪性と相関関係にあったのである!」(マルコ・イアコボーニ:ミラーニューロンの発見「物まね細胞」が明かす驚きの脳科学 塩原通緒訳, 早川書房発行, 東京, 2011, pp251-252)
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第758回『摂食障害と模倣―何を「食事」と認識するか』(2015年2月8日公開)
さて、摂食障害への対応に話を戻しましょう。
埼玉社会保険病院の福光由希子認知症看護認定看護師は、食事の最中に席を離れ、他人の食事に手を伸ばしてしまったCさん(70歳代、女性)の事例を紹介しています(福光由希子:状況別・やるべきこと、やってはいけないこと─食事. Nursing Today Vol.27 24-26 2012)。一部改変して以下にご紹介します。
Cさんは、高度の認知機能低下があり、攻撃的になる等の症状が出現し治療目的で入院しました。時々むせ込みがあるためペースト食に変更されました。すると、主食に果物を混ぜたり、途中で席を立ったり、他人の食事に手を伸ばしトラブルに発展してしまいました。
スタッフはCさんの様子を観察し、種々の工夫を検討していきます。
Cさんは自分で食事を口に運ぶ能力は残っていて、食欲もあり、介助を受ければ毎食ほぼ全量摂取できていました。そこでスタッフは、「白い器に白いご飯」だと認識ができず途中で残してしまうのではないかと考え、見分けがつきやすいように器の色を赤色に変更しました。
また、Cさんの様子を観察していると、おやつや家族が持ち込むものは普通の形態のものでもむせ込むことなく摂取できていました。スタッフは、ペースト食が「食事」と認識できず、いろいろな物を混ぜてしまったのではないかと考えました。そして、他人の食事に手を伸ばしてしまったのは、それがCさんにとって「食事」「自分が食べたいもの」と認識されたためだと考え、「食事形態の変更」を試みました。主治医や栄養士と相談し、少しずつ食事の形態をアップし数週間後には常食(副食は「刻み」)を摂取できるようになりました。
また、食事の途中で席を立ってしまったときのCさんの表情は眉間にシワが寄った険しい表情であり、何らかのストレスを感じていることが伺えました。自分の思いを他者に伝えることができまないCさんにとって食堂のざわついた雰囲気や耳から入ってくる音がストレスになり、食事に集中できる環境ではなかったのではないかと考え、スタッフが数名配置されている介助席から、一人で落ち着いて食べられる席に変更してみました。
これらの対応によりCさんは途中で席を立つことなく自力で全量摂取ができるようになりました。常食になってからは、お膳ごと提供しても食事を混ぜることもなくなり、発語が限られていたCさんから笑顔で「おいしい」という言葉も聞けるようになったそうです。
なお余談ですが、私は大学卒業後1年目後半から2年目前半の研修医時代を埼玉社会保険病院で過ごしました。私が勤務していたのは1983年(昭和58年)12月から1984年7月までの8か月間です。当時の名称は、「社会保険埼玉中央病院」でした。脳神経外科病棟は6階北病棟でした。救急当番日以外の日は、ほとんど毎晩のように飲屋街に出掛けていたことが懐かしく思い出されます。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第759回『摂食障害と模倣―食事に集中できる環境を』(2015年2月9日公開)
精神科医の小澤勲さん(故人)は著書の中で、クリスティーンさん(メモ1参照)が語った言葉を紹介し、認知症の人においては自分にとって意味のある感覚だけを取捨選択する機能に障害が起こっていると指摘しています。
「クリスティーンさんは『ショッピングセンター、診療所、デイケアのようなところに行くと、ラジオやテレビの音、電話の鳴る音、人の話し声などの雑音があり、人の往き来が激しい。それはまるで泡立て器のように、頭のなかをかき混ぜてしまう』と言う。そこで『耳栓をして行くことにした』とも書いておられる。
これは単なる感覚過敏ではない。自分にとって意味ある刺激だけを選択し、あとは無視する機能の障害である。感覚のスクリーニング機能の障害とよんでおこう。彼女は『脳のフィルターがなくなってしまったような感じ』と表現している。
これを注意の障害(メモ2参照)と考えることもあながち無理ではない。
刺激が氾濫する時間帯が多く、感覚のスクリーニングがうまく機能しない人は『うるさい』と感じる。その結果、混乱し、いらいらして行動にまとまりがなくなってしまう人は確かにいる。
この感覚のスクリーニング障害は、アルツハイマー型認知症より血管性認知症の人あるいは若年発症のアルツハイマー病者に多くみられるようである。」(小澤 勲:認知症とは何か 岩波新書出版, 東京, 2005, pp123-126)
メモ1:クリスティーン
1995年に46歳の若さでアルツハイマー病と診断されたクリスティーン・ボーデンさんは、自らの心の旅路を書きつづり、診断を受けた3年後に一冊目の本を出版しました(邦訳:私は誰になっていくの?─アルツハイマー病者からみた世界 桧垣陽子訳, クリエイツかもがわ, 2003)。
本を書き上げたクリスティーンさんは、結婚相談所に登録し元外交官のポール・ブライデンさんと知り合い、1999年に再婚しクリスティーン・ブライデンとなりました。
ところで、クリスティーン・ブライデンさんの病名に関しては、実は1998年に前頭側頭型痴呆症と再診断されております。前頭側頭型痴呆症であることに関しては、クリスティーン・ブライデンさん自身が著書「私は誰になっていくの?─アルツハイマー病者からみた世界」の続編「私は私になっていく─痴呆とダンスを」において、「私が前頭側頭型痴呆症と診断されたのは46歳の時でした(診断当初はアルツハイマー病だと思われていました)」(一部改変)と述べております(クリスティーン・ブライデン:私は私になっていく─痴呆とダンスを 馬籠久美子・桧垣陽子訳, クリエイツかもがわ, 2004, p248)。
メモ2:主な注意機能は以下の3つです(藤田郁代/関啓子編集 大槻美佳著 標準言語聴覚障害学・高次脳機能障害学 医学書院, 東京, 2009, p134)。
1 持続性注意
継時的に注意を持続させる能力。
関与する部位としては、右前頭葉という報告が多いです。
2 選択的注意
複数の刺激の中から、目標とする刺激を選択して注意を向ける機能。
この機能も右前頭葉が関与するとされています。
3 注意の配分
複数の作業を同時に行う場合に、うまく進めるのに最適な注意の配分を采配する能力。
のぞみメモリークリニック(http://nozomi-mem.jp/)の木之下徹院長は、「階段を上がる、平らでないところを歩くには、そのことに集中する必要がある。話しながら階段を上がることは同時にできないし、チューイングガムをかみながら歩くこともできない」というクリスティーン・ボーデンさんの言葉を紹介し、「『認知症の人』の苦悩は記憶力の低下だけととられがちですが、実はそれだけではありません。特徴的なのは、とても疲れやすく、注意力の低下が見られることです。例えば、それまで同時にできていたことができなくなり、気が散る環境で話しかけられても集中できなくなると言うのです。」(木之下 徹:「支援を受ける人」の立場から退院支援を考える. Nursing Today Vol.27 66-69 2012)と指摘しています。
ですから、食事に集中できる環境を整備するという視点はたいへん重要なことですね。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第760回『摂食障害と模倣―薬を混ぜるときの工夫』(2015年2月10日公開)
では摂食障害・拒食の原因にはどのようなものがあるのでしょうか。認知症ケアアドバイザーの五島シズさん(全国高齢者ケア協会監事、認知症介護研究・研修東京センター客員上級研究員)は、摂食障害・拒食の原因と対応について次のように述べております。
「拒食の原因としては、体調を崩しているとき、便秘、義歯が合わない、口腔内のトラブル、嚥下障害(水分がむせやすい、食事中にひどく咳き込むなど)見た目の好くない食事、うつ状態や不安、落ち着かない気分など、精神的なストレス、他のことに心を奪われている、食べものであることが認識できない、食べ方を忘れている、既に食事を済ませたと思っている、急激な環境の変化、食事の勧め方が適切でない、配膳が適切でない、など多様です。客観的な観察で原因を知り、対策を立て実行することが大切です。
拒食への援助は、拒食の原因が口腔内異常、身体疾患などが疑われる場合は、早期に医療につなげる必要があります。
食事を勧めても食べようとしない人には、『お茶だけでもどうぞ』と勧めて、ようすを見ます。」(五島シズ:愛をこめて─認知症のケア 看護の科学社, 東京, 2008, p61)
入院後拒食になった方に対して、息子さんに自宅で使用していたお盆と食器一式を届けてもらい、その食器にご飯を移し、「息子さんが届けましたよ」と声を掛けることで拒食が解消した事例もあったそうです(五島シズ:愛をこめて─認知症のケア 看護の科学社, 東京, 2008, pp110-111)。
なお、「拒食」を未然に防ぐという観点から、念頭においておくべき注意点があります。それは、ご飯に混ぜて服薬してもらう行為です。これにより食事の味が落ちてしまい、拒食に繋がることがあるのです。服薬困難な場合においても、ご飯に混ぜるのではなく、食後のゼリーなどに混ぜる方が好ましいと思われます。
五島シズさんは、「薬は、飲む時間が指定されています。薬を吐き出してしまうお年寄りには、食後30分に服用させるものであれば、食事の終わりころにお年寄りの好きなかぼちゃ、芋類、ヨーグルト、アイスクリームなどの少量を、小皿にわけて薬を混ぜ、『薬ですよ』と説明しないでお年寄りの口の中に入れます。間を置かず、口直しに、薬の入っていないかぼちゃやヨーグルトを与えます。薬を拒否するからといって、食事全体にまぶしたりすると、食事を拒否することにつながるので避けましょう。」(五島シズ:“なぜ”から始まる認知症ケア 中央法規, 東京, 2007, p187)と述べておられます。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第761回『摂食障害と模倣―できない部分見極めアシスト』(2015年2月11日公開)
2011年11月12日、筑波大学医学医療系臨床医学域精神医学/元教授の朝田隆先生(http://www.tsukuba-psychiatry.com/)は、第30回日本認知症学会学術集会のランチョンセミナーにおいて、摂食困難事例への対策には細かな観察・評価が欠かせないことを報告しました。その講演内容の要旨を2012年1月30日発行の「Dementia Support」が伝えておりますので以下にご紹介しましょう(Dementia Support 2012・Winter 26-27)。
「『食事』という行為は、『食べる場所に行く(歩行・移動)』『食べるのに適した位置に座る』『食物を認識する(食物だとわかる)』『食物を操作する(箸やスプーンなどを適切に使う)』『食物を口まで運ぶ』『口を開けて食物を受ける(茶碗を持つ、茶碗を口に近づける)』『食物を噛む(咀嚼)』『飲み込む(嚥下)』といった一連の動作ができて初めて完結する。認知症の人は、これらすべてができないのではなく、例えば箸の使い方がわからないなど、この中のどこかで障害が起こると食事が困難になってしまう。
どこができないのかを、『認識できるか』『認知できるか』『順番がわかるか』など行動を場面ごとに分析すると、本人がどこで困っているのかが見えてくる。見えてきたらできない部分をアシストすれば、本人は食事する一連の行為を完結できるようになる。そうなれば再び本人も食事を楽しむことができるようになる。だが、そのためには評価をしていく必要がある。『食品をまんべんなく摂取するか』『左右の手の協調技術はどうか(茶碗や皿からこぼさない、協調した効率的な動作、手前に引き寄せるなど)』『手づかみ、犬食いなどはないか』『熱いものを吹くなど食物の温度に対応が可能か』など、一点ずつ評価を行わなくてはわからない。朝田氏はこうした細かい分析が必要なことを、実際に何かの動作を行う場合に脳の電位部位がどのように変化するのかを示す波状の線が刻々と変化していく画像を紹介しながら解説した。」
脳機能の評価には、機能的磁気共鳴画像(functional Magnetic Resonance Imaging;fMRI)や脳磁図などが用いられました。
なぜ手づかみでの食事摂取になるかと言いますと、食具の使い方が分からない(失行)ために手でつかんで食べてしまうわけですね。
また朝田隆教授は、著書において「一点集中食い」という問題について言及しております(朝田 隆編集:認知症診療の実践テクニック─患者・家族にどう向き合うか 医学書院, 東京, 2011, pp164-165)。以下のその部分をご紹介します(一部改変)。
「多くの介護者が気づかれるのが、満遍なく食べられない、箸をつけるものとつけないもの偏りが大きいということである。どうも全体が見渡せない、個々の認識ができないらしい。自分に近いところから一つひとつ平らげていく。指示された食物を探すがみつけられないこともあり、まさに灯台下暗し、のように直下がみえない。目の前にお皿が4つ並んでいても、例えばおつゆならおつゆ、ご飯ならご飯と、1つに目がいったら、大抵はそれを持ってそればかりを食べる。普通は、ご飯を食べ、おかずをとり、ときにおつゆを吸って、満遍なく進行するのだが、それが一点集中食いというパターンになってしまう。周囲はお皿が見えないのではないかと感じる。せっかく考えた料理も何の役にも立たないので残さず食べさせるためにはどうしたらよいのか?と悩む。
介護者の方からいただいた回答にはこういうものがあった。
『これは、1つの丼にご飯とおかずを入れて、混ぜてしまえば完食できます。食べられれば、大きな器で1つでも、いくつかの小さな食器でも同じことです。きれいに4つ並べても、それがわかってもらえないなら、大きな器で1つのほうがよいのです。要は見た目をきれいに盛り付けるか、中身を重視し、栄養バランスを考えるかの違いです。どうしても食べさせたい、完食をさせたい場合は、1つの井に入れて混ぜる方法をお勧めします』。実に現実的でよいアイデアだと思う。」
お膳の上はなるべく単純にして、認知症の人の混乱を避けるということがポイントとなるわけですね。
P.S.
朝田 隆先生の現在の所属先
メモリークリニックお茶の水院長(東京医科歯科大学 特任教授)
http://memory-cl.jp/
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第762回『摂食障害と模倣―温かいもの、冷たいものを交互に』(2015年2月12日公開)
北海道医療大学看護福祉学部看護学科・地域保健看護学講座老年看護学の山田律子教授は、「認知症の人の摂食・嚥下障害については、大きく『摂食開始困難』『摂食中断』『食べ方の乱れ』の3つに分類するとケアの方向性が見出しやすい」と指摘しており、アルツハイマー病中期における「摂食開始困難」に関して以下のように述べております。
「配膳されたすべての食器を認知できないことや、食器数が多いと混乱して食べ始めることができないこともある。このような時には、フレンチのコース料理のように1品ずつ配膳したり、丼や弁当箱などワンプレートにすることで食べられることも多い。失行や視空間認知障害により開始できない場合には、食具の持ち方や使い方を支援したり、日本人の文化的習性にならって茶碗と箸を持つ食の構えを支援すると、スイッチが入ったかのように食べ始める人もいる。」(山田律子:認知症の原因疾患別に見た摂食・嚥下障害の特徴とケア 日本医事新報No.4604・学術 75-79 2012)
豊島区口腔保健センターあぜりあ歯科診療所(http://www.azeriashika.com/)の枝広あや子歯科医師は、「重度アルツハイマー病では『姿勢の維持ができなくなる』『食事中の注意力が継続しなくなり、食事中に眠ってしまう』ことや『食事と無関係な体動』が増え、『飲み込むのに時間がかかる』『いつまでも咀嚼し続ける』『口腔内に食べ物をためる』『口が開かない』といった口腔失行が出現するようになる。また、口腔の失行や筋力低下により一般の食物を咀嚼し食塊形成し移送することが困難になってくるので、食形態の調整が必要になる。」と話しています(枝広あや子:認知症の摂食・嚥下障害─原因疾患別の特徴とアプローチ アルツハイマー型認知症. 地域リハビリテーション Vol.7 447-452 2012)。
枝広あや子歯科医師は嚥下の工夫についても言及し、ゼリーなどの喉ごしの良いものとおかずの交互嚥下にすることで喉の通りが良くなる場合もあると話しています。また、口腔内の食べ物が溜め込みによって体温と同じになってしまうと、食べ物が入っていることの認知ができにくくなるので、温かいものと冷たいものの交互嚥下も有効であると指摘しています。
なお、枝広あや子歯科医師は食形態の調整については、注意散漫な状態の時に食べ物であると視覚認知しにくいペースト食が提供されてしまうと、「低下している注意力では食べ物であることがわからない可能性もあり、目の前の食事に興味がわかず、食べ始めることができないかもしれない。またスプーンの使い方や食べ方がわからず、ペースト食を粘土遊びのように手指でこねてしまうかもしれない。隣の人が食べている通常の食事のほうがおいしそうに見えて、隣の人の皿に手を伸ばしてしまうかもしれない。」と注意を喚起しております。
口腔失行が起きるメカニズムについて、東京ふれあい医療生協梶原診療所在宅サポートセンター長の平原佐斗司医師が言及しておりますのでご紹介しましょう。
「重度アルツハイマー型認知症の時期になると、口腔顔面失行(bucco facial disability)が出現することもあります。口腔顔面失行は、左・優位半球障害、特に左シルビウス溝周囲の上半部の損傷によって生じる症状であり、口頭で指示を受けたり模倣しようとしても、口腔と顔面の習慣的運動ができない状態で、しばしば認知症高齢者が食べられない原因となり、適切な観察とサポートが必要になります。」(平原佐斗司編著:認知症ステージアプローチ入門─早期診断、BPSDの対応から緩和ケアまで 中央法規, 東京, 2013, p27)
では、口腔失行が生じている認知症の人に対しては、どのようなことに留意しサポートすれば良いのでしょうか。
「認知症の人へ食事介助をしても口を開かない、顔を背ける、口に入れたものを吐き出すなどの行為がみられた際、単純に『食事を食べたがっていない』と判断してはいないでしょうか?
脳卒中でよくみられる麻痺による『摂食・嚥下機能障害』がなくても、こういったケースでは、食物を処理できなくなる『口腔失行』状態の場合も少なくありません。口腔失行では、処理できていない食物が口腔内にある場合に口を開けない、口から吐き出す、という行為が起こり得ます。この場合は顎下・頸部のマッサージなどで嚥下を促し、口に入っているものを嚥下し終わったことを確認してから次の一口を運ぶなどの介助が必要です。」(平野浩彦、枝広あや子:拒食・異食・嚥下障害をどうする?─認知症に伴う“食べる障害”を支えるケア. Expert Nurse Vol.29 22-27 2013)
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第763回『摂食障害と模倣―「三角食べ」しなくても』(2015年2月13日公開)
豊島区口腔保健センターあぜりあ歯科診療所の枝広あや子歯科医師がアルツハイマー型認知症(AD)における障害部位別の摂食障害の特徴とその支援の方法について言及しておりますので以下にご紹介しましょう。
「たとえば、食事を前にしてどうしたらよいか分からなくなって、困ったようにキョロキョロまわりを見渡していたり、食具をさかさに使う等、使用方法が分からないようすがうかがえたりしたならば、見当識障害や失行・失認等の困難が推察される。また、食事中にほかのなにかに気をとられてしまう、中断中に食事で遊んでしまう等の困難があれば、注意の維持が困難であると推察される。一方、食事を配膳されたときに、食事の時間であることを認識できていない場合や、食卓周囲の別のなにかに気をとられていたり、食事に対して注意を向ける(移す)ことが困難であったりする場合、注意の分割・転導の困難を疑う。ADでは、初期からとくに注意の分割と転導が障害されるといわれている(Perry RJ, Hodges JR:Attention and executive deficits in Alzheimer's diseae. A critical review. Brain Vol.122 383-404 1999)。
また、ADでは社会性があるために『取り繕い』をしてしまうため、困っていることを表現するのではなく、何とか周囲の人の模倣をして問題なくみえるように振る舞うことも見受けられる。もちろん、まわりを見渡し、うまく模倣して食事が始まればそのままでかまわないが、始められない場合は、介助者が声かけによって誘導したり、食具を正しく持つように支援したりして適切な動きのきっかけを支援する必要がある。また、ジェスチャーで食べる動作を示すことで、模倣により食事が始められるケースも少なくない。」(枝広あや子:変性性認知症高齢者への食支援. 日本認知症ケア学会誌 Vol.12 671-681 2014)
先に述べた「一点集中食い」に関しては、以前の生活習慣に根づいた行動パターンなのではないかと捉える方もおられます。
民俗研究者である六車由実さん(元・東北芸術工科大学芸術学部准教授 現在は有限会社ユニット・デイサービス「すまいるほーむ」管理者兼生活相談員)は、「認知症の進んだ利用者ほど、ご飯とおかずを一緒に食べないことが多い。まずご飯を全部食べた後に、次におかずの皿に箸を伸ばして平らげていくといった順番だ。けれど、ご飯とおかずと汁物を交互に食べていき全部を一緒に食べ終わるいわゆる『三角食べ』を小学校時代に徹底的に教育されてきた私などからすると、ご飯だけ食べる、おかずだけ食べるという食べ方がとても不自然な光景に見えてしまう。それで思わず、おかずの皿をご飯の近くに置きなおして、『ほら、お魚もおいしそうだから一緒に食べてくださいね』と声を掛けてしまったりするのだ。
しかしよく考えてみたら、『三角食べ』のほうが、ある時期の学校教育のなかで強制された特殊な食べ方なのである。ましてやご飯が何よりものおかずだった時代を生きた利用者たちにとっては、ご飯からまず平らげるというのは自然なのであり、身体の深くにある記憶なのだと言えるだろう。」と述べています(六車由実:驚きの介護民俗学 医学書院, 東京, 2012, pp67-68)。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第764回『摂食障害と模倣―ヘルパー復帰で食欲も戻った』(2015年2月14日公開)
松本診療所ものわすれクリニックの松本一生院長(元大阪人間科学大学教授)は著書の中で、担当ヘルパーの調整によって食欲不振が改善した事例を報告しています(松本一生:喜怒哀楽でわかる認知症の人のこころ 中央法規, 東京, 2010, pp135-140)。息子さんの観察力が問題解決への糸口となったケースでもあり全文ご紹介したいような素晴らしい事例ですが、著作権の関係がありますので、抜粋して以下にご紹介し(一部改変)、本シリーズを終えたいと思います。
「吉村健吾さん(仮名 74歳・男性)は一昨年の冬に脳梗塞の発作を起こして入院しました。それまでにも血管性認知症は少しずつ進行しており、ベースには糖尿病がありました。50代後半に発病した糖尿病は一進一退を繰り返し、網膜症とともに認知症を引き起こしました。
同居する息子とその妻が日中仕事に出るため、吉村さんは『昼間独居』の生活を送っていましたが、なかなか社会資源の活用には至りませんでした。脳血管障害のある人に起こりがちな性格変化によって、何度か利用しようとしたデイサービスの利用者の人たちと馴染むことは簡単にはできませんでした。
試しにデイサービスを利用した日にもムッツリして表情を変えず、1日中何も話さないので、吉村さんの周囲には誰も近づきませんでした。その日の終わりに職員が声をかけたとたん、彼は金切り声を上げてしまいました。
結局、『デイサービスは無理だろう』という見解になり、在宅で家族がケアをしながら、必要に応じてショートステイの利用を組みこんでいくという方針になりました。
3か月ほど経過して、女性ホームヘルパーから疑問が投げかけられました。『私たちは本当に吉村さんの役に立っているのだろうか。彼は何の反応も示さない。むしろ嫌がっているのではないか』と。また数日前に息子が何気なく『介護保険はお金がかかるから大変…』と漏らしていたことも気にかかっていました。
それを聞いたケアマネジャーはサービス担当者会議の時間を設けました。しかし出席した主治医、訪問看護師、ホームヘルパー、家族は皆、会議の途中で言葉に詰まってしまいました。誰1人として、なぜ今の吉村さんにこれだけのサービス提供が必要なのかをはっきりと理解していなかったからです。ケアマネジャーは金銭的にゆとりのない家族のことを考えて、訪問看護を続けるかわりに訪問介護を減らして様子を見ることにしました。これによって男性ホームヘルパーがケアプランから外れることになりました。
それから2週間後のことです。ケアマネジャーのもとに息子から電話がかかってきて、『父がほとんど食事をしないんです』と悲壮な声で状況を伝えてきました。ここ数日、看護師やホームヘルパーからも吉村さんの食事量が減っているという報告がケアマネジャーのもとにありました。主治医も往診しましたが、脳梗塞や糖尿病の悪化は認められません。電話口で息子はこう言いました。
『思えば私たちがあの(男性の)ホームヘルパーさんがもう来ないと話した時から、食事の量が減ってきたように思います』
いったい男性ホームヘルパーはどのようなかかわりを吉村さんにしていたのでしょうか。ケアマネジャーは呼び出して聞いてみました。すると男性ホームヘルパーは申し訳なさそうに話し始めました。
『私は定年を過ぎてから第二の人生を考えてホームヘルパーになりました。けれど研修中も働き始めてからも、自分が当事者に向き合ったときに何をしてあげればよいのかわかりませんでした。そこで毎日、吉村さんのお宅に行くたびに新聞を読むことにしたのです。はじめは適当な時間つぶしのつもりでしたが、そのうち不思議なことに気づきました。私が新聞を読み始めると、それまで知らん顔をしていた吉村さんが少しずつこちらに向いてきたのです』
その話を聞いた息子は驚いてケアマネジャーに言いました。『そういえば父は元気なころ、毎日の出来事でこころに残った記事を新聞から切り抜いてスクラップ帳に貼っていました。家には“今年の記録”として何冊も残っています。それが父の趣味だったのかもしれません』
男性ホームヘルパーはかかわり方にさぞ苦労したことでしょう。しかし何をすればよいかわからず苦し紛れにとった行動は、しっかりと吉村さんに受け入れられていました。新聞を読んでもらうことが吉村さんにとって何よりの『楽しさ』になり、つらい状況を補う力になっていました。
男性ホームヘルパーが吉村さんの担当に復帰したことで、食欲は急速に改善しました。彼にとって日々のニュースはどんな料理よりも大切な『生きる糧』だったのです。」
幼老統合ケア むく 看護小規模多機能型居宅介護 ママハタ 赤ちゃん先生 佐伯美智子 唐津 [幼老統合ケア]
ミニ講演会 in 福岡─ママハタの目指すもの【2016.9.30】

https://www.facebook.com/atsushi.kasama.9/videos/vb.100004790640447/645469438956072/?type=2&theater
佐伯美智子さんが「赤ちゃん先生プロジェクト」について熱く語ってくれました。
Yuutube動画は↓
https://youtu.be/fYDYvLdGCi4
ママハタは↓
https://www.mamahata.net/
取材の依頼先は、ママハタ・唐津の佐伯美智子さんです。
https://www.facebook.com/michiko.saiki?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all
P.S.
みっちゃんが運営する看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)『むく』(https://www.facebook.com/shoukibomuku/?pnref=lhc)は、2017年4月1日オープンです。

みっちゃんの長年の夢「幼老統合ケア」がいよいよ動き始めます。
みっちゃんの目標は、「あおいけあ」に追いつけ追い越せかな・・。
http://www.aoicare.com/
アピタル連載より
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第57回『幼老統合ケア 赤ん坊のぬいぐるみが効く』(2013年2月18日公開)
復習シリーズを続けてきましたが、年度が替わる前にお伝えしておきたい話題がありますので、いったん復習シリーズをお休みします。
『ひょっとして認知症? Part1』の第158回『高齢者に対する虐待とストレス』において、音とリズムさんから「思いやりの気持ちや態度を養うカリキュラムを幼稚園の時から実施」という提起がありました。
その際私は、「『幼老統合ケア』という試みを実践している施設があります。私も本で読んだだけの知識しか持ち合わせておらず実際の現場は見ていないのですが・・。いずれ『ひょっとして認知症?』においてご紹介します。」とお返事しました。
今回は、「幼老統合ケア」に関連した話題をいくつかご紹介します。
認知症高齢者においては、赤ん坊のぬいぐるみをとっても大切そうに抱きかかえている状況がしばしば見受けられます。認知症の人が怒ったりした際に、ぬいぐるみを渡すと落ち着きを取り戻すこともあります。このような方に対しては、「幼老統合ケア」が向いているのではないかと私は考えています。
認知症ケアにおいて非常に大きな問題である「認知症の行動・心理症状」(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia;BPSD)に対して、赤ちゃんの人形の子守りするという「役割」を担ってもらうことにより、BPSDが軽快した事例が報告されておりますので一部改変して以下にご紹介しましょう(髙尾千香子、上城憲司、岩谷清一 他:人形介在介入によって役割を獲得し、BPSDが減少した事例. 認知症ケア事例ジャーナル Vol.5 258-265 2012)。
「人形介在介入後の変化点を以下に述べる。
①徘徊
ロビーで人形と一緒に過ごすことが多くなりほぼ消失した。
②ゆがんだ解釈
以前は入浴やトイレ動作を促すことに労力と時間をかけていたが、『赤ちゃんのために、お母さんもお風呂に入りましょうか』『赤ちゃんと一緒にトイレに行きませんか』などと声かけをすると、拒否なく導入できるようになった。
③もの隠し・収集癖
②のような声かけを行うことで、自室の床頭台の中やシルバーカーの中に入れた、汚れた尿取りパットを嫌がらず処理させてくれるようになった。
④無意味な作業
徘徊がなくなったことで、他の患者の部屋に入って物を触ることはなくなった。
⑤対人トラブル
毎晩共有スペースで寝てしまうことにより発生していたが、自室ベッドで『赤ちゃんと添い寝してもらえますか』と促すと、起床時間まで眠ることができるようになったため、ほとんどみられなくなった。
⑥介入前の不潔行為
尿意不良で失禁していることが多く、紙パンツ交換の拒否も多かった。また、自らトイレに行き尿取りパットを便器に流して詰まらせてしまうことや、自分で片付けようとして汚してしまう場面もたびたびみられた。
介入後は、前述のように徘徊や拒否が少なくなったため、時間誘導がスムーズに進み失禁も減った。」
この事例においては、スタッフが人形について、「こちらの方とはどのようなご関係ですか」と質問したところ、「家族よ」とはっきりと答えたそうです。
認知症を患った高齢女性にドールセラピーを行うと、子育てという「役割」の賦与による効果なのかBPSDが顕著に改善することはしばしば経験されます。特に、人形を自分の子どもであると誤認するようなケースにおいては、ドールセラピーは著効する可能性があるのかも知れませんね。
Facebookコメント
理学療法士の三好春樹さんが『認知症介護─現場からの見方と関わり方(雲母書房)』という本を2014年5月15日に出版されました。この本は2003年に『痴呆論』として世に出され、その後、「認知症」という呼称が広がりつつあった2009年にあえて『痴呆論』のままで<増補版>として刊行されたものを、新たな題と本文中の「痴呆」の「認知症」への書き換え、および巻頭への新たな章の書きおろしを加えて、改訂新刊として刊行されたものです。
私は、『痴呆論』は読んだことがありませんが『認知症介護─現場からの見方と関わり方』を読みました。その中に「役割」の賦与を応用した非常に印象深いケア方法が記載してありましたので以下にご紹介したいと思います。
「子ども」になって泣いてみる
「介護アドバイザーの青山幸広に、彼がアドバイザーをしているグループホームのスタッフから電話がかかってくる。『どうしても家に帰ると言ってきかないんです。いろいろやってみたんだけど、今日だけは効果がありません。どうしたらいいでしょう』と。グループホームの夜勤は1人だけだから、いっしょに散歩してくるわけにもいかず、電話の向こうで弱り切っている。
『泣け!』と青山幸広。『えっ?』と受話器の向こうで驚いている声が聞こえる。『しやがみこんで、えーん、えーんと大げさに泣いてみろ!』。
果たして、『帰る』と言い張っていた認知症の入所者は、驚いて『泣かなくてもいいよ、どうしたんだい』とやさしく声をかけてきたという。母親になっているのだ。家に帰らなくても、目の前に自分の役割が現われたのである。
青山と同じく介護アドバイザーをしている高口光子も、やはりこの手を使う。困り果てると、突然子どものように泣き出すのだ。困らせていた老人が彼女をあやし始め、すっかり母親のようになってしまったら、『なんちゃって』と泣くのを止める。すると老人は、その展開にはついていけず、どうしていいかわからなくなるという。そこで、みんなで『バンザイ』を三唱する。すると、最初の問題が何だかわからないままお開きになって、老人は部屋に帰っていくという。ここまでくると、介護を知らない人にはまるでシュールな世界に見えるに違いない。
家族が誘っても風呂に入りたがらない女性がいた。他人のほうがいいのでは、とヘルパーが週に2回訪問して、家の風呂に誘うことになった。しかし、説得すればするほど拒否が強くなり、家族は『これならヘルパーに来てもらわなくても』と言い始めた。
困ったヘルパーはある日、子どもになってみることにした。子どもが小さかったころの話を、喜んですることに気づいたからだ。『お風呂に入りたいんですけど、一人じゃ入れないんで、いっしょに入ってもらえませんでしょうか』と言うと、『困った子だねえ』と言って、脱衣室に行って自ら服を脱いだという。それ以降、ほぼ毎回、この方法で成功している。」(三好春樹:認知症介護─現場からの見方と関わり方 雲母書房, 東京, 2014, pp156-158)
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第58回『幼老統合ケア 子どもの顔を見たとたんに笑顔』(2013年2月19日公開)
信濃毎日新聞の飯島裕一編集委員と佐古泰司文化部記者が書かれた著書(認知症の正体 PHP研究所発行, 2011, pp257-262)においては、認知症のお年寄りが暮らすグループホームに、学童保育の子どもたちが日常的に訪れて一緒に過ごす「幼老統合ケア」を実施している洛和グループホーム山科小山(京都市山科区)の取り組みが紹介されており、怒りっぽかった高齢者が子どもたちとの触れ合いを通じて笑顔を取り戻していく様子が報告されています。
『ルポ 認知症ケア最前線』(佐藤幹夫:岩波新書, 東京, 2011, pp52-76)においては、地域のなかにあって、障害者も高齢者も児童も受け入れてケアをする共生スタイルの「富山型デイサービス」について紹介されています。そして代表的な「富山型デイサービス」であるデイケアハウス「にぎやか」(阪井由佳子代表)の様子が詳細に報告されています。「にぎやか」は、富山市の新興住宅街の一角にあり外見は普通の民家です。「にぎやか」では基本的に見学は受けていないそうです。しかし、ボランティアとして一緒に活動してくれるのは構わないそうです。スタッフばかりか、お年寄りたちも入れ替わり立ち替わり赤ん坊に声をかけ、冗談を言い、笑い声が絶えない「にぎやか」の様子が紹介されています。
前述の著書『ルポ 認知症ケア最前線』第4章のタイトルは、「幼児たちの介護力」です。大阪府堺市の複合型福祉施設「ベルタウン」が取り上げられています。「ベルタウン」も「幼老統合ケア」を実践しています。「ベルタウン」内の特別養護老人ホーム「ベルライブ」の白川美保子施設長の言葉をご紹介しましょう。
「普段はまったく会話をしないお年寄りや、職員に話しかけられても芳しい反応が見られない認知症のお年寄りたちにあっても、子どもたちの顔を見たとたんに表情が一変する。なかには子どもたちに自分から話しかけるようになったり、ほとんど笑顔を見せない人が、ゼロ歳児がワゴン車に乗って遊びにやってきた姿を見るだけで、笑顔があふれたりする。」
このように、子どもたちの存在は、認知症の人(メモ1参照)に笑顔をもたらしたのです。
メモ1:認知症の人
医療法人社団こだま会こだまクリニックの木之下徹院長は、「イギリスの医療やケアの国家的ガイドラインには、『OUTPATIENTS(外来患者)』『INPATIENTS(入院患者)』などの例外を除き、『PATIENTS(患者)』が削除されている。またオーストラリアの『アルツハイマーズ オーストラリア』という組織では、この点においてはもっと先進的に、用語の規定集についても公表されている。また同国の認知症関連の医学論文でも、『患者』という言葉が『人』になっている」ことを紹介しています(医師へフィードバックすべき情報. 薬局 Vol.61 3641-3645 2010)。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第59回『幼老統合ケア 子どもたちも元気になる』(2013年2月20日公開)
笑う頻度と認知機能低下との関連を調べた研究があります(大平哲也:笑い・ユーモア療法による認知症の予防と改善. 老年精神医学雑誌 Vol.22 32-38 2011)。
笑いの頻度が少ないと認知機能低下が有意に高いことが報告されています。「幼老統合ケア」の意義はこんなところにあるのかも知れませんね。
さらに、「幼老統合ケア」においては、子どもたちがエンパワーメントされるという可能性も秘めています。
『認知症ケアは地域革命!』という著書の第三章「子どもたちと育んだマインド」(牧坂秀敏:現代書館, 東京, 2010, pp144-181)では、認知症高齢者との触れ合いを通して成長していく子どもたちの様子が描かれています。
2007年の夏休みに、認知症対応型デイサービス「地域福祉館・藤井さん家」を二人の小学生が「ボランティア体験」として訪れます。
高齢者は子どもたちとの触れ合いによって、子どもの名前を覚えたり、明るくなったり、動きが良くなったりしていきます。
子どもたちは、藤井さん家の人たちと、ゆったりした空間でゆっくりとした時間を過ごすなかで、心が満たされていき優しくなっていきます。
ある先生はそんな子どもたちの様子を以下のように考察したそうです。
「藤井さん家は、学校と異なり時間がゆっくり流れている。だから、学校で救われない子どもが藤井さん家で救われるだろう」と。
人権を守ろうとする「藤井さん家」の文化に子どもたちが出会うことで、子どもたちがエンパワーメントされたのです。
第三章は以下の言葉で締めくくられています。
「ここでいうエンパワーメントとは、だれでもが潜在的にもっている力や個性をいきいきと発揮することである。それは、人と人との間にいきいきとした出会い、関係があってはじめて可能となる。」
日本社会事業大学大学院福祉マネジメント研究科の今井幸充教授は、「判断能力を失った者の支援活動では、一方的な情報提供や助言をするのではなく、彼らが自立し、自ら問題を解決していくパワーを発揮できる能力を高める方向に導くことが重要で、このような支援行為をエンパワメント(エンパワーメント)という。このエンパワメント実践に重要なことは、認知症患者やその家族の自己決定権を擁護(権利擁護)、すなわち、アドボカシー(advocacy)であり、患者アドボカシーとは『患者の味方になってその利益・権利のために闘うこと』である。」と述べています(今井幸充:認知症患者に薬物療法を始める際の病名告知について. 治療 Vol.93 1830-1834 2011)。
特定非営利活動法人宮城福祉オンブズネット「エール」理事の内田幸雄さんは、「『おせっかい』という言葉がある。必ずしもよい表現として使われない言葉である。しかし、地域における高齢者の権利擁護を推進するには、この『おせっかい』という視点が重要であると考える。隣近所に対して地域がまったく『無関心』になったとき、そこでは社会的弱者に対する権利擁護の視点が失われることになるからである。」(内田幸雄:地域における権利擁護. 日本認知症ケア学会誌 Vol.10 440-446 2012)と指摘しています。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第60回『幼老統合ケア 子どもとの交流で変わる』(2013年2月21日公開)
さて、グループホーム「ふぁみりえ」ホーム長の大谷るみ子さんは、運営推進会議(メモ2参照)の場で、認知症の人と子どもたちを交流させてみてはどうかという意見が出された経緯を以下のように紹介しています(大谷るみ子:人生の舞台は今、グループホームから地域へ─豊かな人生を支援する. 現代のエスプリ通巻507号 ぎょうせい発行, 東京, 2009, pp132-145)。
「ハツミさんは、入居してしばらく『私はどうしてここにおるとね?』『まだ自分で暮らせる自信があるのに』と繰り返されていた。娘さんともあらためて本人への向き合い方を相談し、『ものわすれによって一人で暮らすことが難しいことが増えたこと』『おかあさんが一人だと心配でたまらない、ここは家からも近く安心して住めるところなので、ここでおかあさんに暮らしてほしい』と伝えることになった。『そんなこと言われても』と最初は少し寂しそうにされていたが、その後『私はどうしてここに?』という質問は少なくなられた。
それからしばらくして、『私は職安に行きたい』とハツミさん。『働きたい』『託児所もしたい』と。そこでそんなハツミさんの希望を、『運営推進会議』の場で話し合うことにした。『託児所はすぐにはできないけど、孫を連れて遊びに来ますよ』と委員の小野さん。『近くの幼稚園の子どもたちと交流してみては』などの意見が出た。近くの保育園に時々通ったり、月に一回『ママ&赤ちゃんの会』をすることになった。また月に二回、敷地内に開設した地域交流センターを活用し、ハツミさんを中心として『ささやかカレーの店』をすることになった。メニューきめ、買物、料理、会場セッティング、食券販売、給仕、おもてなしなど、入居者の皆さんが役割を分担され、職員も一緒にやり始めて二年目である。」
メモ2:運営推進会議
2006年(平成18年)4月の介護保険法改正により、グループホーム(制度上の正式名称:認知症対応型共同生活介護)が地域密着型サービスの1つに位置づけられました。同時に、地域住民を交えてグループホームの運営課題や地域交流を進める鍵として、「運営推進会議」の設置・運営が義務付けられました。民生委員、自治会長、消防団、行政や地域包括支援センターなど、さまざまな顔ぶれの会議です。認知症の人に対する理解を深め、地域全体で支え合うための地域づくりとして、またグループホームの中だけで支えるのではなく、入居者の暮らし方や支援の実際・課題などを取り上げ協議したり、何より本人の希望を聴き、本人・家族、施設と地域住民の交流の場としても意義深い制度です。
厚生労働省は2012年6月18日に、「認知症施策の方向性」(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/dementia/dl/houkousei-02.pdf)について提示しました。独立行政法人国立長寿医療研究センター脳機能診療部第二脳機能診療科の武田章敬医長はこれに関連して、「『今後の認知症施策の方向性について』報告書においては、認知症グループホーム事業所が地域の認知症ケアの拠点としての活動を行うことが求められ、具体的には認知症対応型通所介護やショートステイといったサービスの提供や、在宅で生活する認知症の人や家族への相談や支援を行うとされている。」(武田章敬:わが国の認知症施策. 月刊薬事 Vol.54 1596-1600 2012)と報告しております。
認知症グループホームにおける運営推進会議の実態に関する調査結果もウェブサイト上にて公開(http://ghkyo.or.jp/home/pdf/chousakenkyuujigyouhoukoku-20100520.pdf)されておりますのでご参照下さい。
Facebookコメント
「幼老統合ケアは、大牟田の大谷るみ子さんたちによって始められ、全国に広がりを見せている。認知症の問題解決を早めるためにも、小学生の頃から認知症を意識させることには意義がある。」(中村重信:私たちは認知症にどう立ち向かっていけばよいのだろうか. 南山堂, 東京, 2013, p221)
Facebookコメント
「サロンづくり」とひと言で言ってしまえば簡単なことのように感じられるかも知れませんが、立ち上げの大変さ&維持することの大変さ…など並々ならぬ努力が求められます。
そんな大変さを垣間見ることができる論文がありますので、抜粋して以下にご紹介しましょう(有馬みき、青木明美:地域住民と協働したサロンづくりとその活動─過疎高齢化の小さな田舎町「A町」の将来をになう人材が生まれることを願って. 認知症ケア事例ジャーナル Vol.6 253-262 2013)。
【論文抄録】
A町は、深刻な少子高齢化、過疎化、就労の場の減少など、多くの問題を抱えている。そこでB認知症対応型通所介護(Bデイサービス)では、施設内だけでなくA町の問題点にも向き合い、将来を見据えた活動を行う必要があると考え、制度にはない資源づくりを住民と協働して行った。本事例報告では、その過程を紹介するとともに、その活動の場が、将来をになう次世代の人づくりの場になることを目指して行われている取り組みについて報告する。
【論文本文】
はじめに
A町の人口は約24,500人、年少人口(14歳以下の人口)は約2,400人、高齢化率は約34%である(200X年12月時点)。人口の推移予測は、2035年には人口が約13,500人、年少人口は約950人へと減少し、高齢化率は50%を超える見込みであり、深刻な過疎、少子高齢化の問題を抱えている。また、農業や水産業が低迷し、新規採用を行っている地元企業はほとんどない状況で、就労の場が大幅に減少しているため、高校を卒業する時点でA町外へ就職、進学する若者がほとんどである。
サロンのオープンから地域へのよびかけ;小学生にどう声をかけたか
200X-1年4月にサロンをオープンし、回覧板や広報で周知を促した。また、いっしょに立ち上げてきた住民に、精力的に口コミで宣伝をしてもらうように頼んだ。しかし、お茶のみ場やギャラリーでの利用を中心に交流が始まったということもへあり、比較的年齢が高い人たちの利用は増えても、目的としていた子どもたちには思うように利用してもらえなかった。
職員は、どうすれば「子どもたちが保護者や先生に見守られながらも、ルールに縛られず楽しくすごせ、かつ、世代間交流ができるようなサロン」になるかについて考えた結果、「宿題をする場所」としてサロンを提僕することを思いついた。そして、200X-1年7月に「夏休みにお友だちとサロンで宿題をしませんか?」とよびかけるチラシを作成して、小学生に配布した。小学生が堅苦しく感じず、来るのが楽しみになるように、かき氷を自由につくれることや、あめや飲み物を無料で提供することをチラシに盛り込んだ。そうすると、それまでの状況がうそのように小学生が集まり始め、宿題をするだけでなく、いつの間にかルールを守りながらも通信型のゲームやカードバトルゲームをしたり、さまざまな楽しみ方をしたりするようになった(図)。そのことが、より多くの子どもたちが集まるきっかけになっていった。
サロンとBデイサービスの位置関係にこだわった理由
そして、サロンは「場所」のみでは成り立たず、「人」が重要であると考えた。
職員が、Bデイサービスをオープンな空間にして、サロンからだれもがいつでも入って来やすい雰囲気づくりを行ったところ、徐々に小学生が「Bデイサービスではなにをしているのだろう」と興味をもち始めたようであった。そこで、「高齢者がレクリエーションを楽しむために人手が足りないから手を貸して」と小学生に伝えると、恥ずかしそうにしながらも、レクリエーションに参加してくれるようになった。最初は恐る恐る入ってきていた小学生が、いつの間にか慣れて、自然と高齢者や職員と交流を深めることができるようになった。
考察・課題
当初は小学生の利用はなく、子どもが高齢者とかかわることをいやがっているのではないかとさえ思っていた。しかし、環境の提供ときっかけづくりをていねいに行うことで小学生自身が自ら考え、行動し、日常的に交流を楽しむことができることが分かった。好奇心旺盛な小学生が、自分の力で新たな人や場所とつながることに楽しさや喜びを感じたことで、Bデイサービスやサロンに訪れる頻度が多くなり、職員だけでなく、高齢者にも興味をもち始めたと考える。その姿に職員は勇気づけられ、高齢者が元気になることも再確認した。
当初、Bデイサービスやサロンでは、福祉をになう人材づくりしかできないと考えていた。しかし、認知症の人は、福祉サービスのみで支えられるはずもなく、町のなかのさまざまな人に支えられ、はじめて安心して生活することができる。将来、小学生たちが福祉の仕事に携わらなくても、地域の生活のなかで重要な役割を果たしていくに違いない。サロンの活動を通じて、大人だけでなく、小学生のときから「人は年老いて死んでいくこと」を身近に感じてもらうことは「認知症になっても安心して暮らせる町づくり」に直結する。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第61回『幼老統合ケア 住み慣れた地域で密着型サービスの模索』(2013年2月22日公開)
認知症グループホームについてご紹介しましたので、小規模多機能型居宅介護についてもお話しておきましょう。
厚生労働省は、「地域密着・小規模化」を掲げ、在宅療養への移行を推進しています。しかしながら、特別養護老人ホームの入所申込者は42.1万人もいることが報告されており(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003byd.html)、現状では施設志向が依然として強いのが現状です。それは、在宅療養においては、介護サービスを受けている時間を除く大半の時間、介護者が介護に携わる必要があり、主たる介護者の精神的な負担が強いことが大きな要因として挙げられています。
2006年(平成18年)4月の介護保険制度改正により、今後増加が見込まれる認知症高齢者が、できる限り住み慣れた地域での生活が継続できるように、新たなサービス体系として地域密着型サービスが創設されました。
「地域密着型サービス」に属するサービスの中で、小規模多機能型居宅介護は、「通い(デイサービス)」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問(訪問介護)」や「泊まり(ショートステイ)」を組み合わせてサービスを提供します。「通い」「訪問」「泊まり」の3つの機能を兼ね備えた小規模多機能型居宅介護は、自宅を拠点として生活したいと願う人にとって使い勝手のよいサービスとして注目されております。
このサービスが創設される前は、「通い」、「訪問」と「泊まり」などの介護サービスをそれぞれ別の施設で受けることにより、それぞれの場面で利用者に対応するスタッフが異なるために馴染みの関係やケアの連続性が保たれないといった問題がありました。
小規模多機能型居宅介護が主に担っている役割は、中等度・重度となっても在宅での生活が継続できるように支援することです。
小規模多機能型居宅介護には利用定員が定められており、1つの事業所あたり25人以下の登録制となっています。1日に利用できる通所サービスの定員は15人以下、泊まりは9人以下となっています。
小規模多機能型居宅介護の「泊まり」機能の充実が今後ますます期待されていくように思われますね。
Facebookコメント
特養入居待ち―参入拡大に知恵を絞れ【2014年4月5日付朝日新聞・社説】
「住み慣れた自宅で暮らせる在宅介護は望ましい。ただ、施設の役割も大きい。今後の高齢化を考えれば、施設運営への参入規制を見直し、特に都市部での供給を増やすべきだ。
特別養護老人ホーム(特養)への『入居待ち』が約52万人にのぼり、4年前の前回調査より10万人増えたことが厚生労働省の集計でわかった。
特養は、比較的安い費用で介護を含めた生活の面倒をみてくれる。市町村が施設を割り当てていた時代と違い、介護保険のもとで入居の申し込みは自由にできる。
政府は『地域包括ケア』という考え方のもと、自宅で最後まで暮らすことを目標に、在宅介護を推進する。
52万人のなかには、今は必要ないが将来への不安からとりあえず申し込んだ高齢者もいる。そうした人ができるだけ長く自宅で過ごせるよう、サービスを充実させることは大切だ。
ただ、それには時間がかかるし、地域によってばらつきもある。『在宅重視』のかけ声だけでは、暮らしが行き詰まるお年寄りに対応しきれない。頼れる家族が近くにおらず、地域とのつながりも薄い高齢者は、特に首都圏で急増する。
地価が高く施設が足りないため、こうした高齢者を抱えきれず地方に送り込もうとする動きが強まる懸念もある。
都市部を中心に、特養の整備を進めていくべきだ。
それには、地方自治体が施設の増加による財政負担の拡大を恐れて設けている総量規制を見直すとともに、参入規制を緩めていく必要がある。
現在、特養をつくれるのは、地方公共団体のほかは、社会福祉法人に限られる。低所得の人にも『終のすみか』を提供する公益性が理由とされる。
だが、介護保険のもと、契約に基づき特養のサービスを提供して報酬を受け取るだけなら、運営を社会福祉法人に限定する理由はない。
多様な事業者が参入すれば、都市部でネックになっている土地の確保や資金調達でも新たな知恵が出てくる可能性がある。競争を通じたサービスの質の向上も期待できる。
人員配置など入居者保護の規制は緩めるべきではない。営利法人から『これではもうからない』と緩和を要求されて介護の質を落とせば、『うば捨て山』をつくるだけだ。
在宅介護で暮らしを支えつつも、『最後のとりで』として特養がある。そんな地域づくりが現実的なのではないか。」
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第62回『幼老統合ケア 期待される小規模多機能型居宅介護』(2013年2月23日公開)
小規模多機能型居宅介護は非常に期待されているサービスなのですが、事業者側からみると制度上の問題点もあるようです。
高齢者総合ケアセンターこぶし園の小山剛総合施設長は、「本制度の利点は通い・泊まり・訪問に対応するばかりではなく、それまでの介護保険3施設と認知症対応型共同生活介護のように1か月の利用額を定額にしたことで、利用回数に一律的な制限を受けないことから、そのときの必要量に合わせた柔軟な使い方ができることにある。ただし介護報酬の設定は重症度が中等度~重度用に設計されているため、軽度の認知症の段階から連続的な使用が行われると事業者の負担が増加するというジレンマも内在している。」と指摘しています(小山 剛:福祉施設ケアと精神科入院治療の現状と課題. 老年精神医学雑誌 Vol.23 572-577 2012)。
介護保険三施設とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム;特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設の3施設を指します。
小規模多機能型居宅介護の利用料金例は、NAGOYAかいごネットのウェブサイトをご参照下さい。この表を見ても分かりますように、要介護2以下と要介護3以上では報酬単位にかなりの開きがありますから、認知症患者さんが早い段階から連続的に利用していくには、事業者側に資金的な余力がないとサービス利用が困難という状況になってしまいますね。
小規模多機能型居宅介護の利用料金をNAGOYAかいごネットのウェブサイトで見てみますと、要介護5では28,120単位と記載されておりますね。すなわち、2万8120円(1割の自己負担分)を基本料金として、それ以外に、食事代・宿泊費(首都圏で一泊三千円前後)・おむつ代などが別途かかることになるわけです(2012年10月28日発行週刊ダイヤモンド臨時増刊・通巻4454号 p9)。
2012年10月28日発行の週刊ダイヤモンド臨時増刊・通巻4454号では、情報公開に積極的な1721ホームから回答を得て、「有料老人ホーム ベストランキング」を特集しており、8つの指標から評価し、31都道府県にある介護付き有料老人ホームを合計得点(100点満点)の高い順に紹介しております。たいへん興味深い資料だと思います。
なお、2012年10月28日発行の週刊ダイヤモンド臨時増刊(通巻4454号)においては、小規模多機能型居宅介護の特徴が分かりやすくまとめられておりますので抜粋してご紹介しましょう(一部改変)。
「小規模多機能型居宅介護は、かつては『宅老所』といわれた仕組みを2006年度から制度化したものだ。通所事業所に通い、食事や入浴、機能訓練などを受ける『デイサービス(通所介護)』、施設に短期間宿泊して、食事や入浴などの生活介護を受ける『ショートステイ(短期入所)』、これに訪問介護を加えた三つのサービスを提供する事業所だ。2012年4月からはこれに訪問看護を加え、四つの機能が一体化した『複合サービス』が新たに始まった。医療的な措置を必要とする要介護者を抱える家族にとっては、朗報といえよう。
使う際は、まず、自宅近くの小規模多機能型居宅介護の事業者に登録する。その上で、必要に応じて上記四つのサービスを利用する。
例えば、共働き世帯の方で、急な残業などで帰りが遅くなっても、職員が自宅に利用者を迎えに行って、(小規模多機能施設に)宿泊させることができる。柔軟性のあるサービスのために、家族からは喜ばれることが多い。
いずれも要介護度に応じた定額料金となっている。どれだけ介護サービスを受けても、出来高払いと違い支払額が大きく膨らむ心配はないから安心して利用できる“懐”に優しいサービスといえる。
小規模多機能型居宅介護を利用する場合、介護保険のルール上、サービス内容が重複する他の介護サービス(デイサービス、ショートステイ、訪問介護)と併用はできないので注意が必要だ。
このため、デイサービスの単独利用から、小規模多機能型居宅介護に変えようと思っても、デイサービスのケアマネジャーが、顧客を手放すことを嫌って承諾しないことがある。利用者本人もデイサービスに親しい職員や仲間がいると、離れるのを嫌がって拒むという事態がしばしば発生する。
また、小規模多機能型居宅介護の事業者は、デイサービス、ショートステイ、訪問介護の三つ(訪問看護を含めると四つ)を等しくこなせることが原則だが、人手不足の地域や住宅が分散している地域では訪問介護が十分に行えない事業者も少なくない。
中には意図的に、経営面で効率的なデイサービスやショートステイだけしかやらない事業者もいるから注意したい。」(2012年10月28日発行週刊ダイヤモンド臨時増刊・通巻4454号 pp24-25)
さて、実際にはどのようにして小規模多機能型居宅介護の施設を探せばよいのでしょうか。
「かいごDB」のウェブサイト(http://kaigodb.com/)におきましては、小規模多機能型居宅介護を実施している施設を都道府県別に閲覧できますのでご参照下さい(http://kaigodb.com/kaigo_service/200/)。施設数が少ないのがネックとなっており、なかなか該当施設が見つけられないのが現状ではないでしょうか。なお、地域密着型サービスは、市区町村が施設事業者を指定しており、原則として事業所所在地に居住する被保険者のみが利用できるサービスです。
Facebookコメント
「小規模多機能型居宅介護を利用する場合、介護保険のルール上、サービス内容が重複する他の介護サービス(デイサービス、ショートステイ、訪問介護)と併用はできないので注意が必要だ。」と記載しておりますが、2013年12月17日付中日新聞に「複合型サービス」に関する記事がありましたので以下にご紹介しましょう。
看護や介護で在宅支える・「複合型」じわり普及─医療行為OK、みとりも対応
小規模多機能型居宅介護サービスに、看護機能を強化した「複合型サービス」が少しずつ増えている。看護師が多いので、退院直後の不安定な状況や終末期にも対応しやすいという。静岡市清水区にある施設「複合型ナーシングケアもも」での取り組みを紹介する。【佐橋 大】
清水区の住宅街にある施設「複合型ナーシングケアもも」。今年二月に「小規模多機能型居宅介護事業所」から転換した。高齢者約二十人が利用登録をしている。登録すれば「通い」「泊まり」「訪問介護」「訪問看護」の四サービスを、泊まりの実費負担などを除き、月単位の定額で受けられる。従来との違いは職員の四割(常勤換算)が看護師と、看護職員の割合が高い点だ。
運営会社の地域包括ケアサービス部長、高井由美子さんは「小規模多機能のときなら、ちゅうちょする人も受け入れられるようになった」と話す。例えば肺炎を繰り返し、しばしば抗生剤の点滴が必要になる人。規制のため、看護師が付き添っていても小規模多機能のサービスの中では、医療行為である点滴はできない。
医療機関に通えない人には、訪問看護のサービスで、看護師が自宅を訪れ、抗生剤を点滴するしかなかった。点滴は通常二時間以上かかるため、多忙な訪問看護で付き添うのは難しいという。複合型サービスでは、日中は看護師の常駐を義務付ける代わりに、医師の指示を受けて、点滴などの医療行為ができるようになった。
定額で訪問看護
複合型サービスは2012年四月の介護保険法の改正で、医療依存度の高い人が、地域で暮らし続けるのを支えるために導入。定員は最大二十五人。グループホームや小規模多機能型と同様、利用者は事業所のある市町村の住民に限る。
小規模多機能型との違いは、訪問看護が定額サービスの中で受けられること。その分、小規模多機能型より月額の利用料が少し高い。例えば要介護3なら、本体部分の一割負担が、小規模多機能型の月二万三千円余に対し、複合型サービスは月二万五千円余り。
厚生労働省のまとめでは六月末現荏、全国で七十三事業所が指定を受けている。中部地方では名古屋市三、福井県坂井地区広域連合(あわら市、坂井市)二、静岡市一。その後、愛知県豊橋市でも事業所が指定を受けた。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第63回『幼老統合ケア 認知症初期集中支援チームへの期待』(2013年2月24日公開)
厚生労働省は2012年6月18日に、今後の認知症施策の方向性について提示しました。それに関して2012年6月19日の朝日新聞は、以下のように報道しております(一部改変)。
「厚生労働省は6月18日、高齢化で増える認知症の新たな対策をまとめた。専門職の支援チームが患者の自宅を訪問するなど、症状の初期段階で集中的に在宅での対応を支えるのが柱。症状が悪化して精神科病院に入院するのを防ぐねらいだ。来年度から実施する。
対策の柱は、地域介護の拠点である地域包括支援センター約4200カ所などに設置する『認知症初期集中支援チーム』。看護師や保健師、作業療法士らが本人や家族から生活状況を聞き取り、症状進行の見通しを説明するほか、生活全般についても助言する。
また、このチームやかかりつけ医と連携し、認知症の専門医が早期診断する『身近型認知症疾患医療センター』も医療機関に新設。専門医は一般病院や介護施設も訪問し、地域医療を後押しする。厚労省は今回の対策を具体化した5カ年計画をつくる方針だ。」
「認知症初期集中支援チーム」というあまり聞き慣れない名称が出てきましたね。その役割について、独立行政法人国立長寿医療研究センター脳機能診療部第二脳機能診療科の武田章敬医長が分かりやすく解説しておりますのでご紹介しましょう(一部改変)。
「『今後の認知症施策の方向性について』報告書において、早期診断・早期対応を促進する観点から、看護職員、作業療法士等の専門家からなる『認知症初期集中支援チーム』を地域包括支援センター等に配置し、認知症が疑われる人の家庭を訪問し、生活状況や認知機能等の情報収集や評価を行い、適切な診断へと結びつけ、本人・家族への支援を行うとしている。また、かかりつけ医の認知症対応能力が向上し、『認知症初期集中支援チーム』の取り組みが普及するまでの間は、主として『身近型認知症疾患医療センター』の医師が『認知症初期集中支援チーム』の一員として関与したり、ケアマネジャー及びかかりつけ医等に対する専門的なアドバイスを行ったりする役割を果たすとされている。」(武田章敬:わが国の認知症施策. 月刊薬事 Vol.54 1596-1600 2012)
なお、「身近型認知症疾患医療センター」は、5年間で全国300カ所に整備する予定だそうです。
厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室の勝又浜子氏は、医学雑誌社のインタビューの中で、「認知症初期集中支援チーム」における医師・ケアマネジャーの位置づけについて次のように述べております(一部改変)。
「認知症初期集中支援チームはイギリスの認知症施策である『メモリーサービス』がモデルになっています。
メンバーは、看護師や作業療法士等で、必ずしも医師は要件になっていません。チームがかかりつけ医と連携して初期支援を行なっていくことが想定されます。またイギリスでは、このチームにケアマネジャーは入っておらず、チームが関わったあとにケアマネジャーが引き継ぐという仕組みです。日本ではどういうやり方がいいのか、2013年度からのモデル事業で模索していくことになります。必要に応じて医師が入ることもあるでしょうし、他にも精神保健福祉士や介護職、さまざまな職種がチームに入る可能性もあります。
もちろん『訪問看護師』もメンバーの有力な候補ですね。拠点は『地域包括支援センター等』となっていますが、市町村からの委託を受けた訪問看護ステーションを拠点に地域包括支援センターと連携しながら行なっていくかたちもありえます。」(認知症の「ケアの流れ」をどう変える?─これからの認知症施策の主眼と訪問看護の役割. 訪問看護と介護 Vol.18 16-20 2013)
訪問看護ステーションと地域包括支援センターが連携しながら取り組む試行例も紹介されておりますので以下にご紹介します(一部改変)。
「『認知症初期集中支援チーム』のモデル事業が、2013年度から始まる予定だ。これに先立ち、そのスキーム(概型)を検討する試行も、全国3か所で始まっている。そのうち1つは『訪問看護ステーション』を中核に地域包括支援センターと連携しての取り組みである。
その中心となっているのは、ナースケアステーション(東京都世田谷区)の片山所長だ。認知症初期集中支援チームのメンバーは今のところ、片山所長を中心とする4名の訪問看護スタッフと、ステーション外から作業療法士、連携する在宅療養支援診療所の総合内科医・精神科医である。すでに3事例の『初回アセスメント訪問』を行ない、近く『チーム員会議』を開催する予定だ(2012年12月5日現在)。
『初回アセスメント訪問』は初期集中支援計画の礎になるものであり、認知症の症状はもちろん、既往歴やその治療と服薬状況、身体状況などの『医療』の視点から、本人のパーソナリティや価値観、生活状況や生活障害、家族背景や経済状態などの『生活』の視点まで多岐にわたる。また居住環境など訪問しなければわからない項目も少なくない。片山所長は、このアセスメントを一度に2~3時間かけて行なっている。」(認知症の「ケアの流れ」をどう変える?─これからの認知症施策の主眼と訪問看護の役割. 訪問看護と介護 Vol.18 31 2013)
Facebookコメント
2014年6月9日放送クローズアップ現代「初期認知症と診断されたら… ~どうつくる支援体制~」(http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3510/)の主な放送内容を以下にご紹介しましょう。
1 日本の現状:
7年前に初期の認知症と診断された藤田和子さん(52歳)。
総合病院の脳神経内科にて、「アルツハイマー型認知症の疑い」があると告げられたものの、医師からは病名を告げられただけで症状や今後の見通しなど詳しい説明はなかった(by ナレーション)。
→放送を観ておりますと、診断の根拠としては脳血流検査が決め手の一つとなったようですが、SPECTの偽陽性率を考えますと、「現状では、軽度認知障害(MCI)と思われます。1年後に再診して診断を確認しましょう」という説明が妥当であったかな…と私は感じました。
その1年後、藤田さんは知人の紹介で認知症専門医の診察を受け(=映像を観ておりますと、その認知症専門医とは、鳥取大学医学部保健学科生体制御学の浦上克哉教授でした)、正式にアルツハイマー型認知症と診断を受け諸アドバイスを受けた。
しかし、治療は始まったものの、その後の生活を支援する体制がないことで藤田さんは苦悩を深めていきます(by ナレーション)。
認知症が初期の段階で分かっても、多くの人が不安を増幅させていると言われています(by ナレーション)。
2 認知症の初期集中支援チームは、昨年度よりモデル事業が開始されており、国は2017年度までにすべての市町村で整えようとしています。しかし現場では、初期の認知症の人をなかなか見つけられないという課題に直面しています(by ナレーション)。
3 イギリス・スコットランドの初期認知症への取り組み
認知症の人の「診断後すぐに医療の知識を持った支援者が欲しかった」という声を反映させた取り組みである「リンクワーカー」という仕組みが4年前から始まっている。
リンクワーカーは、地元のアルツハイマー協会から派遣される臨床心理士や看護師などが担い手。
診断を受け混乱しているヘンリー・ランキンさんを救ったのは、診断後まもなく自宅を訪れたリンクワーカーのトレイシー・ギルモアさんだった。
ギルモアさんがランキンさんに渡したのは、認知症の人たちの活動を収めた映像「私たちの目を通して(スコットランド認知症ワーキンググループ制作)」でした。
4 リンクワーカーは、「認知症カフェ」「当事者や家族の勉強会」を紹介するとともに、「年金・税金など優遇策の紹介」などの支援を1年間無料で提供します。
5 放送の番組のコメンテーターは、東京都健康長寿医療センター研究所の粟田主一部長でした。
粟田主一部長は、介護保険の課題として、「認知症の初期段階における『生活支援』を調節する役割(仕組み)を日本の中で何とか作り出していかないといけない」と述べるとともに、「現在、日本においてはケアマネが主にその役割を担っているが専門的な知識を持ち合わせていない場合もある。ケアマネ以外には、『認知症コーディネーター』とか『認知症地域支援推進員』という制度が作られつつある」と指摘されておりました。
P.S.
地域における医療と介護の連携の強化をはかるために、認知症地域支援推進員研修が開始されております。(平成23年以前は認知症連携担当者)認知症地域支援推進員研修は、「市町村認知症施策総合推進事業」を実施する市町村に配置された(もしくは配置予定の)認知症地域支援推進員が、医療機関や介護サービスおよび地域の支援機関をつなぐコーディネーターとしての役割を担える知識・技術を習得することが目的になります。
詳細は、厚生労働省のウェブサイト(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000133sr-att/2r98520000013459.pdf)をご覧下さい。
2012年度の受講者は263名が修了して、2年間で530名が修了しました(谷 規久子、本間 昭:病者と家族を支える社会的支援・地域連携. からだの科学通巻278号 128-136 2013)。
Facebookコメント
住み慣れた地域で豊かに暮らし続けるために認知症の初期支援を充実(2014年9月21日付朝日新聞・名古屋本社版17面─全面広告【名古屋市】)
認知症になっても住み慣れた地域で豊かな生活を過ごすためには、早期発見・早期対応が大切です。名古屋市は国の「認知症施策推進5か年計画」に基づき、平成26年度より「認知症初期集中支援チーム」を設置し、モデル事業を展開。医師、社会福祉士、看護師をチーム員として、初期支援の充実を目指しています。
対象者や家族を支援し自立サポートを行う
黒川(認知症初期集中支援チーム/医師 黒川医院院長・黒川豊さん):
認知症の問題が社会的に認識されるようになったのは、今から25年くらい前です。当時の認知症は発見されてからの余命は平均して4年。現在は約14年と、飛躍的に伸びています。近年になって、認知症の治療が早期発見・早期対応に変化していますが、初期段階から治療を始めることにより症状の進行を遅らせ、家族とよい時間を過ごすことができるようになると思います。
石川(名古屋市 健康福祉局 高齢福祉部 地域ケア推進課 地域支援係主事・石川隼さん):
黒川先生のお話のように昨今のケアの流れは、早期発見・早期対応へとシフトしています。厚生労働省が平成24年にまとめた今後の目指すべき基本目標において、早期発見により「認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けることのできる社会」の実現を目指しています。この実現のため、同年に認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)を策定。その柱となるのが「認知症初期集中支援チーム」です。名古屋市でも平成26年度より、千種区東部いきいき支援センターに支援チームを配置して、モデル事業をスタートさせました。
黒川(認知症初期集中支援チーム/医師 黒川医院院長・黒川豊さん):
今回のモデル事業の認知症初期集中支援チームは、医師、社会福祉士、看護師の3人で構成されています。認知症の人やその疑いのある人、その家族に早期から家庭訪問して関わりを持つ中で、症状の程度の確認や必要なアドバイスを行うことによって早期の診断や治療につなげ、対象者や家族を支援し、自立サポートを行うことを目的としています。
新村(認知症初期集中支援チーム/社会福祉士 名古屋市千種区東部いきいき支援センター・新村小枝子さん):
地域には認知症の疑いのある一人暮らしの高齢者もいらっしゃいますが、地域の民生委員や住民、ご家族から困っている人がいるという相談があり、私たちの活動が始まります。それぞれの分野の専門家が、違った視点からアプローチすることで、支援の内容も広がっていくと思います。
山岡(認知症初期集中支援チーム/看護師 名古屋市千種区東部いきいき支援センター・山岡美和子さん):
物忘れなどの認知症症状だけでなく、内側に隠れた低栄養や高血圧など、体の状態をお聞きしながら医師に相談をして、早期受診につなげることも私たちの役割のひとつだと思います。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第64回『幼老統合ケア 認知症300万人時代』(2013年2月25日公開)
認知症施策検討プロジェクトチームが2012年6月18日にとりまとめた「今後の認知症施策の方向性について」や、同年8月24日に公表した認知症高齢者数の将来推計などに基づいて、「認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)」が2012年9月に発表されました。
オレンジプランは、平成25年度から29年度(2013~2017年度)までの認知症施策の数値目標を示したものです。
オレンジプランの詳細は、厚生労働省のウェブサイト(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002j8dh-att/2r9852000002j8ey.pdf)にて閲覧可能です。
このpdfファイルの4頁には、認知症高齢者数の居場所別内訳が記載されております。認知症高齢者数は、305万人(2012年)から373万人(2017年)に増加すると推計されておりますが、医療機関における認知症高齢者数は38万人で変化がありません。すなわち、増加した分は、在宅介護(149万人→186万人)、居住系サービス(28万人→44万人)、介護施設(89万人→105万人)が受け皿になると想定されているわけです。
介護施設とは、介護老人福祉施設と介護老人保健施設等(介護療養型医療施設を含む)であり、このうち介護老人福祉施設を居場所とする認知症高齢者数は48万人から58万人に増加することが想定されております。
なお、介護療養型医療施設については2017年度末(平成30年3月末)に廃止予定となっております。しかしながら、2011年における介護療養型医療施設の平均在院日数は311日であり、5年前の269日から42日も延びており、入院の必要がない高齢者を病院から介護施設に移す政策が進んでおらず、介護療養型医療施設の廃止には程遠い状況にあることを2012年12月3日付日本経済新聞は1面トップニュースとして伝えております。
指定介護老人福祉施設とは、介護保険制度の施行により、老人福祉法による特別養護老人ホームが介護保険法の指定施設となったものです。すなわち、介護保険法に基づき、都道府県知事から指定を受けることにより「指定介護老人福祉施設」となり、介護保険による施設サービスの対象となります。介護施設の呼称・分類に関しては、ウィキペディア(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E)などをご参照下さい。
さて、介護老人福祉施設における10万人規模の受け皿増加は十分と言えるでしょうか? 2012年10月28日発行週刊ダイヤモンド臨時増刊が特別養護老人ホーム(特養)の待機者の現状を伝えておりますのでご紹介しましょう。
「『特別養護老人ホーム(特養)に入ることができれば、介護の負担は大幅に減るのだが…』
在宅介護が困難になった家族の声は悲痛だ。特養の待機者(申込者)は、全国で実に42万1259人で、定員の41万4668人をも上回る。受け皿を2倍に増やしても、収容し切れない勘定だ。
なかでも、首都圏の待機者は最大規模。東京都の4万3746人を筆頭に、1都3県で計9万7324人に達している。」(2012年10月28日発行週刊ダイヤモンド臨時増刊・通巻4454号 pp174-176)
このように、10万人規模で受け皿を増やしたとしても、現時点での特養待機者の1/4程度の解消にしかならないことは明白です。
では何故こんなにも特養の待機者が多いのでしょうか。
「特別養護老人ホーム(特養)に入ることができれば、介護の負担は大幅に減るのだが…」という言葉にもありますように、何と言ってもコストの安さが最大の特徴です。
2012年10月28日発行週刊ダイヤモンド臨時増刊によれば、特別養護老人ホームの月額利用料の目安は6万~15万円です。介護型老人保健施設(13~15万円)、サービス付き高齢者向け住宅(12~20万円)、グループホーム(13~20万円)、介護付き有料老人ホーム(15~35万円)に比べるとかなり低額です(2012年10月28日発行週刊ダイヤモンド臨時増刊・通巻4454号 p9)。
さらに、所得による負担軽減措置があるため、多床室タイプの特別養護老人ホームに入所する市町村民税非課税の方であれば、上記料金よりもさらに減額され、月額利用料が4~6万円程度となるケースもしばしばです。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第65回『幼老統合ケア 介護のために離職する人は5年で57万人』(2013年2月26日公開)
厚生労働省は、認知症患者が住み慣れた環境で暮らし続けられる社会の実現を今後の認知症施策の基本目標として提示しております。
具体例を挙げれば、「認知症初期集中支援チーム」を地域包括支援センター等に配置し、認知症が疑われる人の家庭を訪問し、生活状況や認知機能等の情報収集や評価を行い適切な診断へと結びつけ、本人・家族への支援を行い、在宅療養が少しでも長く継続できるようにと思案しております。
しかしながら、介護と仕事の両立は決して簡単なことではありません。2012年10月28日発行週刊ダイヤモンド臨時増刊において、フリーライターの西川敦子さんは「働く人の介護」という原稿を寄せております。抜粋して以下にご紹介します。
「晩婚化、非婚化が進み、シングルが急増。共働き家庭も増えている。その上、兄弟が少ない、となれば介護負担をもろに背負う確率は男女共に高くなる。
総務省の『就業構造基本調査』(2007年)によると、介護離職者は2002年10月からの5年間で56万8000人。離職後、無業の状態にある人は40万4000人に上る。『介護失業』は人ごとではない。危機はあなたの足元まで迫っているかもしれないのだ。
では、ある日突然、親が倒れたら、働く息子や娘はどう対応すべきなのだろうか。
思い付くのは、会社を長期間休み、介護できる態勢を整えることだが、東京大学大学院情報学環の佐藤博樹教授は『介護休業を利用し、自分で親を介護するのは極力避けるべき』と意外なアドバイスをする。
1999年に施行された『育児・介護休業法』で定められた介護休業。要介護状態にある家族1人につき通算93日間、仕事を休めることになっている。なお、その間、支給される『介護給付金』は休業前の貸金の40%だ。
だが、介護の平均期間は55.2カ月間(生命保険文化センター調べ)にも及ぶ。『3カ月間の介護休業を超えて、自ら介護を続けようとすれば、退職しか選択肢がないことになる』(佐藤氏)
6割減の収入でやりくりした揚げ句、失業。貯金も底を突き、やがて生活保護を受給する─、こんな最悪のシナリオはなんとしても避けたい。
『だからこそ介護はプロの手に任せるなどし、自らは介護サービスの調整役に徹してほしい』と佐藤氏は言う。
親が倒れたときは、真っ先に『介護と仕事を両立できる環境づくり』をするべきなのである。」(2012年10月28日発行週刊ダイヤモンド臨時増刊・通巻4454号 pp12-14)
そもそも、定年後に必要とされる生活資金3,000万円をこの不況の折りに準備できている家庭は稀な存在ではないでしょうか。「貯金も底を突き、やがて生活保護を受給」ということは、近年の日本社会の動向を見ておりますと、いとも簡単に起きてしまうことのように感じられます。
フィデリティ退職・投資教育研究所が2010年2月に実施した「サラリーマン1万人アンケート」を見ておりますと、老後難民予備軍の急増が懸念されます。その「サラリーマン1万人アンケート」の結果の一部をご紹介しましょう。
「現在の公的年金制度では安心できないと考えている人は全体の9割近くいる。それにもかかわらず、老後の生活資金を全く準備していない人が44%もいるのだ。しかも、定年退職後の資産形成を特に何もしていない人が41%に達している。さらに、老後の生活資金準備額が100万円未満(ゼロも含む)の人で、資産形成を特に何もしていない人は84%に上る。」(2012年10月28日発行週刊ダイヤモンド臨時増刊・通巻4454号 pp184-185)
なお、「定年後に必要とされる生活資金3,000万円」と記載しましたが、この数字は、「サラリーマン1万人アンケート」において、公的年金以外に必要となる退職後の生活資金の総額を聞いたところ、平均で2,989万円であったことに基づく数字です。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第66回『幼老統合ケア 「感情労働」という言葉に疑問』(2013年2月27日公開)
利用者・介護者の立場から考えると、「通い」「訪問」「泊まり」の3つの機能を兼ね備えた小規模多機能型居宅介護はたいへん有意義な施設でしょう。しかしながら、小規模ならではの職員の負担もあるようです。
「現在の高齢者介護施設における介護方法は、食事や入浴などが管理された巨大な集団生活に基づくものから、家庭的な雰囲気を追求する小規模で親身な方法に転換しつつある。それを体現するシステムとして、グループホームやユニットケアなどが登場してきた。このような介護方法は利用者の人権やケア方法にも配慮した優れたものであると考えられるが、被介護者グループの細分化に伴い、介護スタッフ1人当たりの労働負担が増加せざるをえないという問題がある。さらに、小規模介護実現のためには、より利用者の家族に近いケア対応が要求されることになり、それに伴い、在宅介護に特有な、感情労働としての心理的負担も高まると思われる。」(田辺毅彦:介護ストレスを再考する─在宅および施設介護ストレスの問題点. 認知症ケア事例ジャーナル. Vol.4 378-388 2012)
感情労働というのは、カナダの社会学者ホックシールドが提唱した概念で、それによると、現在の社会はさまざまなサービス業において、適切な感情の内容や表出の仕方が決められており、その感情ルールに対して有形無形の報酬が与えられます。
しかしながら、熱心にケアする介護スタッフからしてみると、そういった感情表出を「感情労働」という言葉に置き換えられてしまうと何とも言えない切ない気持ちになってしまうのではないでしょうか。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第67回『幼老統合ケア 「居酒屋に連れてって」をサポート』(2013年2月28日公開)
さて、宅老所「鴇嶺(ときがね)の家」およびグループホーム・小規模多機能ホーム「五根(ごこん)の家」の増田知子代表は、「通い慣れた居酒屋に行きたいという要望に対し、夜、実際に職員が利用者を居酒屋に連れて行ったこともあります。普通だったら『時間外だから家族に連れて行ってもらえば』となりますが、どうやったらできるかを考えることが大切」と述べており、自身が地域に根づく意気込みが求められ、ある意味利他的な精神が要求されると指摘しています(安西順子編著:基礎から学ぶ介護シリーズ・気づいていますか─認知症ケアの落とし穴 中央法規, 東京, 2012, pp78-87)。
しかしながら、最近では地域と交流してこなかった世代も多くなってきています。ですから、仕事で「地域と交流しよう」と言われても、頭では理解できても肌で感じていないため、実感が湧かないようです。増田知子代表は、そういった職員はあえて泥臭い場所に連れ回すようにしているそうです。町内会や自治会、地域行事など、何かしら得るものがあると言います。
さて、先程の居酒屋の件、酒好きの私としては気にかかる話ですので、もう少し詳しくご紹介しましょう。サブタイトルは、「出かければ、地域が変わる」です。
「『外で一杯やりたいなぁ』とつぶやいたお年寄りがいました。私たちはさっそく、希望があった行きつけの居酒屋に出かけてみました。下見はできるだけ行いたいと思っていますが、昔からある居酒屋の場合、店内がバリアフリーではなく、トイレも和式であることが多いです。しかし、リスクを考え始めるといつまでたっても出かけられません。今までの実践のなかで、うまくいくかどうか悩むのに時間をかけるよりも、覚悟を決めて出かけてしまうほうが道が開けることが多かったという自負がありました。
お年寄りが店内のトイレや段差をうまく使うことができなかったこともありました。認知症のある人が行くことで、お店の店員を驚かせたこともありました。しかしどの店も、昔から行きつけだった店です。一番輝いていたころを知っている店でもあり、職員が付き添っているので、何が起こっても入店を断られることはありませんでした。
後日談として、店側がトイレに手すりをつけてくれたり、段差に踏み台を置いてくれた例もありました。『おじいさんに来てもらって、いろいろと気がついた』『お年寄りが使いやすいということは、ほかのお客さんも使いやすいということ』と言ってくれる店もありました。
このように、私たちが地域に出かけることで、少しずつではあっても地域が変わっていくのです。」(安西順子編著:基礎から学ぶ介護シリーズ・気づいていますか─認知症ケアの落とし穴 中央法規, 東京, 2012, p83)
一方、宅老所「井戸端げんき」の加藤正裕施設長は、「地域づくりとは、要するに“近所づきあい”。難しい言葉を使うから、何か特別なことをしなければならないと勘違いしてしまうのです。井戸端げんきに集まっていることが地域交流です。地域とは出ていくものではなく、集まるもの、いつの間にかできるものです」と語ります(安西順子編著:基礎から学ぶ介護シリーズ・気づいていますか─認知症ケアの落とし穴 中央法規, 東京, 2012, pp108-117)。そんな「井戸端げんき」には、デイサービスの登録者以外にも、来たい人が来て大勢集まり「すし詰め」状態だそうです。
群馬大学大学院保健学研究科の山口晴保教授は著書において、「役割」の持つ重要性に関して言及しております。
「人間は本来怠け者です。日課を決めて動かないと、ついつい怠けてしまいます。定年退職して毎日家で過ごすようになったら急にボケてきたという方を、しばしば見かけます。すぐに認知症になるわけではありませんが、仕事が人生の目的だった方は、目的を失い意欲の湧かない生活になって、何をするのも面倒と閉じこもりがちになります。こうなると、うつ状態の悪循環に陥り、認知機能も低下してしまいます。脳は使わないでいると機能を失っていくからです。楽しいことがない日が続くと、やる気も失せ、身体活動の低下に伴って記憶も悪くなります。日課を決めて毎日規則的に動くようにすれば、心の平安に役立ちます。役割を果たすことは快をもたらし、脳の活性化に有効です。」(認知症予防 ─読めば納得! 脳を守るライフスタイルの秘訣─ 協同医書出版社発行, 東京, 2010, pp189-190)
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第68回『幼老統合ケア 新しいケアシステムが求められている』(2013年3月1日公開)
2011年の介護保険の改定において、2025年をめどに「地域包括ケア」が目標理念となっています。これは、おおむね30分以内に駆けつけられる圏域において医療と介護サービスが適正に提供されることです(三浦久幸、遠藤英俊:在宅での認知症ケア. 月刊薬事 Vol.54 1732-1736 2012)。
2010年3月に平成21年度老人保健健康増進事業による「地域包括ケア研究会報告書」(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/9600ee3fd4ba9b2c4925774a001e71d9/$FILE/20100622_1shiryou3_1.pdf)が発表されております。これは、2025年に実現すべき地域包括ケアの姿を示すために、2012年度からの介護保険事業計画の骨子を示したものです。
日本社会事業大学専門職大学院の今井幸充教授(精神科医)は、「『地域包括ケア研究会報告書』の提言は、大きく2つに分けることができる。1つは、地域ケアシステム構築のための国の基本原則と自治体の実施計画ならびに在宅サービスの抜本的な充実のあり方である。国の基本原則としてもっとも強調しているのが、おおむね30分以内の生活圏域で、生活上の安全・安心・健康が24時間365日確保できる地域のサービス体系の構築であり、住み慣れた地域で継続的な生活を可能にすることである。…(中略)…そしてこの報告書のもう1つの大きな提言が、地域包括ケアを支える幅広い介護人材を育成する基盤整備である。」(今井幸充:地域包括ケアシステムに思う. 日本認知症ケア学会誌 Vol.10・巻頭言 8-9 2011)と述べています。
厚生労働省の私的研究会として設置された高齢者介護研究会による「2015年の高齢者介護」(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/15kourei/index.html)の報告においても、主要な柱の一つとして認知症の人々に対する新しいケアモデルの確立が位置づけられています。すなわち、地域包括ケアシステムの確立です。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第69回『幼老統合ケア 家族や友人、近隣住民、ボランティアのサポートが必要』(2013年3月2日公開)
2012年8月27日付日本経済新聞の1面トップニュースは、「在宅医療に地域責任者(副タイトル:病院依存脱却へ)」という見出しの記事でした。記事内容を少しご紹介しましょう。
「厚生労働省は住み慣れた場所で医療や介護のサービスが受けられる体制を整えるため、中核となる人材を組織化する。平成24年度中に全国で7千人以上の責任者を配置する計画だ。地域の実情に応じた24時間体制の在宅医療や介護を実施する。入院できる患者数が限られる現状を踏まえて病院に頼りすぎる体質を改め、サービスの効率化も狙う。
現在の医療は病院完結型とも呼ばれ、1950年に80%だった自宅で死亡する人の割合は2010年で12%まで下がった。高齢者の長期入院による施設不足は深刻で、在宅で医療や介護を進めざるを得ない事情もある。
体制が整えば在宅医療費は膨らむ見通しだが、医療費の4割程度を占める入院医療費の伸びの抑制を期待できる。厚労省は医療費を適正な水準に戻すために長期入院の見直しを重視している。」
高齢者の長期入院を見直すには、何よりも在宅医療の充実が喫緊の課題となります。
東京都健康長寿医療センター研究所自立促進と介護予防研究チームの粟田主一研究部長は、「後期高齢者人口の増加、単独・夫婦のみ世帯の増加、認知症高齢者の増加、都市部における急速な高齢化、要介護認定者の増加などを背景にして、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが、日常生活圏域(30分で駆けつけられる圏域)において一体的に提供できる『地域包括ケアシステム』の構築が求められている。これは、近年世界的に活発に議論されているCommunity-based Integrated Careの理念と一致する。Community-based Integrated Careは、Community-based care(地域を基盤としたケア)とIntegrated care(統合型のケア)という2つの独立した概念で構成される。」と述べています(粟田主一:認知症医療ネットワーク構築の現状と課題. 綜合臨牀 Vol.60 1761-1762 2011)。
ケアマネジメントで活用する社会資源は、介護保険サービスや行政等によるフォーマル・サービス、そして家族や友人、近隣住民、ボランティア等によるインフォーマル・サポートに大きく区分されます。
地域包括ケアを推進していくためには、フォーマル・サービスだけでなく、インフォーマル・サポートを積極的に活用していくことが重要な視点となります。梨木さんが『ひょっとして認知症? Part1』の第406回のコメント欄「介護保険の変容」において語っていた「縁側カフェ」のアイデアもインフォーマル・サポートに該当するものですね。
厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室の勝又浜子氏は、医学雑誌社のインタビューの中で、「認知症カフェ」の意義についても言及しております。
「オレンジプランには、『認知症サポーター』の育成や『認知症カフェ』など、一般市民の啓発にあたる内容も多く含まれています。そうした取り組みを通して、地域住民ぐるみで『気づき』のポイントを早めていこうということです。」(認知症の「ケアの流れ」をどう変える?─これからの認知症施策の主眼と訪問看護の役割. 訪問看護と介護 Vol.18 16-20 2013)
認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)の詳細は、厚生労働省のウェブサイト(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002j8dh-att/2r9852000002j8ey.pdf)において閲覧可能です。
朝日新聞社の連載「認知症とわたしたち」第1部「気づきのとき・4─1人で抱え込まないで」(2013.1.6)においては、目黒認知症家族会「たけのこ」の一泊旅行の様子が紹介されましたね。「たけのこ」では、月に2回の交流会を開いており、認知症の人と家族が一緒に参加し認知症の人はボランティアと過ごすため、家族は介護から離れることができると報道されました。
そして、「たけのこ」の世話人・竹内弘道さんが自宅を開放して開催している談話サロン「ラミヨ」の様子も報道されました。「ラミヨ」においては、介護中の人だけでなく、みとった人、認知症に関心のある人も対象にしており、介護経験を語り合ったりする中で、ベテラン介護者がまだ介護に不慣れな介護者に助言する場面もあることが紹介されました。
こうしたカフェ・サロンの原点は、藤本クリニック(滋賀県守山市)の「もの忘れカフェ」(http://fujimoto-clinic.net/cafe/index.html)ではないかと思われます。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第70回『幼老統合ケア 「認知症でもだいじょうぶ」町づくり』(2013年3月3日公開)
認知症の人を支えるまちづくりを考えた場合、「認知症になっても、終の棲家として選択した『我がまち』に住み続けられるまちづくり」と「その人のそれまでの生活・歴史・人間関係を大切にしたまちづくり」の2点が具体的目標となります(http://www.jice.or.jp/jishu/k1/200709_zaitaku_pdf/3-2_ninchisho.pdf)。
そして、「認知症でもだいじょうぶ」町づくりに向けての具体的な取り組み内容を紹介しているウェブサイト(http://www.dcnet.gr.jp/campaign/)もありますのでご参照下さい。
2012年1月30日に開催された座談会に於いて、梶原診療所在宅サポートセンターの平原佐斗司医師は、認知症の人を支えるまちづくりという点から考えると、今後は都市部でのコミュニティー作りが大きな課題になるのではないかと指摘しました。以下にその部分をご紹介します。
「支えるということで私が一つ気になっているのは、これまで過去15年間、高齢化は日本全国一律に起こってきたのですが、今後は都市近郊が中心で、認知症も圧倒的に都市部に増えるという問題があります。埼玉ではこの30年間で3.1倍、千葉・神奈川では2.9倍、東京でも2.4倍です。ですから、認知症の方は首都圏ですごく増えていくのです。都市部では地方と比べるとコミュニティーの力がないですから、地域の力をもう一度つくり直すというプロセスが必要です。そのことが危機的な問題として出てくるのではないかと非常に心配しています。」
この意見に対して、座談会の司会を務めた北里大学医学部(北里大学東病院)神経内科学の荻野美恵子講師は、「宮崎に『かあさんの家』というのがあって、空いている民家を使って、そこに認知症や高齢者の皆さんに入っていただく。皆さんといっても、そんなに多いわけではなくて5~6人です。その方たちを子育てが終わった世代の女性が世話をしていく。今までの生活に近いような環境で集団生活ができるということで、精神的にもとても落ちついて過ごせるのだそうです。そういう施設が増えるといいのかなと思いますね。とくに都市部は人口が多いですから、雇用創出という面も含めて、できないことではないと思いますが。」と述べております(荻野美恵子 他:座談会・非専門医がどのように認知症に向き合ったらよいか? 内科 Vol.109 847-860 2012)。
2011年8月20日の朝日新聞・生活では、高齢者、障害者、子育て世代が共に支え合い暮らす現代版「長屋」(広島県東広島市)がコミュニティー再生の一つの手段になるのではないかと紹介されていましたね。
この現代版「長屋」とも比喩された「C-CORE東広島」(http://communitysystem.web.fc2.com/works/work1-building.html)は2011年3月にオープンした5階建ての賃貸マンションです。このマンションの1階には、子どもの居場所づくりをするボランティアの事務所や、地域住民の要望を受け開設された、障害者の就労支援を目的に気軽に集えるカフェもあるそうです。
『ひょっとして認知症? Part1』の第181回『認知症を生きるということ(その5)』においても、「幼老統合ケア」を実施している「ベルタウン」をご紹介し、「地域包括ケア研究会報告書」において提言された「おおむね30分以内の生活圏域で、生活上の安全・安心・健康が24時間365日確保できる地域のサービス体系の構築」に先進的に取り組んだ斬新なシステムと言えるのではないかと私は述べました。大阪府堺市の複合型福祉施設「ベルタウン」は、一階が通所リハビリテーションと通所介護サービスなど、二階が保育園ベルキンダー、三~四階が介護老人保健施設ベルアルト、五~七階が特別養護老人ホームベルライブで、建物自体を一つのタウン(街)と捉えていましたね。
一つのタウンとして捉えつつも、各階ごとに一定のしきりがあれば、多世代共生において大きな支障も生じないのかも知れませんね。しかしながら垣根が低ければ、有料老人ホーム「アクラスタウン」での様子を綴っている今村美都さんが報告されておりますように、「私たち親子が実際に住んでみての率直な感想は、ハード面でもソフト面でも老人ホームに一般の人間が住むのはまだまだハードルが高い」という状況がどうしても生じてしまうのでしょうね。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第71回『幼老統合ケア 認知症の元教育ママが大活躍』(2013年3月4日公開)
三重県桑名市において取り組まれている託老所と隣接する保育園が共有のスペースを作り、高齢者と子どもが触れ合う活動の様子は、「認知症フォーラム.com」の動画サイトにおいて閲覧できます。
三重県桑名市にあるウエルネス医療クリニック(http://wellness-medicalclinic.jp/)の多湖光宗院長は、認知症高齢者の役割づくりの具体例として、認知症高齢者の行動障害を逆に活用する試みを紹介しています(苛原 実・編著:認知症の方の在宅医療 南山堂発行, 東京, 2010, pp165-171)。
「『しつけ』の語源は『しつづける』である。認知症高齢者の行動障害の『繰り返し』が役立つ。普通の大人なら1回か2回でイヤになったりあきらめたりすることを何回もしつこくする。『何回も教える。何回もしかる。何回もほめる』、それも本気でする。この能力を生かすべきだ。以前学童保育『パンの木』の子どもたちを『宿題は無理。学習障害児の集まり』と元教員の指導員らは見放していた。また、『宿題しないのも個性のうち』と親や子どもたちには体裁を繕っていた。認知症の元教育ママたちは、宿題するのは子どもの義務で当たり前と思っており、①騒いでいる子を『本気でしかり』机に座らせる、②机に座って落ち着くまで見守る、③できているかチェックして、できていればほめる、このことを繰り返し行い、子どもたちの宿題習慣をつけるのに大きな貢献をした。なお、子どもはこの繰り返しを通常平気で楽しめる。また十分な時間もお互いにある。」
ウエルネス医療クリニックの試みは、幼老統合ケアの実践例として「高齢者住宅新聞」(http://www.koureisha-jutaku.com/news2011/news_110805002.html)でも紹介されています。
多湖光宗院長らは2001年より学童保育を併設するグループホームを設立しており、「認知障害の『トンチンカンさ』が癒しとなり、引きこもりのケア、非行少年の更生などに役立つこともわかってきた。『ひかりの里』でも荒れた子どもが素直になっていくことが体験された。」と報告しています(多湖光宗:能力活用セラピー. 日本臨牀 Vol.69 Suppl10 126-130 2011)。
また多湖光宗院長は、更正だけではなく「青少年の育成」にも有用であると指摘しています。
「見て見ぬふりをし、あとで陰口を言う大人の中では子どもたちはうまく育たない。喜怒哀楽が素直で、本気で怒り、心から喜んだり悲しんだりする認知症高齢者たちこそ、子どもたちが表情を読みとる訓練に必要な存在だ。全員から悲しまれるとこれはいけないことと思うし、1人のおばあちゃんからしかられて、ほかは『まあいい』という場合には、あのおばあちゃんに気を付けようと判断するようになり、社会性が身につく。」(多湖光宗:認知症の人の底力を地域に活かす. Dementia Japan Vol.26 28-35 2012)
パーソンセンタードケアを唱えたトム・キットウッドは、「認知症という病気は、神経障害、全身の健康、生活史、性格や個性、その人を取り巻く家族や地域社会という5つの因子によって形作られる」(水野 裕:DCMをめぐって. 老年精神医学雑誌 Vol.15 1384-1391 2004)と指摘しています。住み慣れた地域・住み慣れた家で少しでも長く過ごせるように、認知症の人を地域から支えていくシステムの構築が喫緊の課題となっております。
グループホーム「ふぁみりえ」ホーム長の大谷るみ子さんは、子ども目線から見た徘徊について紹介するなかで、認知症の人を地域で支えていくことの大切さについて語っています(大谷るみ子:人生の舞台は今、グループホームから地域へ─豊かな人生を支援する. 現代のエスプリ通巻507号 ぎょうせい発行, 東京, 2009, pp132-145)。そのご意見を紹介し本稿を閉じたいと思います(一部改変)。
「入居者のひとり、岩花さんは、もと小学校の校長先生。その仕事ぶりが表彰を受けられ、世界一周旅行をした方である。未だに世界一周旅行の話は輝きを放っている。定年退職後は民生委員の会長のお役目を務められ、自分でも放浪癖があったと言われるくらい校長の割には遊び心豊かな方だったようだ。奥さんを亡くされた後、徐々に認知症が目立ち始め、幾度となく放浪癖まがいの徘徊を繰り返され、次第に行方不明のために捜索願を出されることが増え、在宅生活の限界となり、平成十五年九月から入居されている。岩花さんのところには、毎日のように孫のさあやちゃんが通ってきた。ランドセル背負ってまずふぁみりえに『ただいま~』と帰って来る。…(中略)…この岩花さんの物語は、平成十五年度に大牟田市認知症ケア研究会が作成した絵本『いつだって心は生きている~大切なものを見つけよう~』の第三話のモデルとなっている。孫のさあやちゃんが、徘徊で行方不明になったおじいちゃんが、三日目にひょっこり家に帰ってきて『楽しかったあ』と言うのを聞いて、おじいちゃんの徘徊を冒険ととらえるという子どもの目線で描かれている。この絵本を通して、子どもたちに認知症の人の豊かな感情や力、子や孫を思う愛情、認知症でも大切な人ということを伝え、その子どもたちがまた大人や地域を変えてくれることを願っている。」
https://www.facebook.com/atsushi.kasama.9/videos/vb.100004790640447/645469438956072/?type=2&theater
佐伯美智子さんが「赤ちゃん先生プロジェクト」について熱く語ってくれました。
Yuutube動画は↓
https://youtu.be/fYDYvLdGCi4
ママハタは↓
https://www.mamahata.net/
取材の依頼先は、ママハタ・唐津の佐伯美智子さんです。
https://www.facebook.com/michiko.saiki?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all
P.S.
みっちゃんが運営する看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)『むく』(https://www.facebook.com/shoukibomuku/?pnref=lhc)は、2017年4月1日オープンです。

みっちゃんの長年の夢「幼老統合ケア」がいよいよ動き始めます。
みっちゃんの目標は、「あおいけあ」に追いつけ追い越せかな・・。
http://www.aoicare.com/
アピタル連載より
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第57回『幼老統合ケア 赤ん坊のぬいぐるみが効く』(2013年2月18日公開)
復習シリーズを続けてきましたが、年度が替わる前にお伝えしておきたい話題がありますので、いったん復習シリーズをお休みします。
『ひょっとして認知症? Part1』の第158回『高齢者に対する虐待とストレス』において、音とリズムさんから「思いやりの気持ちや態度を養うカリキュラムを幼稚園の時から実施」という提起がありました。
その際私は、「『幼老統合ケア』という試みを実践している施設があります。私も本で読んだだけの知識しか持ち合わせておらず実際の現場は見ていないのですが・・。いずれ『ひょっとして認知症?』においてご紹介します。」とお返事しました。
今回は、「幼老統合ケア」に関連した話題をいくつかご紹介します。
認知症高齢者においては、赤ん坊のぬいぐるみをとっても大切そうに抱きかかえている状況がしばしば見受けられます。認知症の人が怒ったりした際に、ぬいぐるみを渡すと落ち着きを取り戻すこともあります。このような方に対しては、「幼老統合ケア」が向いているのではないかと私は考えています。
認知症ケアにおいて非常に大きな問題である「認知症の行動・心理症状」(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia;BPSD)に対して、赤ちゃんの人形の子守りするという「役割」を担ってもらうことにより、BPSDが軽快した事例が報告されておりますので一部改変して以下にご紹介しましょう(髙尾千香子、上城憲司、岩谷清一 他:人形介在介入によって役割を獲得し、BPSDが減少した事例. 認知症ケア事例ジャーナル Vol.5 258-265 2012)。
「人形介在介入後の変化点を以下に述べる。
①徘徊
ロビーで人形と一緒に過ごすことが多くなりほぼ消失した。
②ゆがんだ解釈
以前は入浴やトイレ動作を促すことに労力と時間をかけていたが、『赤ちゃんのために、お母さんもお風呂に入りましょうか』『赤ちゃんと一緒にトイレに行きませんか』などと声かけをすると、拒否なく導入できるようになった。
③もの隠し・収集癖
②のような声かけを行うことで、自室の床頭台の中やシルバーカーの中に入れた、汚れた尿取りパットを嫌がらず処理させてくれるようになった。
④無意味な作業
徘徊がなくなったことで、他の患者の部屋に入って物を触ることはなくなった。
⑤対人トラブル
毎晩共有スペースで寝てしまうことにより発生していたが、自室ベッドで『赤ちゃんと添い寝してもらえますか』と促すと、起床時間まで眠ることができるようになったため、ほとんどみられなくなった。
⑥介入前の不潔行為
尿意不良で失禁していることが多く、紙パンツ交換の拒否も多かった。また、自らトイレに行き尿取りパットを便器に流して詰まらせてしまうことや、自分で片付けようとして汚してしまう場面もたびたびみられた。
介入後は、前述のように徘徊や拒否が少なくなったため、時間誘導がスムーズに進み失禁も減った。」
この事例においては、スタッフが人形について、「こちらの方とはどのようなご関係ですか」と質問したところ、「家族よ」とはっきりと答えたそうです。
認知症を患った高齢女性にドールセラピーを行うと、子育てという「役割」の賦与による効果なのかBPSDが顕著に改善することはしばしば経験されます。特に、人形を自分の子どもであると誤認するようなケースにおいては、ドールセラピーは著効する可能性があるのかも知れませんね。
Facebookコメント
理学療法士の三好春樹さんが『認知症介護─現場からの見方と関わり方(雲母書房)』という本を2014年5月15日に出版されました。この本は2003年に『痴呆論』として世に出され、その後、「認知症」という呼称が広がりつつあった2009年にあえて『痴呆論』のままで<増補版>として刊行されたものを、新たな題と本文中の「痴呆」の「認知症」への書き換え、および巻頭への新たな章の書きおろしを加えて、改訂新刊として刊行されたものです。
私は、『痴呆論』は読んだことがありませんが『認知症介護─現場からの見方と関わり方』を読みました。その中に「役割」の賦与を応用した非常に印象深いケア方法が記載してありましたので以下にご紹介したいと思います。
「子ども」になって泣いてみる
「介護アドバイザーの青山幸広に、彼がアドバイザーをしているグループホームのスタッフから電話がかかってくる。『どうしても家に帰ると言ってきかないんです。いろいろやってみたんだけど、今日だけは効果がありません。どうしたらいいでしょう』と。グループホームの夜勤は1人だけだから、いっしょに散歩してくるわけにもいかず、電話の向こうで弱り切っている。
『泣け!』と青山幸広。『えっ?』と受話器の向こうで驚いている声が聞こえる。『しやがみこんで、えーん、えーんと大げさに泣いてみろ!』。
果たして、『帰る』と言い張っていた認知症の入所者は、驚いて『泣かなくてもいいよ、どうしたんだい』とやさしく声をかけてきたという。母親になっているのだ。家に帰らなくても、目の前に自分の役割が現われたのである。
青山と同じく介護アドバイザーをしている高口光子も、やはりこの手を使う。困り果てると、突然子どものように泣き出すのだ。困らせていた老人が彼女をあやし始め、すっかり母親のようになってしまったら、『なんちゃって』と泣くのを止める。すると老人は、その展開にはついていけず、どうしていいかわからなくなるという。そこで、みんなで『バンザイ』を三唱する。すると、最初の問題が何だかわからないままお開きになって、老人は部屋に帰っていくという。ここまでくると、介護を知らない人にはまるでシュールな世界に見えるに違いない。
家族が誘っても風呂に入りたがらない女性がいた。他人のほうがいいのでは、とヘルパーが週に2回訪問して、家の風呂に誘うことになった。しかし、説得すればするほど拒否が強くなり、家族は『これならヘルパーに来てもらわなくても』と言い始めた。
困ったヘルパーはある日、子どもになってみることにした。子どもが小さかったころの話を、喜んですることに気づいたからだ。『お風呂に入りたいんですけど、一人じゃ入れないんで、いっしょに入ってもらえませんでしょうか』と言うと、『困った子だねえ』と言って、脱衣室に行って自ら服を脱いだという。それ以降、ほぼ毎回、この方法で成功している。」(三好春樹:認知症介護─現場からの見方と関わり方 雲母書房, 東京, 2014, pp156-158)
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第58回『幼老統合ケア 子どもの顔を見たとたんに笑顔』(2013年2月19日公開)
信濃毎日新聞の飯島裕一編集委員と佐古泰司文化部記者が書かれた著書(認知症の正体 PHP研究所発行, 2011, pp257-262)においては、認知症のお年寄りが暮らすグループホームに、学童保育の子どもたちが日常的に訪れて一緒に過ごす「幼老統合ケア」を実施している洛和グループホーム山科小山(京都市山科区)の取り組みが紹介されており、怒りっぽかった高齢者が子どもたちとの触れ合いを通じて笑顔を取り戻していく様子が報告されています。
『ルポ 認知症ケア最前線』(佐藤幹夫:岩波新書, 東京, 2011, pp52-76)においては、地域のなかにあって、障害者も高齢者も児童も受け入れてケアをする共生スタイルの「富山型デイサービス」について紹介されています。そして代表的な「富山型デイサービス」であるデイケアハウス「にぎやか」(阪井由佳子代表)の様子が詳細に報告されています。「にぎやか」は、富山市の新興住宅街の一角にあり外見は普通の民家です。「にぎやか」では基本的に見学は受けていないそうです。しかし、ボランティアとして一緒に活動してくれるのは構わないそうです。スタッフばかりか、お年寄りたちも入れ替わり立ち替わり赤ん坊に声をかけ、冗談を言い、笑い声が絶えない「にぎやか」の様子が紹介されています。
前述の著書『ルポ 認知症ケア最前線』第4章のタイトルは、「幼児たちの介護力」です。大阪府堺市の複合型福祉施設「ベルタウン」が取り上げられています。「ベルタウン」も「幼老統合ケア」を実践しています。「ベルタウン」内の特別養護老人ホーム「ベルライブ」の白川美保子施設長の言葉をご紹介しましょう。
「普段はまったく会話をしないお年寄りや、職員に話しかけられても芳しい反応が見られない認知症のお年寄りたちにあっても、子どもたちの顔を見たとたんに表情が一変する。なかには子どもたちに自分から話しかけるようになったり、ほとんど笑顔を見せない人が、ゼロ歳児がワゴン車に乗って遊びにやってきた姿を見るだけで、笑顔があふれたりする。」
このように、子どもたちの存在は、認知症の人(メモ1参照)に笑顔をもたらしたのです。
メモ1:認知症の人
医療法人社団こだま会こだまクリニックの木之下徹院長は、「イギリスの医療やケアの国家的ガイドラインには、『OUTPATIENTS(外来患者)』『INPATIENTS(入院患者)』などの例外を除き、『PATIENTS(患者)』が削除されている。またオーストラリアの『アルツハイマーズ オーストラリア』という組織では、この点においてはもっと先進的に、用語の規定集についても公表されている。また同国の認知症関連の医学論文でも、『患者』という言葉が『人』になっている」ことを紹介しています(医師へフィードバックすべき情報. 薬局 Vol.61 3641-3645 2010)。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第59回『幼老統合ケア 子どもたちも元気になる』(2013年2月20日公開)
笑う頻度と認知機能低下との関連を調べた研究があります(大平哲也:笑い・ユーモア療法による認知症の予防と改善. 老年精神医学雑誌 Vol.22 32-38 2011)。
笑いの頻度が少ないと認知機能低下が有意に高いことが報告されています。「幼老統合ケア」の意義はこんなところにあるのかも知れませんね。
さらに、「幼老統合ケア」においては、子どもたちがエンパワーメントされるという可能性も秘めています。
『認知症ケアは地域革命!』という著書の第三章「子どもたちと育んだマインド」(牧坂秀敏:現代書館, 東京, 2010, pp144-181)では、認知症高齢者との触れ合いを通して成長していく子どもたちの様子が描かれています。
2007年の夏休みに、認知症対応型デイサービス「地域福祉館・藤井さん家」を二人の小学生が「ボランティア体験」として訪れます。
高齢者は子どもたちとの触れ合いによって、子どもの名前を覚えたり、明るくなったり、動きが良くなったりしていきます。
子どもたちは、藤井さん家の人たちと、ゆったりした空間でゆっくりとした時間を過ごすなかで、心が満たされていき優しくなっていきます。
ある先生はそんな子どもたちの様子を以下のように考察したそうです。
「藤井さん家は、学校と異なり時間がゆっくり流れている。だから、学校で救われない子どもが藤井さん家で救われるだろう」と。
人権を守ろうとする「藤井さん家」の文化に子どもたちが出会うことで、子どもたちがエンパワーメントされたのです。
第三章は以下の言葉で締めくくられています。
「ここでいうエンパワーメントとは、だれでもが潜在的にもっている力や個性をいきいきと発揮することである。それは、人と人との間にいきいきとした出会い、関係があってはじめて可能となる。」
日本社会事業大学大学院福祉マネジメント研究科の今井幸充教授は、「判断能力を失った者の支援活動では、一方的な情報提供や助言をするのではなく、彼らが自立し、自ら問題を解決していくパワーを発揮できる能力を高める方向に導くことが重要で、このような支援行為をエンパワメント(エンパワーメント)という。このエンパワメント実践に重要なことは、認知症患者やその家族の自己決定権を擁護(権利擁護)、すなわち、アドボカシー(advocacy)であり、患者アドボカシーとは『患者の味方になってその利益・権利のために闘うこと』である。」と述べています(今井幸充:認知症患者に薬物療法を始める際の病名告知について. 治療 Vol.93 1830-1834 2011)。
特定非営利活動法人宮城福祉オンブズネット「エール」理事の内田幸雄さんは、「『おせっかい』という言葉がある。必ずしもよい表現として使われない言葉である。しかし、地域における高齢者の権利擁護を推進するには、この『おせっかい』という視点が重要であると考える。隣近所に対して地域がまったく『無関心』になったとき、そこでは社会的弱者に対する権利擁護の視点が失われることになるからである。」(内田幸雄:地域における権利擁護. 日本認知症ケア学会誌 Vol.10 440-446 2012)と指摘しています。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第60回『幼老統合ケア 子どもとの交流で変わる』(2013年2月21日公開)
さて、グループホーム「ふぁみりえ」ホーム長の大谷るみ子さんは、運営推進会議(メモ2参照)の場で、認知症の人と子どもたちを交流させてみてはどうかという意見が出された経緯を以下のように紹介しています(大谷るみ子:人生の舞台は今、グループホームから地域へ─豊かな人生を支援する. 現代のエスプリ通巻507号 ぎょうせい発行, 東京, 2009, pp132-145)。
「ハツミさんは、入居してしばらく『私はどうしてここにおるとね?』『まだ自分で暮らせる自信があるのに』と繰り返されていた。娘さんともあらためて本人への向き合い方を相談し、『ものわすれによって一人で暮らすことが難しいことが増えたこと』『おかあさんが一人だと心配でたまらない、ここは家からも近く安心して住めるところなので、ここでおかあさんに暮らしてほしい』と伝えることになった。『そんなこと言われても』と最初は少し寂しそうにされていたが、その後『私はどうしてここに?』という質問は少なくなられた。
それからしばらくして、『私は職安に行きたい』とハツミさん。『働きたい』『託児所もしたい』と。そこでそんなハツミさんの希望を、『運営推進会議』の場で話し合うことにした。『託児所はすぐにはできないけど、孫を連れて遊びに来ますよ』と委員の小野さん。『近くの幼稚園の子どもたちと交流してみては』などの意見が出た。近くの保育園に時々通ったり、月に一回『ママ&赤ちゃんの会』をすることになった。また月に二回、敷地内に開設した地域交流センターを活用し、ハツミさんを中心として『ささやかカレーの店』をすることになった。メニューきめ、買物、料理、会場セッティング、食券販売、給仕、おもてなしなど、入居者の皆さんが役割を分担され、職員も一緒にやり始めて二年目である。」
メモ2:運営推進会議
2006年(平成18年)4月の介護保険法改正により、グループホーム(制度上の正式名称:認知症対応型共同生活介護)が地域密着型サービスの1つに位置づけられました。同時に、地域住民を交えてグループホームの運営課題や地域交流を進める鍵として、「運営推進会議」の設置・運営が義務付けられました。民生委員、自治会長、消防団、行政や地域包括支援センターなど、さまざまな顔ぶれの会議です。認知症の人に対する理解を深め、地域全体で支え合うための地域づくりとして、またグループホームの中だけで支えるのではなく、入居者の暮らし方や支援の実際・課題などを取り上げ協議したり、何より本人の希望を聴き、本人・家族、施設と地域住民の交流の場としても意義深い制度です。
厚生労働省は2012年6月18日に、「認知症施策の方向性」(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/dementia/dl/houkousei-02.pdf)について提示しました。独立行政法人国立長寿医療研究センター脳機能診療部第二脳機能診療科の武田章敬医長はこれに関連して、「『今後の認知症施策の方向性について』報告書においては、認知症グループホーム事業所が地域の認知症ケアの拠点としての活動を行うことが求められ、具体的には認知症対応型通所介護やショートステイといったサービスの提供や、在宅で生活する認知症の人や家族への相談や支援を行うとされている。」(武田章敬:わが国の認知症施策. 月刊薬事 Vol.54 1596-1600 2012)と報告しております。
認知症グループホームにおける運営推進会議の実態に関する調査結果もウェブサイト上にて公開(http://ghkyo.or.jp/home/pdf/chousakenkyuujigyouhoukoku-20100520.pdf)されておりますのでご参照下さい。
Facebookコメント
「幼老統合ケアは、大牟田の大谷るみ子さんたちによって始められ、全国に広がりを見せている。認知症の問題解決を早めるためにも、小学生の頃から認知症を意識させることには意義がある。」(中村重信:私たちは認知症にどう立ち向かっていけばよいのだろうか. 南山堂, 東京, 2013, p221)
Facebookコメント
「サロンづくり」とひと言で言ってしまえば簡単なことのように感じられるかも知れませんが、立ち上げの大変さ&維持することの大変さ…など並々ならぬ努力が求められます。
そんな大変さを垣間見ることができる論文がありますので、抜粋して以下にご紹介しましょう(有馬みき、青木明美:地域住民と協働したサロンづくりとその活動─過疎高齢化の小さな田舎町「A町」の将来をになう人材が生まれることを願って. 認知症ケア事例ジャーナル Vol.6 253-262 2013)。
【論文抄録】
A町は、深刻な少子高齢化、過疎化、就労の場の減少など、多くの問題を抱えている。そこでB認知症対応型通所介護(Bデイサービス)では、施設内だけでなくA町の問題点にも向き合い、将来を見据えた活動を行う必要があると考え、制度にはない資源づくりを住民と協働して行った。本事例報告では、その過程を紹介するとともに、その活動の場が、将来をになう次世代の人づくりの場になることを目指して行われている取り組みについて報告する。
【論文本文】
はじめに
A町の人口は約24,500人、年少人口(14歳以下の人口)は約2,400人、高齢化率は約34%である(200X年12月時点)。人口の推移予測は、2035年には人口が約13,500人、年少人口は約950人へと減少し、高齢化率は50%を超える見込みであり、深刻な過疎、少子高齢化の問題を抱えている。また、農業や水産業が低迷し、新規採用を行っている地元企業はほとんどない状況で、就労の場が大幅に減少しているため、高校を卒業する時点でA町外へ就職、進学する若者がほとんどである。
サロンのオープンから地域へのよびかけ;小学生にどう声をかけたか
200X-1年4月にサロンをオープンし、回覧板や広報で周知を促した。また、いっしょに立ち上げてきた住民に、精力的に口コミで宣伝をしてもらうように頼んだ。しかし、お茶のみ場やギャラリーでの利用を中心に交流が始まったということもへあり、比較的年齢が高い人たちの利用は増えても、目的としていた子どもたちには思うように利用してもらえなかった。
職員は、どうすれば「子どもたちが保護者や先生に見守られながらも、ルールに縛られず楽しくすごせ、かつ、世代間交流ができるようなサロン」になるかについて考えた結果、「宿題をする場所」としてサロンを提僕することを思いついた。そして、200X-1年7月に「夏休みにお友だちとサロンで宿題をしませんか?」とよびかけるチラシを作成して、小学生に配布した。小学生が堅苦しく感じず、来るのが楽しみになるように、かき氷を自由につくれることや、あめや飲み物を無料で提供することをチラシに盛り込んだ。そうすると、それまでの状況がうそのように小学生が集まり始め、宿題をするだけでなく、いつの間にかルールを守りながらも通信型のゲームやカードバトルゲームをしたり、さまざまな楽しみ方をしたりするようになった(図)。そのことが、より多くの子どもたちが集まるきっかけになっていった。
サロンとBデイサービスの位置関係にこだわった理由
そして、サロンは「場所」のみでは成り立たず、「人」が重要であると考えた。
職員が、Bデイサービスをオープンな空間にして、サロンからだれもがいつでも入って来やすい雰囲気づくりを行ったところ、徐々に小学生が「Bデイサービスではなにをしているのだろう」と興味をもち始めたようであった。そこで、「高齢者がレクリエーションを楽しむために人手が足りないから手を貸して」と小学生に伝えると、恥ずかしそうにしながらも、レクリエーションに参加してくれるようになった。最初は恐る恐る入ってきていた小学生が、いつの間にか慣れて、自然と高齢者や職員と交流を深めることができるようになった。
考察・課題
当初は小学生の利用はなく、子どもが高齢者とかかわることをいやがっているのではないかとさえ思っていた。しかし、環境の提供ときっかけづくりをていねいに行うことで小学生自身が自ら考え、行動し、日常的に交流を楽しむことができることが分かった。好奇心旺盛な小学生が、自分の力で新たな人や場所とつながることに楽しさや喜びを感じたことで、Bデイサービスやサロンに訪れる頻度が多くなり、職員だけでなく、高齢者にも興味をもち始めたと考える。その姿に職員は勇気づけられ、高齢者が元気になることも再確認した。
当初、Bデイサービスやサロンでは、福祉をになう人材づくりしかできないと考えていた。しかし、認知症の人は、福祉サービスのみで支えられるはずもなく、町のなかのさまざまな人に支えられ、はじめて安心して生活することができる。将来、小学生たちが福祉の仕事に携わらなくても、地域の生活のなかで重要な役割を果たしていくに違いない。サロンの活動を通じて、大人だけでなく、小学生のときから「人は年老いて死んでいくこと」を身近に感じてもらうことは「認知症になっても安心して暮らせる町づくり」に直結する。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第61回『幼老統合ケア 住み慣れた地域で密着型サービスの模索』(2013年2月22日公開)
認知症グループホームについてご紹介しましたので、小規模多機能型居宅介護についてもお話しておきましょう。
厚生労働省は、「地域密着・小規模化」を掲げ、在宅療養への移行を推進しています。しかしながら、特別養護老人ホームの入所申込者は42.1万人もいることが報告されており(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003byd.html)、現状では施設志向が依然として強いのが現状です。それは、在宅療養においては、介護サービスを受けている時間を除く大半の時間、介護者が介護に携わる必要があり、主たる介護者の精神的な負担が強いことが大きな要因として挙げられています。
2006年(平成18年)4月の介護保険制度改正により、今後増加が見込まれる認知症高齢者が、できる限り住み慣れた地域での生活が継続できるように、新たなサービス体系として地域密着型サービスが創設されました。
「地域密着型サービス」に属するサービスの中で、小規模多機能型居宅介護は、「通い(デイサービス)」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問(訪問介護)」や「泊まり(ショートステイ)」を組み合わせてサービスを提供します。「通い」「訪問」「泊まり」の3つの機能を兼ね備えた小規模多機能型居宅介護は、自宅を拠点として生活したいと願う人にとって使い勝手のよいサービスとして注目されております。
このサービスが創設される前は、「通い」、「訪問」と「泊まり」などの介護サービスをそれぞれ別の施設で受けることにより、それぞれの場面で利用者に対応するスタッフが異なるために馴染みの関係やケアの連続性が保たれないといった問題がありました。
小規模多機能型居宅介護が主に担っている役割は、中等度・重度となっても在宅での生活が継続できるように支援することです。
小規模多機能型居宅介護には利用定員が定められており、1つの事業所あたり25人以下の登録制となっています。1日に利用できる通所サービスの定員は15人以下、泊まりは9人以下となっています。
小規模多機能型居宅介護の「泊まり」機能の充実が今後ますます期待されていくように思われますね。
Facebookコメント
特養入居待ち―参入拡大に知恵を絞れ【2014年4月5日付朝日新聞・社説】
「住み慣れた自宅で暮らせる在宅介護は望ましい。ただ、施設の役割も大きい。今後の高齢化を考えれば、施設運営への参入規制を見直し、特に都市部での供給を増やすべきだ。
特別養護老人ホーム(特養)への『入居待ち』が約52万人にのぼり、4年前の前回調査より10万人増えたことが厚生労働省の集計でわかった。
特養は、比較的安い費用で介護を含めた生活の面倒をみてくれる。市町村が施設を割り当てていた時代と違い、介護保険のもとで入居の申し込みは自由にできる。
政府は『地域包括ケア』という考え方のもと、自宅で最後まで暮らすことを目標に、在宅介護を推進する。
52万人のなかには、今は必要ないが将来への不安からとりあえず申し込んだ高齢者もいる。そうした人ができるだけ長く自宅で過ごせるよう、サービスを充実させることは大切だ。
ただ、それには時間がかかるし、地域によってばらつきもある。『在宅重視』のかけ声だけでは、暮らしが行き詰まるお年寄りに対応しきれない。頼れる家族が近くにおらず、地域とのつながりも薄い高齢者は、特に首都圏で急増する。
地価が高く施設が足りないため、こうした高齢者を抱えきれず地方に送り込もうとする動きが強まる懸念もある。
都市部を中心に、特養の整備を進めていくべきだ。
それには、地方自治体が施設の増加による財政負担の拡大を恐れて設けている総量規制を見直すとともに、参入規制を緩めていく必要がある。
現在、特養をつくれるのは、地方公共団体のほかは、社会福祉法人に限られる。低所得の人にも『終のすみか』を提供する公益性が理由とされる。
だが、介護保険のもと、契約に基づき特養のサービスを提供して報酬を受け取るだけなら、運営を社会福祉法人に限定する理由はない。
多様な事業者が参入すれば、都市部でネックになっている土地の確保や資金調達でも新たな知恵が出てくる可能性がある。競争を通じたサービスの質の向上も期待できる。
人員配置など入居者保護の規制は緩めるべきではない。営利法人から『これではもうからない』と緩和を要求されて介護の質を落とせば、『うば捨て山』をつくるだけだ。
在宅介護で暮らしを支えつつも、『最後のとりで』として特養がある。そんな地域づくりが現実的なのではないか。」
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第62回『幼老統合ケア 期待される小規模多機能型居宅介護』(2013年2月23日公開)
小規模多機能型居宅介護は非常に期待されているサービスなのですが、事業者側からみると制度上の問題点もあるようです。
高齢者総合ケアセンターこぶし園の小山剛総合施設長は、「本制度の利点は通い・泊まり・訪問に対応するばかりではなく、それまでの介護保険3施設と認知症対応型共同生活介護のように1か月の利用額を定額にしたことで、利用回数に一律的な制限を受けないことから、そのときの必要量に合わせた柔軟な使い方ができることにある。ただし介護報酬の設定は重症度が中等度~重度用に設計されているため、軽度の認知症の段階から連続的な使用が行われると事業者の負担が増加するというジレンマも内在している。」と指摘しています(小山 剛:福祉施設ケアと精神科入院治療の現状と課題. 老年精神医学雑誌 Vol.23 572-577 2012)。
介護保険三施設とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム;特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設の3施設を指します。
小規模多機能型居宅介護の利用料金例は、NAGOYAかいごネットのウェブサイトをご参照下さい。この表を見ても分かりますように、要介護2以下と要介護3以上では報酬単位にかなりの開きがありますから、認知症患者さんが早い段階から連続的に利用していくには、事業者側に資金的な余力がないとサービス利用が困難という状況になってしまいますね。
小規模多機能型居宅介護の利用料金をNAGOYAかいごネットのウェブサイトで見てみますと、要介護5では28,120単位と記載されておりますね。すなわち、2万8120円(1割の自己負担分)を基本料金として、それ以外に、食事代・宿泊費(首都圏で一泊三千円前後)・おむつ代などが別途かかることになるわけです(2012年10月28日発行週刊ダイヤモンド臨時増刊・通巻4454号 p9)。
2012年10月28日発行の週刊ダイヤモンド臨時増刊・通巻4454号では、情報公開に積極的な1721ホームから回答を得て、「有料老人ホーム ベストランキング」を特集しており、8つの指標から評価し、31都道府県にある介護付き有料老人ホームを合計得点(100点満点)の高い順に紹介しております。たいへん興味深い資料だと思います。
なお、2012年10月28日発行の週刊ダイヤモンド臨時増刊(通巻4454号)においては、小規模多機能型居宅介護の特徴が分かりやすくまとめられておりますので抜粋してご紹介しましょう(一部改変)。
「小規模多機能型居宅介護は、かつては『宅老所』といわれた仕組みを2006年度から制度化したものだ。通所事業所に通い、食事や入浴、機能訓練などを受ける『デイサービス(通所介護)』、施設に短期間宿泊して、食事や入浴などの生活介護を受ける『ショートステイ(短期入所)』、これに訪問介護を加えた三つのサービスを提供する事業所だ。2012年4月からはこれに訪問看護を加え、四つの機能が一体化した『複合サービス』が新たに始まった。医療的な措置を必要とする要介護者を抱える家族にとっては、朗報といえよう。
使う際は、まず、自宅近くの小規模多機能型居宅介護の事業者に登録する。その上で、必要に応じて上記四つのサービスを利用する。
例えば、共働き世帯の方で、急な残業などで帰りが遅くなっても、職員が自宅に利用者を迎えに行って、(小規模多機能施設に)宿泊させることができる。柔軟性のあるサービスのために、家族からは喜ばれることが多い。
いずれも要介護度に応じた定額料金となっている。どれだけ介護サービスを受けても、出来高払いと違い支払額が大きく膨らむ心配はないから安心して利用できる“懐”に優しいサービスといえる。
小規模多機能型居宅介護を利用する場合、介護保険のルール上、サービス内容が重複する他の介護サービス(デイサービス、ショートステイ、訪問介護)と併用はできないので注意が必要だ。
このため、デイサービスの単独利用から、小規模多機能型居宅介護に変えようと思っても、デイサービスのケアマネジャーが、顧客を手放すことを嫌って承諾しないことがある。利用者本人もデイサービスに親しい職員や仲間がいると、離れるのを嫌がって拒むという事態がしばしば発生する。
また、小規模多機能型居宅介護の事業者は、デイサービス、ショートステイ、訪問介護の三つ(訪問看護を含めると四つ)を等しくこなせることが原則だが、人手不足の地域や住宅が分散している地域では訪問介護が十分に行えない事業者も少なくない。
中には意図的に、経営面で効率的なデイサービスやショートステイだけしかやらない事業者もいるから注意したい。」(2012年10月28日発行週刊ダイヤモンド臨時増刊・通巻4454号 pp24-25)
さて、実際にはどのようにして小規模多機能型居宅介護の施設を探せばよいのでしょうか。
「かいごDB」のウェブサイト(http://kaigodb.com/)におきましては、小規模多機能型居宅介護を実施している施設を都道府県別に閲覧できますのでご参照下さい(http://kaigodb.com/kaigo_service/200/)。施設数が少ないのがネックとなっており、なかなか該当施設が見つけられないのが現状ではないでしょうか。なお、地域密着型サービスは、市区町村が施設事業者を指定しており、原則として事業所所在地に居住する被保険者のみが利用できるサービスです。
Facebookコメント
「小規模多機能型居宅介護を利用する場合、介護保険のルール上、サービス内容が重複する他の介護サービス(デイサービス、ショートステイ、訪問介護)と併用はできないので注意が必要だ。」と記載しておりますが、2013年12月17日付中日新聞に「複合型サービス」に関する記事がありましたので以下にご紹介しましょう。
看護や介護で在宅支える・「複合型」じわり普及─医療行為OK、みとりも対応
小規模多機能型居宅介護サービスに、看護機能を強化した「複合型サービス」が少しずつ増えている。看護師が多いので、退院直後の不安定な状況や終末期にも対応しやすいという。静岡市清水区にある施設「複合型ナーシングケアもも」での取り組みを紹介する。【佐橋 大】
清水区の住宅街にある施設「複合型ナーシングケアもも」。今年二月に「小規模多機能型居宅介護事業所」から転換した。高齢者約二十人が利用登録をしている。登録すれば「通い」「泊まり」「訪問介護」「訪問看護」の四サービスを、泊まりの実費負担などを除き、月単位の定額で受けられる。従来との違いは職員の四割(常勤換算)が看護師と、看護職員の割合が高い点だ。
運営会社の地域包括ケアサービス部長、高井由美子さんは「小規模多機能のときなら、ちゅうちょする人も受け入れられるようになった」と話す。例えば肺炎を繰り返し、しばしば抗生剤の点滴が必要になる人。規制のため、看護師が付き添っていても小規模多機能のサービスの中では、医療行為である点滴はできない。
医療機関に通えない人には、訪問看護のサービスで、看護師が自宅を訪れ、抗生剤を点滴するしかなかった。点滴は通常二時間以上かかるため、多忙な訪問看護で付き添うのは難しいという。複合型サービスでは、日中は看護師の常駐を義務付ける代わりに、医師の指示を受けて、点滴などの医療行為ができるようになった。
定額で訪問看護
複合型サービスは2012年四月の介護保険法の改正で、医療依存度の高い人が、地域で暮らし続けるのを支えるために導入。定員は最大二十五人。グループホームや小規模多機能型と同様、利用者は事業所のある市町村の住民に限る。
小規模多機能型との違いは、訪問看護が定額サービスの中で受けられること。その分、小規模多機能型より月額の利用料が少し高い。例えば要介護3なら、本体部分の一割負担が、小規模多機能型の月二万三千円余に対し、複合型サービスは月二万五千円余り。
厚生労働省のまとめでは六月末現荏、全国で七十三事業所が指定を受けている。中部地方では名古屋市三、福井県坂井地区広域連合(あわら市、坂井市)二、静岡市一。その後、愛知県豊橋市でも事業所が指定を受けた。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第63回『幼老統合ケア 認知症初期集中支援チームへの期待』(2013年2月24日公開)
厚生労働省は2012年6月18日に、今後の認知症施策の方向性について提示しました。それに関して2012年6月19日の朝日新聞は、以下のように報道しております(一部改変)。
「厚生労働省は6月18日、高齢化で増える認知症の新たな対策をまとめた。専門職の支援チームが患者の自宅を訪問するなど、症状の初期段階で集中的に在宅での対応を支えるのが柱。症状が悪化して精神科病院に入院するのを防ぐねらいだ。来年度から実施する。
対策の柱は、地域介護の拠点である地域包括支援センター約4200カ所などに設置する『認知症初期集中支援チーム』。看護師や保健師、作業療法士らが本人や家族から生活状況を聞き取り、症状進行の見通しを説明するほか、生活全般についても助言する。
また、このチームやかかりつけ医と連携し、認知症の専門医が早期診断する『身近型認知症疾患医療センター』も医療機関に新設。専門医は一般病院や介護施設も訪問し、地域医療を後押しする。厚労省は今回の対策を具体化した5カ年計画をつくる方針だ。」
「認知症初期集中支援チーム」というあまり聞き慣れない名称が出てきましたね。その役割について、独立行政法人国立長寿医療研究センター脳機能診療部第二脳機能診療科の武田章敬医長が分かりやすく解説しておりますのでご紹介しましょう(一部改変)。
「『今後の認知症施策の方向性について』報告書において、早期診断・早期対応を促進する観点から、看護職員、作業療法士等の専門家からなる『認知症初期集中支援チーム』を地域包括支援センター等に配置し、認知症が疑われる人の家庭を訪問し、生活状況や認知機能等の情報収集や評価を行い、適切な診断へと結びつけ、本人・家族への支援を行うとしている。また、かかりつけ医の認知症対応能力が向上し、『認知症初期集中支援チーム』の取り組みが普及するまでの間は、主として『身近型認知症疾患医療センター』の医師が『認知症初期集中支援チーム』の一員として関与したり、ケアマネジャー及びかかりつけ医等に対する専門的なアドバイスを行ったりする役割を果たすとされている。」(武田章敬:わが国の認知症施策. 月刊薬事 Vol.54 1596-1600 2012)
なお、「身近型認知症疾患医療センター」は、5年間で全国300カ所に整備する予定だそうです。
厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室の勝又浜子氏は、医学雑誌社のインタビューの中で、「認知症初期集中支援チーム」における医師・ケアマネジャーの位置づけについて次のように述べております(一部改変)。
「認知症初期集中支援チームはイギリスの認知症施策である『メモリーサービス』がモデルになっています。
メンバーは、看護師や作業療法士等で、必ずしも医師は要件になっていません。チームがかかりつけ医と連携して初期支援を行なっていくことが想定されます。またイギリスでは、このチームにケアマネジャーは入っておらず、チームが関わったあとにケアマネジャーが引き継ぐという仕組みです。日本ではどういうやり方がいいのか、2013年度からのモデル事業で模索していくことになります。必要に応じて医師が入ることもあるでしょうし、他にも精神保健福祉士や介護職、さまざまな職種がチームに入る可能性もあります。
もちろん『訪問看護師』もメンバーの有力な候補ですね。拠点は『地域包括支援センター等』となっていますが、市町村からの委託を受けた訪問看護ステーションを拠点に地域包括支援センターと連携しながら行なっていくかたちもありえます。」(認知症の「ケアの流れ」をどう変える?─これからの認知症施策の主眼と訪問看護の役割. 訪問看護と介護 Vol.18 16-20 2013)
訪問看護ステーションと地域包括支援センターが連携しながら取り組む試行例も紹介されておりますので以下にご紹介します(一部改変)。
「『認知症初期集中支援チーム』のモデル事業が、2013年度から始まる予定だ。これに先立ち、そのスキーム(概型)を検討する試行も、全国3か所で始まっている。そのうち1つは『訪問看護ステーション』を中核に地域包括支援センターと連携しての取り組みである。
その中心となっているのは、ナースケアステーション(東京都世田谷区)の片山所長だ。認知症初期集中支援チームのメンバーは今のところ、片山所長を中心とする4名の訪問看護スタッフと、ステーション外から作業療法士、連携する在宅療養支援診療所の総合内科医・精神科医である。すでに3事例の『初回アセスメント訪問』を行ない、近く『チーム員会議』を開催する予定だ(2012年12月5日現在)。
『初回アセスメント訪問』は初期集中支援計画の礎になるものであり、認知症の症状はもちろん、既往歴やその治療と服薬状況、身体状況などの『医療』の視点から、本人のパーソナリティや価値観、生活状況や生活障害、家族背景や経済状態などの『生活』の視点まで多岐にわたる。また居住環境など訪問しなければわからない項目も少なくない。片山所長は、このアセスメントを一度に2~3時間かけて行なっている。」(認知症の「ケアの流れ」をどう変える?─これからの認知症施策の主眼と訪問看護の役割. 訪問看護と介護 Vol.18 31 2013)
Facebookコメント
2014年6月9日放送クローズアップ現代「初期認知症と診断されたら… ~どうつくる支援体制~」(http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3510/)の主な放送内容を以下にご紹介しましょう。
1 日本の現状:
7年前に初期の認知症と診断された藤田和子さん(52歳)。
総合病院の脳神経内科にて、「アルツハイマー型認知症の疑い」があると告げられたものの、医師からは病名を告げられただけで症状や今後の見通しなど詳しい説明はなかった(by ナレーション)。
→放送を観ておりますと、診断の根拠としては脳血流検査が決め手の一つとなったようですが、SPECTの偽陽性率を考えますと、「現状では、軽度認知障害(MCI)と思われます。1年後に再診して診断を確認しましょう」という説明が妥当であったかな…と私は感じました。
その1年後、藤田さんは知人の紹介で認知症専門医の診察を受け(=映像を観ておりますと、その認知症専門医とは、鳥取大学医学部保健学科生体制御学の浦上克哉教授でした)、正式にアルツハイマー型認知症と診断を受け諸アドバイスを受けた。
しかし、治療は始まったものの、その後の生活を支援する体制がないことで藤田さんは苦悩を深めていきます(by ナレーション)。
認知症が初期の段階で分かっても、多くの人が不安を増幅させていると言われています(by ナレーション)。
2 認知症の初期集中支援チームは、昨年度よりモデル事業が開始されており、国は2017年度までにすべての市町村で整えようとしています。しかし現場では、初期の認知症の人をなかなか見つけられないという課題に直面しています(by ナレーション)。
3 イギリス・スコットランドの初期認知症への取り組み
認知症の人の「診断後すぐに医療の知識を持った支援者が欲しかった」という声を反映させた取り組みである「リンクワーカー」という仕組みが4年前から始まっている。
リンクワーカーは、地元のアルツハイマー協会から派遣される臨床心理士や看護師などが担い手。
診断を受け混乱しているヘンリー・ランキンさんを救ったのは、診断後まもなく自宅を訪れたリンクワーカーのトレイシー・ギルモアさんだった。
ギルモアさんがランキンさんに渡したのは、認知症の人たちの活動を収めた映像「私たちの目を通して(スコットランド認知症ワーキンググループ制作)」でした。
4 リンクワーカーは、「認知症カフェ」「当事者や家族の勉強会」を紹介するとともに、「年金・税金など優遇策の紹介」などの支援を1年間無料で提供します。
5 放送の番組のコメンテーターは、東京都健康長寿医療センター研究所の粟田主一部長でした。
粟田主一部長は、介護保険の課題として、「認知症の初期段階における『生活支援』を調節する役割(仕組み)を日本の中で何とか作り出していかないといけない」と述べるとともに、「現在、日本においてはケアマネが主にその役割を担っているが専門的な知識を持ち合わせていない場合もある。ケアマネ以外には、『認知症コーディネーター』とか『認知症地域支援推進員』という制度が作られつつある」と指摘されておりました。
P.S.
地域における医療と介護の連携の強化をはかるために、認知症地域支援推進員研修が開始されております。(平成23年以前は認知症連携担当者)認知症地域支援推進員研修は、「市町村認知症施策総合推進事業」を実施する市町村に配置された(もしくは配置予定の)認知症地域支援推進員が、医療機関や介護サービスおよび地域の支援機関をつなぐコーディネーターとしての役割を担える知識・技術を習得することが目的になります。
詳細は、厚生労働省のウェブサイト(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000133sr-att/2r98520000013459.pdf)をご覧下さい。
2012年度の受講者は263名が修了して、2年間で530名が修了しました(谷 規久子、本間 昭:病者と家族を支える社会的支援・地域連携. からだの科学通巻278号 128-136 2013)。
Facebookコメント
住み慣れた地域で豊かに暮らし続けるために認知症の初期支援を充実(2014年9月21日付朝日新聞・名古屋本社版17面─全面広告【名古屋市】)
認知症になっても住み慣れた地域で豊かな生活を過ごすためには、早期発見・早期対応が大切です。名古屋市は国の「認知症施策推進5か年計画」に基づき、平成26年度より「認知症初期集中支援チーム」を設置し、モデル事業を展開。医師、社会福祉士、看護師をチーム員として、初期支援の充実を目指しています。
対象者や家族を支援し自立サポートを行う
黒川(認知症初期集中支援チーム/医師 黒川医院院長・黒川豊さん):
認知症の問題が社会的に認識されるようになったのは、今から25年くらい前です。当時の認知症は発見されてからの余命は平均して4年。現在は約14年と、飛躍的に伸びています。近年になって、認知症の治療が早期発見・早期対応に変化していますが、初期段階から治療を始めることにより症状の進行を遅らせ、家族とよい時間を過ごすことができるようになると思います。
石川(名古屋市 健康福祉局 高齢福祉部 地域ケア推進課 地域支援係主事・石川隼さん):
黒川先生のお話のように昨今のケアの流れは、早期発見・早期対応へとシフトしています。厚生労働省が平成24年にまとめた今後の目指すべき基本目標において、早期発見により「認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けることのできる社会」の実現を目指しています。この実現のため、同年に認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)を策定。その柱となるのが「認知症初期集中支援チーム」です。名古屋市でも平成26年度より、千種区東部いきいき支援センターに支援チームを配置して、モデル事業をスタートさせました。
黒川(認知症初期集中支援チーム/医師 黒川医院院長・黒川豊さん):
今回のモデル事業の認知症初期集中支援チームは、医師、社会福祉士、看護師の3人で構成されています。認知症の人やその疑いのある人、その家族に早期から家庭訪問して関わりを持つ中で、症状の程度の確認や必要なアドバイスを行うことによって早期の診断や治療につなげ、対象者や家族を支援し、自立サポートを行うことを目的としています。
新村(認知症初期集中支援チーム/社会福祉士 名古屋市千種区東部いきいき支援センター・新村小枝子さん):
地域には認知症の疑いのある一人暮らしの高齢者もいらっしゃいますが、地域の民生委員や住民、ご家族から困っている人がいるという相談があり、私たちの活動が始まります。それぞれの分野の専門家が、違った視点からアプローチすることで、支援の内容も広がっていくと思います。
山岡(認知症初期集中支援チーム/看護師 名古屋市千種区東部いきいき支援センター・山岡美和子さん):
物忘れなどの認知症症状だけでなく、内側に隠れた低栄養や高血圧など、体の状態をお聞きしながら医師に相談をして、早期受診につなげることも私たちの役割のひとつだと思います。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第64回『幼老統合ケア 認知症300万人時代』(2013年2月25日公開)
認知症施策検討プロジェクトチームが2012年6月18日にとりまとめた「今後の認知症施策の方向性について」や、同年8月24日に公表した認知症高齢者数の将来推計などに基づいて、「認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)」が2012年9月に発表されました。
オレンジプランは、平成25年度から29年度(2013~2017年度)までの認知症施策の数値目標を示したものです。
オレンジプランの詳細は、厚生労働省のウェブサイト(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002j8dh-att/2r9852000002j8ey.pdf)にて閲覧可能です。
このpdfファイルの4頁には、認知症高齢者数の居場所別内訳が記載されております。認知症高齢者数は、305万人(2012年)から373万人(2017年)に増加すると推計されておりますが、医療機関における認知症高齢者数は38万人で変化がありません。すなわち、増加した分は、在宅介護(149万人→186万人)、居住系サービス(28万人→44万人)、介護施設(89万人→105万人)が受け皿になると想定されているわけです。
介護施設とは、介護老人福祉施設と介護老人保健施設等(介護療養型医療施設を含む)であり、このうち介護老人福祉施設を居場所とする認知症高齢者数は48万人から58万人に増加することが想定されております。
なお、介護療養型医療施設については2017年度末(平成30年3月末)に廃止予定となっております。しかしながら、2011年における介護療養型医療施設の平均在院日数は311日であり、5年前の269日から42日も延びており、入院の必要がない高齢者を病院から介護施設に移す政策が進んでおらず、介護療養型医療施設の廃止には程遠い状況にあることを2012年12月3日付日本経済新聞は1面トップニュースとして伝えております。
指定介護老人福祉施設とは、介護保険制度の施行により、老人福祉法による特別養護老人ホームが介護保険法の指定施設となったものです。すなわち、介護保険法に基づき、都道府県知事から指定を受けることにより「指定介護老人福祉施設」となり、介護保険による施設サービスの対象となります。介護施設の呼称・分類に関しては、ウィキペディア(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E)などをご参照下さい。
さて、介護老人福祉施設における10万人規模の受け皿増加は十分と言えるでしょうか? 2012年10月28日発行週刊ダイヤモンド臨時増刊が特別養護老人ホーム(特養)の待機者の現状を伝えておりますのでご紹介しましょう。
「『特別養護老人ホーム(特養)に入ることができれば、介護の負担は大幅に減るのだが…』
在宅介護が困難になった家族の声は悲痛だ。特養の待機者(申込者)は、全国で実に42万1259人で、定員の41万4668人をも上回る。受け皿を2倍に増やしても、収容し切れない勘定だ。
なかでも、首都圏の待機者は最大規模。東京都の4万3746人を筆頭に、1都3県で計9万7324人に達している。」(2012年10月28日発行週刊ダイヤモンド臨時増刊・通巻4454号 pp174-176)
このように、10万人規模で受け皿を増やしたとしても、現時点での特養待機者の1/4程度の解消にしかならないことは明白です。
では何故こんなにも特養の待機者が多いのでしょうか。
「特別養護老人ホーム(特養)に入ることができれば、介護の負担は大幅に減るのだが…」という言葉にもありますように、何と言ってもコストの安さが最大の特徴です。
2012年10月28日発行週刊ダイヤモンド臨時増刊によれば、特別養護老人ホームの月額利用料の目安は6万~15万円です。介護型老人保健施設(13~15万円)、サービス付き高齢者向け住宅(12~20万円)、グループホーム(13~20万円)、介護付き有料老人ホーム(15~35万円)に比べるとかなり低額です(2012年10月28日発行週刊ダイヤモンド臨時増刊・通巻4454号 p9)。
さらに、所得による負担軽減措置があるため、多床室タイプの特別養護老人ホームに入所する市町村民税非課税の方であれば、上記料金よりもさらに減額され、月額利用料が4~6万円程度となるケースもしばしばです。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第65回『幼老統合ケア 介護のために離職する人は5年で57万人』(2013年2月26日公開)
厚生労働省は、認知症患者が住み慣れた環境で暮らし続けられる社会の実現を今後の認知症施策の基本目標として提示しております。
具体例を挙げれば、「認知症初期集中支援チーム」を地域包括支援センター等に配置し、認知症が疑われる人の家庭を訪問し、生活状況や認知機能等の情報収集や評価を行い適切な診断へと結びつけ、本人・家族への支援を行い、在宅療養が少しでも長く継続できるようにと思案しております。
しかしながら、介護と仕事の両立は決して簡単なことではありません。2012年10月28日発行週刊ダイヤモンド臨時増刊において、フリーライターの西川敦子さんは「働く人の介護」という原稿を寄せております。抜粋して以下にご紹介します。
「晩婚化、非婚化が進み、シングルが急増。共働き家庭も増えている。その上、兄弟が少ない、となれば介護負担をもろに背負う確率は男女共に高くなる。
総務省の『就業構造基本調査』(2007年)によると、介護離職者は2002年10月からの5年間で56万8000人。離職後、無業の状態にある人は40万4000人に上る。『介護失業』は人ごとではない。危機はあなたの足元まで迫っているかもしれないのだ。
では、ある日突然、親が倒れたら、働く息子や娘はどう対応すべきなのだろうか。
思い付くのは、会社を長期間休み、介護できる態勢を整えることだが、東京大学大学院情報学環の佐藤博樹教授は『介護休業を利用し、自分で親を介護するのは極力避けるべき』と意外なアドバイスをする。
1999年に施行された『育児・介護休業法』で定められた介護休業。要介護状態にある家族1人につき通算93日間、仕事を休めることになっている。なお、その間、支給される『介護給付金』は休業前の貸金の40%だ。
だが、介護の平均期間は55.2カ月間(生命保険文化センター調べ)にも及ぶ。『3カ月間の介護休業を超えて、自ら介護を続けようとすれば、退職しか選択肢がないことになる』(佐藤氏)
6割減の収入でやりくりした揚げ句、失業。貯金も底を突き、やがて生活保護を受給する─、こんな最悪のシナリオはなんとしても避けたい。
『だからこそ介護はプロの手に任せるなどし、自らは介護サービスの調整役に徹してほしい』と佐藤氏は言う。
親が倒れたときは、真っ先に『介護と仕事を両立できる環境づくり』をするべきなのである。」(2012年10月28日発行週刊ダイヤモンド臨時増刊・通巻4454号 pp12-14)
そもそも、定年後に必要とされる生活資金3,000万円をこの不況の折りに準備できている家庭は稀な存在ではないでしょうか。「貯金も底を突き、やがて生活保護を受給」ということは、近年の日本社会の動向を見ておりますと、いとも簡単に起きてしまうことのように感じられます。
フィデリティ退職・投資教育研究所が2010年2月に実施した「サラリーマン1万人アンケート」を見ておりますと、老後難民予備軍の急増が懸念されます。その「サラリーマン1万人アンケート」の結果の一部をご紹介しましょう。
「現在の公的年金制度では安心できないと考えている人は全体の9割近くいる。それにもかかわらず、老後の生活資金を全く準備していない人が44%もいるのだ。しかも、定年退職後の資産形成を特に何もしていない人が41%に達している。さらに、老後の生活資金準備額が100万円未満(ゼロも含む)の人で、資産形成を特に何もしていない人は84%に上る。」(2012年10月28日発行週刊ダイヤモンド臨時増刊・通巻4454号 pp184-185)
なお、「定年後に必要とされる生活資金3,000万円」と記載しましたが、この数字は、「サラリーマン1万人アンケート」において、公的年金以外に必要となる退職後の生活資金の総額を聞いたところ、平均で2,989万円であったことに基づく数字です。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第66回『幼老統合ケア 「感情労働」という言葉に疑問』(2013年2月27日公開)
利用者・介護者の立場から考えると、「通い」「訪問」「泊まり」の3つの機能を兼ね備えた小規模多機能型居宅介護はたいへん有意義な施設でしょう。しかしながら、小規模ならではの職員の負担もあるようです。
「現在の高齢者介護施設における介護方法は、食事や入浴などが管理された巨大な集団生活に基づくものから、家庭的な雰囲気を追求する小規模で親身な方法に転換しつつある。それを体現するシステムとして、グループホームやユニットケアなどが登場してきた。このような介護方法は利用者の人権やケア方法にも配慮した優れたものであると考えられるが、被介護者グループの細分化に伴い、介護スタッフ1人当たりの労働負担が増加せざるをえないという問題がある。さらに、小規模介護実現のためには、より利用者の家族に近いケア対応が要求されることになり、それに伴い、在宅介護に特有な、感情労働としての心理的負担も高まると思われる。」(田辺毅彦:介護ストレスを再考する─在宅および施設介護ストレスの問題点. 認知症ケア事例ジャーナル. Vol.4 378-388 2012)
感情労働というのは、カナダの社会学者ホックシールドが提唱した概念で、それによると、現在の社会はさまざまなサービス業において、適切な感情の内容や表出の仕方が決められており、その感情ルールに対して有形無形の報酬が与えられます。
しかしながら、熱心にケアする介護スタッフからしてみると、そういった感情表出を「感情労働」という言葉に置き換えられてしまうと何とも言えない切ない気持ちになってしまうのではないでしょうか。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第67回『幼老統合ケア 「居酒屋に連れてって」をサポート』(2013年2月28日公開)
さて、宅老所「鴇嶺(ときがね)の家」およびグループホーム・小規模多機能ホーム「五根(ごこん)の家」の増田知子代表は、「通い慣れた居酒屋に行きたいという要望に対し、夜、実際に職員が利用者を居酒屋に連れて行ったこともあります。普通だったら『時間外だから家族に連れて行ってもらえば』となりますが、どうやったらできるかを考えることが大切」と述べており、自身が地域に根づく意気込みが求められ、ある意味利他的な精神が要求されると指摘しています(安西順子編著:基礎から学ぶ介護シリーズ・気づいていますか─認知症ケアの落とし穴 中央法規, 東京, 2012, pp78-87)。
しかしながら、最近では地域と交流してこなかった世代も多くなってきています。ですから、仕事で「地域と交流しよう」と言われても、頭では理解できても肌で感じていないため、実感が湧かないようです。増田知子代表は、そういった職員はあえて泥臭い場所に連れ回すようにしているそうです。町内会や自治会、地域行事など、何かしら得るものがあると言います。
さて、先程の居酒屋の件、酒好きの私としては気にかかる話ですので、もう少し詳しくご紹介しましょう。サブタイトルは、「出かければ、地域が変わる」です。
「『外で一杯やりたいなぁ』とつぶやいたお年寄りがいました。私たちはさっそく、希望があった行きつけの居酒屋に出かけてみました。下見はできるだけ行いたいと思っていますが、昔からある居酒屋の場合、店内がバリアフリーではなく、トイレも和式であることが多いです。しかし、リスクを考え始めるといつまでたっても出かけられません。今までの実践のなかで、うまくいくかどうか悩むのに時間をかけるよりも、覚悟を決めて出かけてしまうほうが道が開けることが多かったという自負がありました。
お年寄りが店内のトイレや段差をうまく使うことができなかったこともありました。認知症のある人が行くことで、お店の店員を驚かせたこともありました。しかしどの店も、昔から行きつけだった店です。一番輝いていたころを知っている店でもあり、職員が付き添っているので、何が起こっても入店を断られることはありませんでした。
後日談として、店側がトイレに手すりをつけてくれたり、段差に踏み台を置いてくれた例もありました。『おじいさんに来てもらって、いろいろと気がついた』『お年寄りが使いやすいということは、ほかのお客さんも使いやすいということ』と言ってくれる店もありました。
このように、私たちが地域に出かけることで、少しずつではあっても地域が変わっていくのです。」(安西順子編著:基礎から学ぶ介護シリーズ・気づいていますか─認知症ケアの落とし穴 中央法規, 東京, 2012, p83)
一方、宅老所「井戸端げんき」の加藤正裕施設長は、「地域づくりとは、要するに“近所づきあい”。難しい言葉を使うから、何か特別なことをしなければならないと勘違いしてしまうのです。井戸端げんきに集まっていることが地域交流です。地域とは出ていくものではなく、集まるもの、いつの間にかできるものです」と語ります(安西順子編著:基礎から学ぶ介護シリーズ・気づいていますか─認知症ケアの落とし穴 中央法規, 東京, 2012, pp108-117)。そんな「井戸端げんき」には、デイサービスの登録者以外にも、来たい人が来て大勢集まり「すし詰め」状態だそうです。
群馬大学大学院保健学研究科の山口晴保教授は著書において、「役割」の持つ重要性に関して言及しております。
「人間は本来怠け者です。日課を決めて動かないと、ついつい怠けてしまいます。定年退職して毎日家で過ごすようになったら急にボケてきたという方を、しばしば見かけます。すぐに認知症になるわけではありませんが、仕事が人生の目的だった方は、目的を失い意欲の湧かない生活になって、何をするのも面倒と閉じこもりがちになります。こうなると、うつ状態の悪循環に陥り、認知機能も低下してしまいます。脳は使わないでいると機能を失っていくからです。楽しいことがない日が続くと、やる気も失せ、身体活動の低下に伴って記憶も悪くなります。日課を決めて毎日規則的に動くようにすれば、心の平安に役立ちます。役割を果たすことは快をもたらし、脳の活性化に有効です。」(認知症予防 ─読めば納得! 脳を守るライフスタイルの秘訣─ 協同医書出版社発行, 東京, 2010, pp189-190)
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第68回『幼老統合ケア 新しいケアシステムが求められている』(2013年3月1日公開)
2011年の介護保険の改定において、2025年をめどに「地域包括ケア」が目標理念となっています。これは、おおむね30分以内に駆けつけられる圏域において医療と介護サービスが適正に提供されることです(三浦久幸、遠藤英俊:在宅での認知症ケア. 月刊薬事 Vol.54 1732-1736 2012)。
2010年3月に平成21年度老人保健健康増進事業による「地域包括ケア研究会報告書」(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/9600ee3fd4ba9b2c4925774a001e71d9/$FILE/20100622_1shiryou3_1.pdf)が発表されております。これは、2025年に実現すべき地域包括ケアの姿を示すために、2012年度からの介護保険事業計画の骨子を示したものです。
日本社会事業大学専門職大学院の今井幸充教授(精神科医)は、「『地域包括ケア研究会報告書』の提言は、大きく2つに分けることができる。1つは、地域ケアシステム構築のための国の基本原則と自治体の実施計画ならびに在宅サービスの抜本的な充実のあり方である。国の基本原則としてもっとも強調しているのが、おおむね30分以内の生活圏域で、生活上の安全・安心・健康が24時間365日確保できる地域のサービス体系の構築であり、住み慣れた地域で継続的な生活を可能にすることである。…(中略)…そしてこの報告書のもう1つの大きな提言が、地域包括ケアを支える幅広い介護人材を育成する基盤整備である。」(今井幸充:地域包括ケアシステムに思う. 日本認知症ケア学会誌 Vol.10・巻頭言 8-9 2011)と述べています。
厚生労働省の私的研究会として設置された高齢者介護研究会による「2015年の高齢者介護」(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/15kourei/index.html)の報告においても、主要な柱の一つとして認知症の人々に対する新しいケアモデルの確立が位置づけられています。すなわち、地域包括ケアシステムの確立です。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第69回『幼老統合ケア 家族や友人、近隣住民、ボランティアのサポートが必要』(2013年3月2日公開)
2012年8月27日付日本経済新聞の1面トップニュースは、「在宅医療に地域責任者(副タイトル:病院依存脱却へ)」という見出しの記事でした。記事内容を少しご紹介しましょう。
「厚生労働省は住み慣れた場所で医療や介護のサービスが受けられる体制を整えるため、中核となる人材を組織化する。平成24年度中に全国で7千人以上の責任者を配置する計画だ。地域の実情に応じた24時間体制の在宅医療や介護を実施する。入院できる患者数が限られる現状を踏まえて病院に頼りすぎる体質を改め、サービスの効率化も狙う。
現在の医療は病院完結型とも呼ばれ、1950年に80%だった自宅で死亡する人の割合は2010年で12%まで下がった。高齢者の長期入院による施設不足は深刻で、在宅で医療や介護を進めざるを得ない事情もある。
体制が整えば在宅医療費は膨らむ見通しだが、医療費の4割程度を占める入院医療費の伸びの抑制を期待できる。厚労省は医療費を適正な水準に戻すために長期入院の見直しを重視している。」
高齢者の長期入院を見直すには、何よりも在宅医療の充実が喫緊の課題となります。
東京都健康長寿医療センター研究所自立促進と介護予防研究チームの粟田主一研究部長は、「後期高齢者人口の増加、単独・夫婦のみ世帯の増加、認知症高齢者の増加、都市部における急速な高齢化、要介護認定者の増加などを背景にして、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが、日常生活圏域(30分で駆けつけられる圏域)において一体的に提供できる『地域包括ケアシステム』の構築が求められている。これは、近年世界的に活発に議論されているCommunity-based Integrated Careの理念と一致する。Community-based Integrated Careは、Community-based care(地域を基盤としたケア)とIntegrated care(統合型のケア)という2つの独立した概念で構成される。」と述べています(粟田主一:認知症医療ネットワーク構築の現状と課題. 綜合臨牀 Vol.60 1761-1762 2011)。
ケアマネジメントで活用する社会資源は、介護保険サービスや行政等によるフォーマル・サービス、そして家族や友人、近隣住民、ボランティア等によるインフォーマル・サポートに大きく区分されます。
地域包括ケアを推進していくためには、フォーマル・サービスだけでなく、インフォーマル・サポートを積極的に活用していくことが重要な視点となります。梨木さんが『ひょっとして認知症? Part1』の第406回のコメント欄「介護保険の変容」において語っていた「縁側カフェ」のアイデアもインフォーマル・サポートに該当するものですね。
厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室の勝又浜子氏は、医学雑誌社のインタビューの中で、「認知症カフェ」の意義についても言及しております。
「オレンジプランには、『認知症サポーター』の育成や『認知症カフェ』など、一般市民の啓発にあたる内容も多く含まれています。そうした取り組みを通して、地域住民ぐるみで『気づき』のポイントを早めていこうということです。」(認知症の「ケアの流れ」をどう変える?─これからの認知症施策の主眼と訪問看護の役割. 訪問看護と介護 Vol.18 16-20 2013)
認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)の詳細は、厚生労働省のウェブサイト(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002j8dh-att/2r9852000002j8ey.pdf)において閲覧可能です。
朝日新聞社の連載「認知症とわたしたち」第1部「気づきのとき・4─1人で抱え込まないで」(2013.1.6)においては、目黒認知症家族会「たけのこ」の一泊旅行の様子が紹介されましたね。「たけのこ」では、月に2回の交流会を開いており、認知症の人と家族が一緒に参加し認知症の人はボランティアと過ごすため、家族は介護から離れることができると報道されました。
そして、「たけのこ」の世話人・竹内弘道さんが自宅を開放して開催している談話サロン「ラミヨ」の様子も報道されました。「ラミヨ」においては、介護中の人だけでなく、みとった人、認知症に関心のある人も対象にしており、介護経験を語り合ったりする中で、ベテラン介護者がまだ介護に不慣れな介護者に助言する場面もあることが紹介されました。
こうしたカフェ・サロンの原点は、藤本クリニック(滋賀県守山市)の「もの忘れカフェ」(http://fujimoto-clinic.net/cafe/index.html)ではないかと思われます。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第70回『幼老統合ケア 「認知症でもだいじょうぶ」町づくり』(2013年3月3日公開)
認知症の人を支えるまちづくりを考えた場合、「認知症になっても、終の棲家として選択した『我がまち』に住み続けられるまちづくり」と「その人のそれまでの生活・歴史・人間関係を大切にしたまちづくり」の2点が具体的目標となります(http://www.jice.or.jp/jishu/k1/200709_zaitaku_pdf/3-2_ninchisho.pdf)。
そして、「認知症でもだいじょうぶ」町づくりに向けての具体的な取り組み内容を紹介しているウェブサイト(http://www.dcnet.gr.jp/campaign/)もありますのでご参照下さい。
2012年1月30日に開催された座談会に於いて、梶原診療所在宅サポートセンターの平原佐斗司医師は、認知症の人を支えるまちづくりという点から考えると、今後は都市部でのコミュニティー作りが大きな課題になるのではないかと指摘しました。以下にその部分をご紹介します。
「支えるということで私が一つ気になっているのは、これまで過去15年間、高齢化は日本全国一律に起こってきたのですが、今後は都市近郊が中心で、認知症も圧倒的に都市部に増えるという問題があります。埼玉ではこの30年間で3.1倍、千葉・神奈川では2.9倍、東京でも2.4倍です。ですから、認知症の方は首都圏ですごく増えていくのです。都市部では地方と比べるとコミュニティーの力がないですから、地域の力をもう一度つくり直すというプロセスが必要です。そのことが危機的な問題として出てくるのではないかと非常に心配しています。」
この意見に対して、座談会の司会を務めた北里大学医学部(北里大学東病院)神経内科学の荻野美恵子講師は、「宮崎に『かあさんの家』というのがあって、空いている民家を使って、そこに認知症や高齢者の皆さんに入っていただく。皆さんといっても、そんなに多いわけではなくて5~6人です。その方たちを子育てが終わった世代の女性が世話をしていく。今までの生活に近いような環境で集団生活ができるということで、精神的にもとても落ちついて過ごせるのだそうです。そういう施設が増えるといいのかなと思いますね。とくに都市部は人口が多いですから、雇用創出という面も含めて、できないことではないと思いますが。」と述べております(荻野美恵子 他:座談会・非専門医がどのように認知症に向き合ったらよいか? 内科 Vol.109 847-860 2012)。
2011年8月20日の朝日新聞・生活では、高齢者、障害者、子育て世代が共に支え合い暮らす現代版「長屋」(広島県東広島市)がコミュニティー再生の一つの手段になるのではないかと紹介されていましたね。
この現代版「長屋」とも比喩された「C-CORE東広島」(http://communitysystem.web.fc2.com/works/work1-building.html)は2011年3月にオープンした5階建ての賃貸マンションです。このマンションの1階には、子どもの居場所づくりをするボランティアの事務所や、地域住民の要望を受け開設された、障害者の就労支援を目的に気軽に集えるカフェもあるそうです。
『ひょっとして認知症? Part1』の第181回『認知症を生きるということ(その5)』においても、「幼老統合ケア」を実施している「ベルタウン」をご紹介し、「地域包括ケア研究会報告書」において提言された「おおむね30分以内の生活圏域で、生活上の安全・安心・健康が24時間365日確保できる地域のサービス体系の構築」に先進的に取り組んだ斬新なシステムと言えるのではないかと私は述べました。大阪府堺市の複合型福祉施設「ベルタウン」は、一階が通所リハビリテーションと通所介護サービスなど、二階が保育園ベルキンダー、三~四階が介護老人保健施設ベルアルト、五~七階が特別養護老人ホームベルライブで、建物自体を一つのタウン(街)と捉えていましたね。
一つのタウンとして捉えつつも、各階ごとに一定のしきりがあれば、多世代共生において大きな支障も生じないのかも知れませんね。しかしながら垣根が低ければ、有料老人ホーム「アクラスタウン」での様子を綴っている今村美都さんが報告されておりますように、「私たち親子が実際に住んでみての率直な感想は、ハード面でもソフト面でも老人ホームに一般の人間が住むのはまだまだハードルが高い」という状況がどうしても生じてしまうのでしょうね。
朝日新聞アピタル「ひょっとして認知症-PartⅡ」第71回『幼老統合ケア 認知症の元教育ママが大活躍』(2013年3月4日公開)
三重県桑名市において取り組まれている託老所と隣接する保育園が共有のスペースを作り、高齢者と子どもが触れ合う活動の様子は、「認知症フォーラム.com」の動画サイトにおいて閲覧できます。
三重県桑名市にあるウエルネス医療クリニック(http://wellness-medicalclinic.jp/)の多湖光宗院長は、認知症高齢者の役割づくりの具体例として、認知症高齢者の行動障害を逆に活用する試みを紹介しています(苛原 実・編著:認知症の方の在宅医療 南山堂発行, 東京, 2010, pp165-171)。
「『しつけ』の語源は『しつづける』である。認知症高齢者の行動障害の『繰り返し』が役立つ。普通の大人なら1回か2回でイヤになったりあきらめたりすることを何回もしつこくする。『何回も教える。何回もしかる。何回もほめる』、それも本気でする。この能力を生かすべきだ。以前学童保育『パンの木』の子どもたちを『宿題は無理。学習障害児の集まり』と元教員の指導員らは見放していた。また、『宿題しないのも個性のうち』と親や子どもたちには体裁を繕っていた。認知症の元教育ママたちは、宿題するのは子どもの義務で当たり前と思っており、①騒いでいる子を『本気でしかり』机に座らせる、②机に座って落ち着くまで見守る、③できているかチェックして、できていればほめる、このことを繰り返し行い、子どもたちの宿題習慣をつけるのに大きな貢献をした。なお、子どもはこの繰り返しを通常平気で楽しめる。また十分な時間もお互いにある。」
ウエルネス医療クリニックの試みは、幼老統合ケアの実践例として「高齢者住宅新聞」(http://www.koureisha-jutaku.com/news2011/news_110805002.html)でも紹介されています。
多湖光宗院長らは2001年より学童保育を併設するグループホームを設立しており、「認知障害の『トンチンカンさ』が癒しとなり、引きこもりのケア、非行少年の更生などに役立つこともわかってきた。『ひかりの里』でも荒れた子どもが素直になっていくことが体験された。」と報告しています(多湖光宗:能力活用セラピー. 日本臨牀 Vol.69 Suppl10 126-130 2011)。
また多湖光宗院長は、更正だけではなく「青少年の育成」にも有用であると指摘しています。
「見て見ぬふりをし、あとで陰口を言う大人の中では子どもたちはうまく育たない。喜怒哀楽が素直で、本気で怒り、心から喜んだり悲しんだりする認知症高齢者たちこそ、子どもたちが表情を読みとる訓練に必要な存在だ。全員から悲しまれるとこれはいけないことと思うし、1人のおばあちゃんからしかられて、ほかは『まあいい』という場合には、あのおばあちゃんに気を付けようと判断するようになり、社会性が身につく。」(多湖光宗:認知症の人の底力を地域に活かす. Dementia Japan Vol.26 28-35 2012)
パーソンセンタードケアを唱えたトム・キットウッドは、「認知症という病気は、神経障害、全身の健康、生活史、性格や個性、その人を取り巻く家族や地域社会という5つの因子によって形作られる」(水野 裕:DCMをめぐって. 老年精神医学雑誌 Vol.15 1384-1391 2004)と指摘しています。住み慣れた地域・住み慣れた家で少しでも長く過ごせるように、認知症の人を地域から支えていくシステムの構築が喫緊の課題となっております。
グループホーム「ふぁみりえ」ホーム長の大谷るみ子さんは、子ども目線から見た徘徊について紹介するなかで、認知症の人を地域で支えていくことの大切さについて語っています(大谷るみ子:人生の舞台は今、グループホームから地域へ─豊かな人生を支援する. 現代のエスプリ通巻507号 ぎょうせい発行, 東京, 2009, pp132-145)。そのご意見を紹介し本稿を閉じたいと思います(一部改変)。
「入居者のひとり、岩花さんは、もと小学校の校長先生。その仕事ぶりが表彰を受けられ、世界一周旅行をした方である。未だに世界一周旅行の話は輝きを放っている。定年退職後は民生委員の会長のお役目を務められ、自分でも放浪癖があったと言われるくらい校長の割には遊び心豊かな方だったようだ。奥さんを亡くされた後、徐々に認知症が目立ち始め、幾度となく放浪癖まがいの徘徊を繰り返され、次第に行方不明のために捜索願を出されることが増え、在宅生活の限界となり、平成十五年九月から入居されている。岩花さんのところには、毎日のように孫のさあやちゃんが通ってきた。ランドセル背負ってまずふぁみりえに『ただいま~』と帰って来る。…(中略)…この岩花さんの物語は、平成十五年度に大牟田市認知症ケア研究会が作成した絵本『いつだって心は生きている~大切なものを見つけよう~』の第三話のモデルとなっている。孫のさあやちゃんが、徘徊で行方不明になったおじいちゃんが、三日目にひょっこり家に帰ってきて『楽しかったあ』と言うのを聞いて、おじいちゃんの徘徊を冒険ととらえるという子どもの目線で描かれている。この絵本を通して、子どもたちに認知症の人の豊かな感情や力、子や孫を思う愛情、認知症でも大切な人ということを伝え、その子どもたちがまた大人や地域を変えてくれることを願っている。」